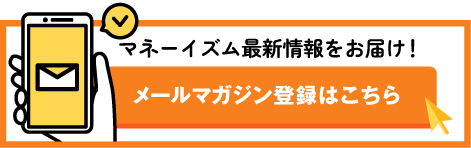法人の代表者を変更すると、税金の取り扱いが通常とは異なってきます。たとえば、役員報酬を期中に増額や減額をしても、例外として経費で落とせます。では、税法上の代表者とは何でしょうか?社長という肩書を持つ人のことを指すのでしょうか?今回は税法上の代表者、法人の代表者変更に伴う税金の取り扱いについて解説します。
そもそも法人の代表者とは?
代表者変更に伴う税金の取り扱いについて理解するため、法人の代表者について知る必要があります。それでは、詳しく見ていきましょう。
法人の組織は2種類に大別できる
株式会社の組織は「取締役会非設置会社」と「取締役会設置会社」の2種類に大別できます。
| 組織の種類 | 内容 |
|---|---|
| 取締役会非設置会社 | 株主総会により、株主が株式会社の意思決定をすべて担う組織形態 |
| 取締役会設置会社 | 株式会社の意思決定の一部を取締役会に移譲し、取締役がそれを担う組織形態 |
なお、取締役会設置会社は次の全ての条件を満たす必要があります。
・取締役は最低3人以上が必要
・1人以上の「監査役」または「税理士または公認会計士の資格を有する会計参与」が必要
・最低でも3ヵ月に1度の頻度で取締役会の開催が義務付けられている
取締役会非設置会社の代表者とは?
株式会社の代表者は、厳密にいうと社長という肩書を持つ人ではありません。これは会社法で定められており、取締役会非設置会社の場合は次の通りです。
・原則:各取締役が代表者
・特例:各取締役から代表取締役(法人の代表者)を選任(特定の人の中から選ぶこと)することができる
なお、取締役の選定(不特定多数から選ぶこと)と解任(辞めさせること)は株主が行います。
取締役会設置会社の代表者とは?
取締役会設置会社の場合、取締役の中から代表取締役を選任することが義務付けられています。その選任は基本的に取締役会で行います。ただし、定款で定めている場合は株主総会でも代表取締役を選任することが認められています。
代表取締役の権限について解説
代表取締役は株式会社の業務に関する一切の権限を持ちます。たとえば、決算書や確定申告書など重要書類を作成する権限があります。また一方で、代表取締役は法人の訴訟に対する責任を負うことになります。
代表者を変更した場合の役員報酬について解説
法人の代表者を変更すると、「代表取締役に就任した取締役」や「代表取締役を退いた人」に対する役員報酬の取り扱いが原則と異なります。そこで、代表者変更に伴う役員報酬の取り扱いについて解説します。
役員報酬は年度途中で変更できないのが原則
そもそも役員報酬を経費で落とすためには、定期同額給与である必要があります。定期同額給与とは、役員報酬の変更を年度初めから3ヵ月以内とし、1カ月以下のスパンで支給することを指します。
代表者変更の場合、年度途中でも役員報酬は変更できる
前述の通り、役員報酬の変更を年度初めから3ヵ月以内に行うのが原則です。しかし、代表者変更など役員の職制上の地位が変更をされた場合、例外的に年度途中で役員報酬を変更しても定期同額給与として経費で落とせます。
たとえば、取締役から代表取締役に昇格した場合は、役員報酬を年度途中で増額しても増額分を経費で落とせます。一方、代表取締役が非常勤役員の取締役に退いた場合、年度途中で役員報酬を減額しても、減額分を経費に計上することが認められます。
ただ、「役員の職制上の地位が変更」とは、単に「常務から専務に昇格した」などと自称するだけでなく、「定款の規定」や「株主総会や取締役会の決議による手続き」により裏付けられることが求められます。
代表取締役を退く場合の退職金について解説
代表取締役を退く場合、たとえ法人に在籍していても役員を退職したものとして取り扱われます。そのときに支給する退職金は法人の経費で落とすことができます。しかし、支給額が多額になる傾向のため、形式だけの退職により法人の利益操作に利用される恐れがあるため、代表取締役を退く場合の退職金を法人の経費で落とすために制限が設けられます。
退職金と認めらないときのリスク
代表取締役を退く場合に支給される退職金は、税務調査で役員賞与と認定されるリスクが潜んでいます。そこで、退職金と認められないときの個人と法人、それぞれの増税額を紹介します。
例)
勤続年数30年の代表取締役に役員退職金として1,000万円支給した場合
(1)個人の増税額
退職金と認められない場合、退職所得ではなく、給与所得(役員賞与)として扱われます。所得金額の違いは次の通りです。
①退職所得
・支給額1,000万円-退職所得控除額(※)1,500万円>0円→所得金額と税金は0円
※退職所得控除額の計算方法
70万円×(勤続年数30年-20年)+800万円=1,500万円
②給与所得
・支給額1,000万円-給与所得控除額220万円=所得金額780万円
このように個人の所得金額の差は最低でも780万円となります。
(2)法人の増税額
退職金と認められない場合、役員賞与として取り扱われます。役員賞与は法人の経費で落とせないため、所得金額に加算され、法人税などの課税対象となります。たとえば、法人税率が30%の場合、「1,000万円×30%=300万円」の増税となってしまいます。
代表取締役を退職したと同じ取り扱いができる3つのケース
そもそも退職したものとして取り扱われることが退職金として認められる大前提です。法人税法基本通達では、代表取締役を退き法人に在籍しても、退職したのと同じ取り扱いがされるケースを3つ例示しています。
・常勤役員から非常勤役員になる
・取締役から監査役になる
・代表取締役を退任後、給与がおおむね50%以上減少した場合
しかし、実質的に経営上主要な地位にある場合は退職したものとして取り扱われません。
経営上主要な地位にある場合とは?
おもに次の複数の要素を加味して経営上主要な地位にあるかどうかを判断します。
(1)出勤の頻度と勤務時間が退く前とあまり変わらない
たとえば、出勤の頻度と勤務時間が常勤役員と同じ場合などが挙げられます。
(2)経営の重要な意思決定に携わっていること
たとえば、代表取締役を退いた後に製品開発など経営の根幹に携わっていたり、銀行交渉をメインで行ったり、退いた後でも銀行融資の連帯保証人になったりする場合は経営の重要な意思決定に携わっていると判断されます。
また、役員人事などに影響を及ぼしたり、主要な取引先の営業を担当したり、支店や組織などの設置・廃止の決定に携わったりするなども、経営の重要な意思決定に含まれます。
(3)本人の株式保有比率が高い(例50%超など)
株式を保有していれば法人の重要な意思決定ができる立場にあります。たとえば、株式保有比率が50%超の場合、役員の選定や解任を自由に行うことができます。
(4)代表取締役を退いたことを知らない取引先が存在すること
この事実をもって、直ちに経営上主要な地位にあるどうかを判断するわけではありませんが、税務調査で争点になる部分です。たとえば、ほとんどの取引先が代表取締役を退いたこと知らないということは、対外的に代表取締役と認識されていると考えるのが自然でしょう。その場合、経営上主要な地位にあると判断される可能性が高いです。そのため、代表取締役を退いた場合は取引先に通知すべきでしょう。
まとめ
法人の代表者である代表取締役の権限は強いです。そのため、役員報酬や退職金の税金の取り扱いは、通常の場合と異なります。それを生かせば節税につながります。しかし、やり方を間違えると税務調査で増税されるリスクが潜んでいます。代表者を変更する場合、役員報酬や退職金の支給については事前に専門家に相談することをおすすめします。
参考文献・URL
- http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC0000000086&openerCode=1#2474
- http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC0000000086&openerCode=1#2548
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5203.htm
- http://www.e-hoki.com/tax/taxlaw/7800.html