2025年度から導入される?政府が育休後の時短勤務者に賃金10%分の給付を検討か
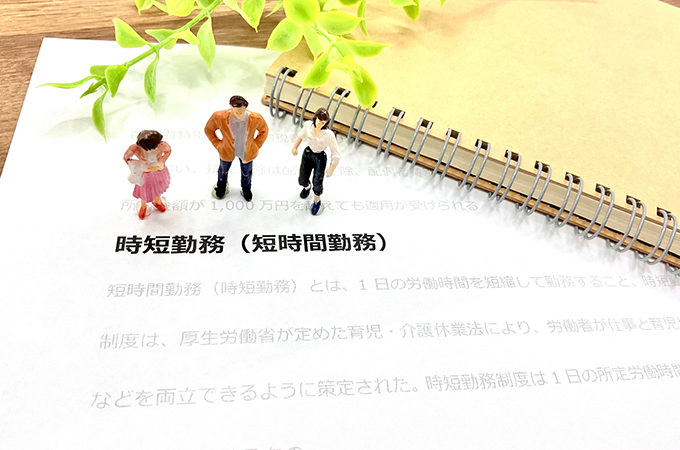
政府は、育児のために時短勤務をする労働者に対して賃金の10%を給付する方向で検討していることを明らかにしました。2025年度からの導入を目指し、来年の通常国会に提出する雇用保険法改正案に盛り込む予定です。
対象は2歳未満の子を持つ労働者
そもそも時短勤務とは、育児や介護などの事情がある労働者が、所定労働時間よりも短い時間で勤務できる制度のことを指します。
対象となるのは以下の労働者です。
- 3歳に満たない子を養育する労働者
- 1日の所定労働時間が6時間以下ではない労働者
時短勤務の適用期間は、原則として「子が3歳に達する日まで」とされています。勤務時間は、原則として1日6時間です。ただし、業務の都合等により、就業規則で定めた範囲内で、1日4時間以上8時間以内の間で調整することができます。時短勤務の詳細については、厚生労働省のHPにて確認ができます。
冒頭の話に戻すと、厚生労働省は、この措置を「育児時短就業給付(仮称)」として雇用保険に組み入れることを計画しているようです。今回、給付の対象となるのは2歳未満の子どもを持ち、時短勤務により収入が低下した労働者となります。労働時間や日数に制限は設けず、時短勤務で収入が下がる家庭を経済的に支え、子育てしやすい環境を整えるのが狙いとしています。
政府は既に、両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合、手取り収入が休業前から変わらない水準にまで「育児休業給付金」の支給率を引き上げることも検討しています。
これらの政策の背景には、少子化対策があります。政府は、子どもや家族に関する政策を強化していく方針を示しており、「育児時短就業給付」の創設も、6月に閣議決定された「こども未来戦略方針」の一環として位置づけられています。
この方策により、子育て中の家庭の経済的負担を軽減し、育児と仕事の両立を促進することが期待されています。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。
新着記事
人気記事ランキング
-
「相互関税」の影響でどう変わる?企業が今すぐ始めるべき事例を解説
-
日鉄のUSスチール買収、頓挫による影響はどれぐらい?
-
2025年の税制改正により何が変わった?個人・企業のポイントを解説
-
会社の資産と社長個人の資産が“ごっちゃ”になっていませんか? そのリスクと対処法を解説
-
知っておきたい!海外留学中の子どもを扶養控除の対象とするために気を付けること
-
トランプコインは投資チャンス?投資する前に知るべきリスク
-
飲食店の倒産が過去最多!その要因と生き残り戦略を徹底解説
-
初任給の引き上げ最新動向と業界別の比較や影響について解説
-
遺族が知っておきたい!死亡後に行うべき手続きの流れと注意点
-
確定申告は進んでる?今だからこそ見直したい個人事業主ができる節税方法3選!


















