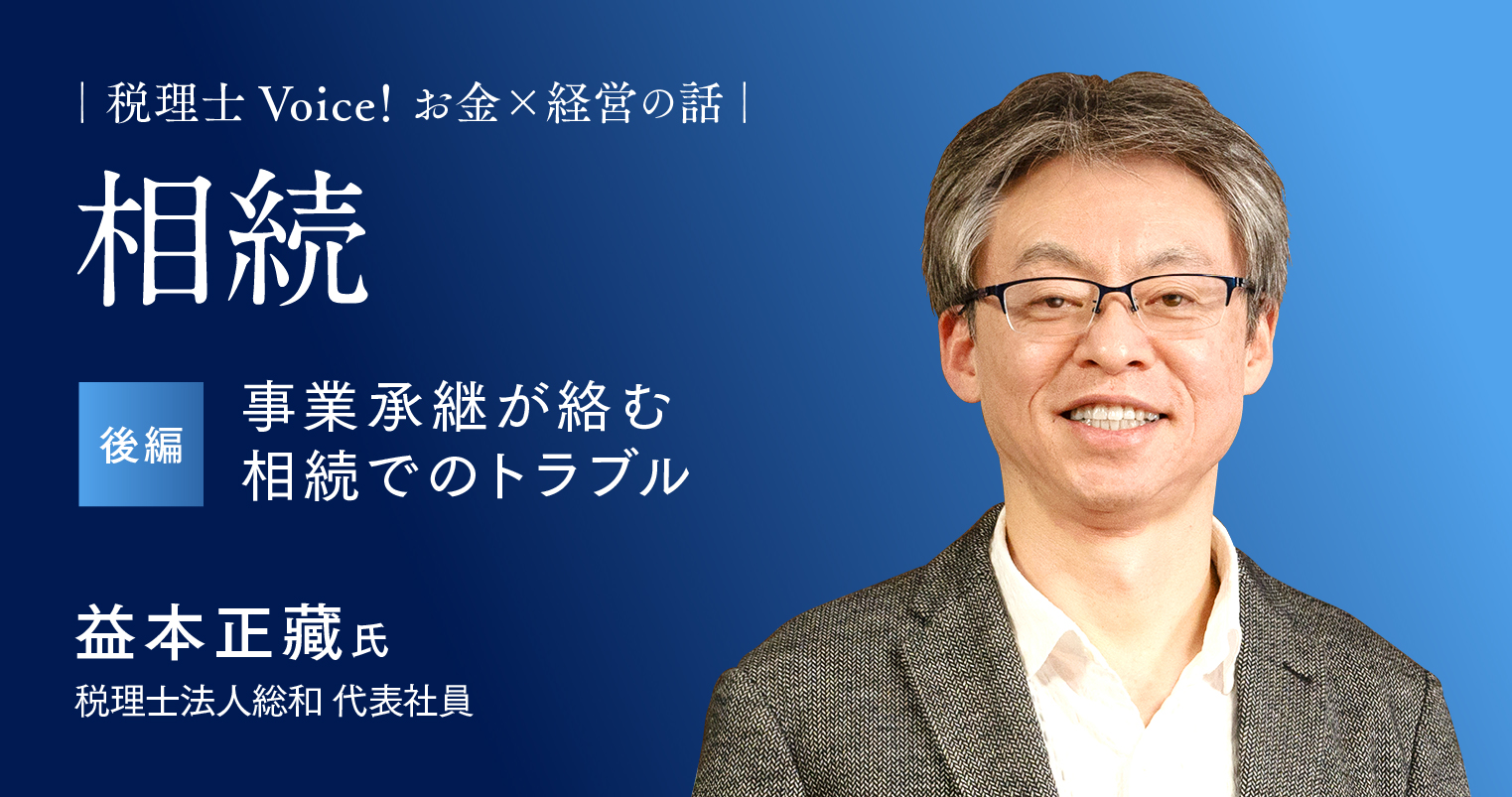【生前贈与 前編】2024年から変わった生前贈与の仕組み どう使えばいいのかは、家族ごとに違う
税理士法人AOIみらい CEO 杉山信也氏(中)、理事 長坂京氏(右)、相続担当 小林弘展氏(左)2024年1月から生前贈与(暦年課税、相続時精算課税)の仕組みが大きく変わった。相続にも影響する制度改正とはどんな内容で、どのような使い方ができるのか。相続税、贈与税など資産税関係のサポートに定評のある税理士法人AOIみらいの杉山信也氏(CEO)、長坂京氏(理事・税理士)、小林弘展氏(相続担当)に、生前贈与のポイント、注意点なども含めてお話しいただいた。
記事は、「前編」で今回の制度改正の内容と影響などについて、「後編」で制度を活用した事例、生前贈与の注意点などを中心にまとめた。
相続の事前相談は増えている
――最初に、事務所の概要をお聞かせください。
杉山(敬称略) 理事長の長坂修が1987年に立ち上げた個人事務所が2020年に法人化し、当社は現在4期目になります。パートさん含めて従業員26名の体制で、顧問先として160を超える法人と、400件程度の個人の顧客がいます。
不動産をお持ちの方を相続対策でお手伝いしているケースも多くて、贈与とか相続とかのいわゆる資産税関連の案件は、細かなものも含めて年間30~40件ほど扱っているんですよ。
――貴社のホームページには、「相続発生後にも生前対策にも対応」とありますが、実際にはどんなお客さまが多いのでしょう?
杉山 相続の事前相談自体は、だいぶ増えてきております。「相続税が不安だから、とりあえず不動産などの財産を評価してほしい」といったパターンです。一方で、相続になってから、「どうしたらいいですか」と、当社のお客さまの紹介や税理士紹介会社などを通じて来られるケースも、やはり少なからずあります。

長坂(敬称略) 生前贈与に関しては、子どもなどに財産を渡したいという思いはあるものの、そもそも贈与税の仕組みをきちんと知っている方は、そんなに多くありません。「贈与税は高いと聞くけれど、実際にはどのくらいかかるのか」といったところが、まずは相談の入り口になります。
杉山 そうですね。当社のお客さまには、相続税対策をきっかけに贈与を考え始める方も少なくないんですよ。土地をたくさん持っているものの、現金は僅かしかない。そうなると、相続税の支払いのために、相続人が先祖代々の土地を「切り売り」せざるをえなくなるかもしれません。その対策として、アパートなどの収益物件を建てたりして納税資金の確保に努めるのですが、そのうちに今度は現金資産が増えてくるわけですね。
現金資産が増えることも相続税が膨らむ要因になりますから、ある程度は生前贈与で渡していこうか、という発想になる。ただ、ではどうしたらいいのかについて、知識をお持ちの方は稀です。
贈与税はどう変わったのか
――その生前贈与ですが、今年の1月から、課税制度が大きく変わりました。このことについて、お客さまはどのくらい関心をお持ちですか?
長坂 お客さまの中には、不動産所得の確定申告の際などに、「ネットで見た」とか「テレビでやっていましたね」とかおっしゃる方もいます。で、「節税になるのなら、自分もやってみようかな」と。
でも、そういうのは、ある程度の財産をお持ちで、常日頃から相続について気にされている方ですよね。新しい制度はスタートしたばかりですし、ほとんどの人は、やっぱり「よくわからない」というのが実情だと思います。
――今回の制度改正では、歴年課税によるいわゆる暦年贈与と、相続時精算課税の両方に手が加えられました。
長坂 暦年贈与は、贈与分の相続財産への持ち戻し(※)の期間が、相続発生前3年から段階的に7年まで延長されます。暦年贈与には、年間110万円までは非課税という基礎控除があるのですが、それを使った贈与可能期間が4年短縮されるわけですから、相続税対策としては大きなマイナスといえますね。
※暦年贈与の持ち戻し:“駆け込み贈与”による「税逃れ」を防ぐために、被相続人(亡くなった人)が亡くなる直前に贈与した分を、その財産に戻して(加算して)相続税を計算すること。この期間が3年から7年に延長された。
杉山 余談……でもないのですが、この持ち戻しというのは、我々にとってもけっこう手間のかかる仕組みなんですよ。亡くなった方のその期間の贈与額を正確に追いかけなくてはなりませんから。それが7年まで延びるというのは、かなりやっかいです(笑)。
――税理士業界にも影響があるかもしれないわけですか(笑)。
長坂 一方、2,500万円まで贈与税ゼロで生前贈与することができ、税金は相続になったときに相続税で「後払い」するという相続時精算課税のほうには、今までなかった110万円の基礎控除が新たに認められました。しかも、暦年贈与のような持ち戻しの仕組みはなく、相続ギリギリまで非課税枠を使った贈与が可能です。税金面では、逆にメリットが生まれました。

小林(敬称略) この制度を使うためには、税務署への届け出が必要なのですが、以後は贈与額が基礎控除額以下の場合、暦年贈与と同様、いちいち申告しなくてもOKなんですね。使い勝手も非常にいいと思います。
どちらが有利なのかは、ケースバイケース
――そうしたことも踏まえると、納税者は今後、メリットが増した相続時精算課税を使うべきなのでしょうか?
杉山 今の話にもあったように、相続時精算課税による贈与を行うためには、相続時精算課税の選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の3月15日までに税務署に届出を行う必要があります。また、いったんこの制度を使うと、暦年贈与に変更したり、戻ったりすることはできないんですね。そうしたこともあって、以前は暦年贈与に比べて、かなり「敷居の高い」方法だったわけです。
でも、「持ち戻しのない基礎控除」が設けられたことで、あえて相続時精算課税を積極的に使う意味が大きくなりました。逆にいえば、なんとなく歴年贈与をしていると、非課税で渡されたと思っていた財産の多くが、相続財産に戻されてしまうリスクがあります。
ただし、だから「相続時精算課税にしましょう」と、単純にいえないところが、贈与の難しさなんですよ。どちらを選ぶのかは、やはりケースバイケースといえます。
――それはなぜですか?
杉山 まず、110万円という基礎控除額を意識した金銭贈与に主眼を置く場合を考えてみます。あえてシビアないい方をすれば、年齢や病気などで余命が限られているならば、基礎控除が新設された相続時精算課税で譲るのが正解でしょう。贈与が短期間であっても、持ち戻しされることはないですから。
一方、何十年かけて贈与していけばいいという人が、わざわざ相続時精算課税にする必要があるのかどうかは、やはり検討の余地があります。なんらかの事情で歴年贈与にしたいと思っても、できなくなりますし。
相続税との兼ね合いもある
杉山 また、資産額によっては、相続税との比較も必要になる場合があります。相続税は、遺産額が大きいほど税率も上がっていく累進課税になっていて、最高税率は55%です。贈与の期間がどれだけあるのかにもよりますが、相続時にこのレベルの税率の適用が確実な遺産額が大きいケースでは、30%ぐらいの贈与税を払ったとしても、生前贈与でまとまった財産を渡していったほうが、節税になることがあるんですね。相続財産を減らすことで相続税の税率を下げ、トータルの納税額を減らすわけです。
このスキームで使えるのは、暦年贈与です。相続時精算課税にすると、相続の際に基礎控除を超えた贈与分を相続財産にプラスして相続税を計算することになりますから、結局高い税率が適用されてしまいます。

小林 昨年、父親が資産家の方からご相談いただいて実行した贈与の事例は、まさに今の話に当てはまります。お父さんは高齢で、いつ亡くなってもおかしくないのだけれど、このままだと高額の相続税が避けられない。しかし、一気に贈与したりすれば、とんでもない贈与税がかかってしまう、という状況でした。
そこで、昨年は、とりあえず税率20%の暦年贈与で、ある程度まとまった現金の贈与を受けることにしました。ただ、話に出ているように、2024年から相続時精算課税に持ち戻しのない基礎控除ができましたから、今後はそれを使って相続が発生するまで贈与してもらう、という選択肢が増えました。それも踏まえて、さらに暦年贈与でまとまった財産を移動させるのか、お父さんの状態も見ながら判断していきましょう、という話になっています。
長坂 このように、歴年贈与か相続時精算課税を使うべきなのかは、財産の額や種類、渡していく期間などによって変わってきます。特に高額の財産を持つ方は、早めに専門家に相談してほしいと思います。
「後編」では、生前贈与のノウハウや注意点などについて、さらに事例も紹介していただきながら、インタビューを進めます。
注:記載の「事例」に関しては、情報保護の観点により、お話の内容を一般化したり、シチュエーションなどを一部改変したりしている場合があります。
「世の中からお金に関する不安と面倒をなくす」をミッションに掲げ、税理士と経営コンサルタントが連携し、お金に関する知識・経験を提供する税理士事務所。税務・会計顧問だけではなく、経理代行、経営コンサルティング、相続など、人員体制や事業支援に合わせて経営者をサポート。
URL:https://aoi-mirai.jp/