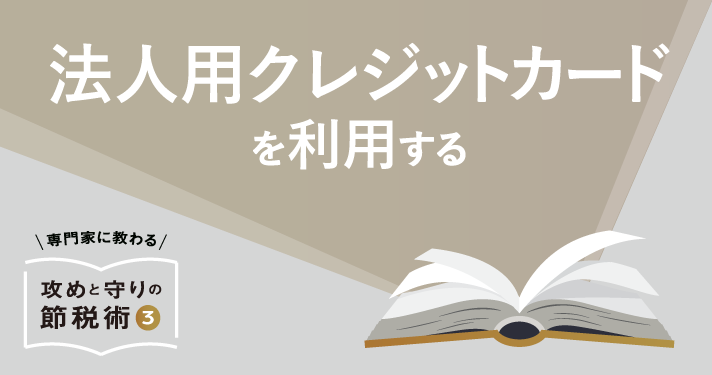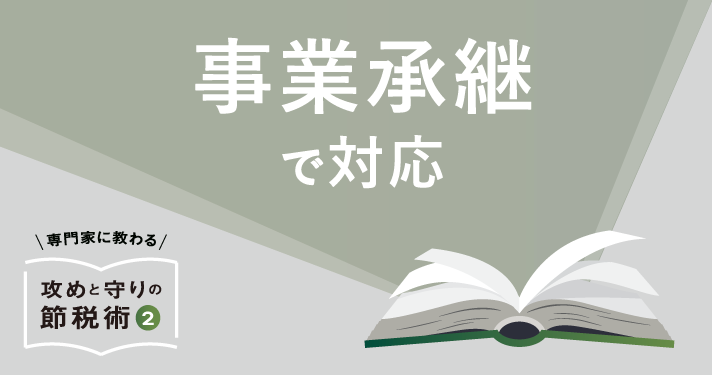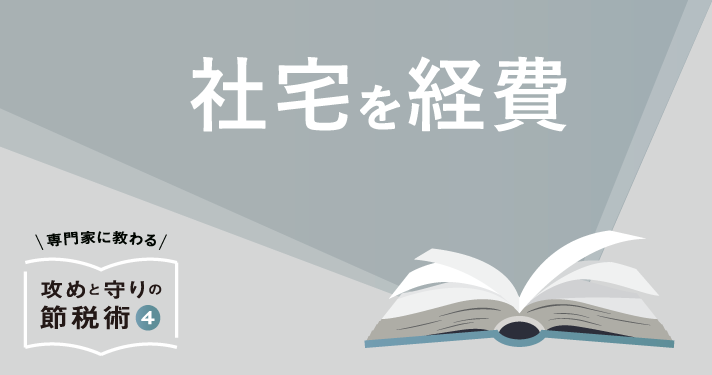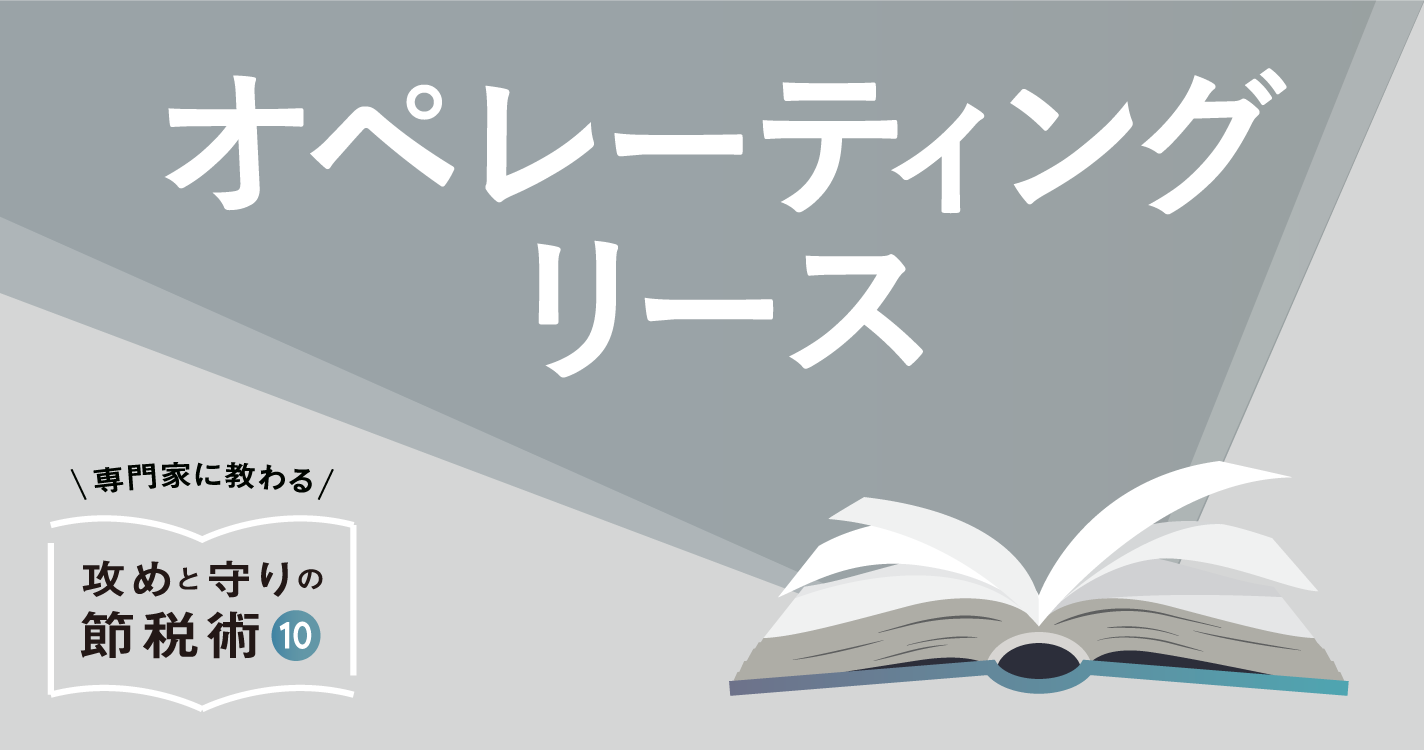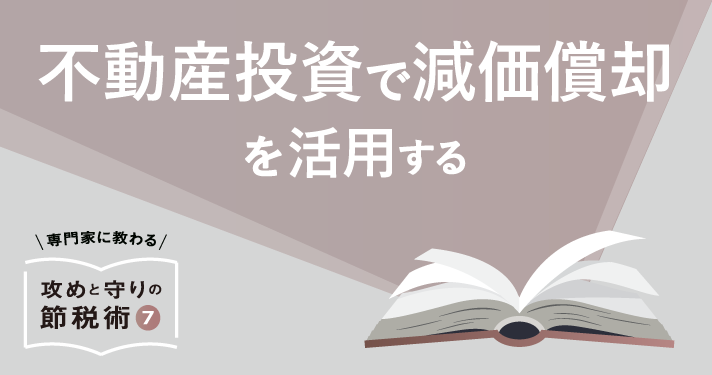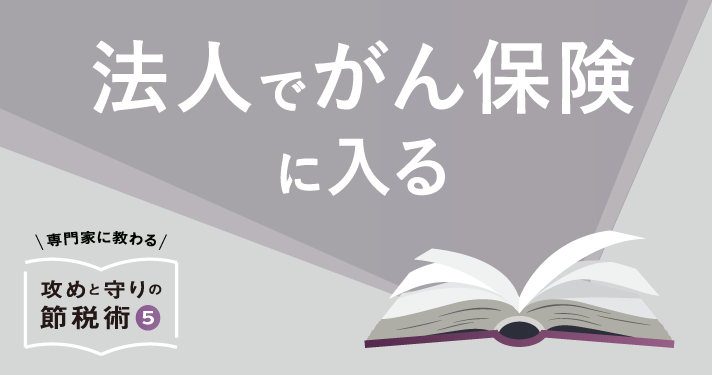
「法人でがん保険に入る」
という節税術
生命保険の保障内容の一つに、がんになったとき保険金の給付を受けられる「がん保険」があります。「がん保険」は個人はもちろんのこと、法人でも契約可能です。今回は、法人で「がん保険」に入ることの節税メリットや注意点を解説していきます。
まずは知りたい
「がん保険」とは何か?
医療保険との組み合わせで疾病を幅広くカバー
例えば、がんに罹った際に手術や治療で長期間の入院が必要になる場合があります。治療可能な病気になったとはいえ、がんで入院した場合、入院期間が長期間になることや先が見えないことも考えられます。結果として入院にかかる費用が高額になり、生計への負担が重くなると不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
そのような場合にお勧めしたいのが「医療保険」との重複契約です。がん保険が、がんに罹患した場合のみ給付対象となるのに対し、医療保険はがんに限らずどのような疾病が原因であっても給付対象となる商品が多いのが特徴です。万が一入院した場合、がん保険と医療保険の給付金を重複して受け取ることができますし、がん以外の疾病に備えることもできます。保険が重複することで保険料負担が増加する、がん保険と異なり医療保険は給付対象の入院日数に上限があるといったデメリットはあります。しかし、複数の保険を組み合わせて幅広く備えることで、得られる安心感は大きくなります。
法人向けの「がん保険」とは何か?
生命保険契約といえば、個人で契約するものというイメージを持っている方もいると思いますが、がん保険は法人でも契約できるということをご存じでしょうか。法人はその名のとおり「法のもと人格(法人格)を付された組織」です。しかし、法人が生命保険契約を結んだとしても、法人自体が被保険者となることはできません。法人契約で被保険者となれるのは内部の役員や従業員です。なお、保険金の受取人になれるのは契約者である法人に限らず、被保険者である役員や従業員もなることができます。ただしこの場合、契約内容によっては保険料が被保険者に対する給与扱いとなり、源泉所得税の問題が発生しますので注意が必要です。
がん保険の掛金と法人の経理処理について
次に、法人が保険料を負担した場合の経理処理について解説します。保険料の経理処理については2019年の保険通達のルール改正によって、非常に複雑になっています。ここでは「定期保険」の経理処理を例にあげてみます。
| 最高解約 返戻率 |
資産計上期間 | 資産計上額 | 資産取崩期間 |
| 85%超 | A.Bいずれか長い期間
A.保険開始日から 解約返戻率が 最も高くなる期間終了の日 B.Aの期間経過後に (当年の解約返戻金相当額 -前年の解約返戻金相当額) ÷年換算保険料相当額」が 70%を超える期間 (資産計上期間が5年未満 となる場合には5年間) (保険期間が10年未満の 場合には保険期間の 当初5割相当期間を 経過する日まで) |
1. 保険期間の 当初10年経過する 日当期支払保険料 ×最高解約返戻率の90% 2. 保険期間の 11年目以降 当期支払保険料 ×最高解約返戻率の70% |
解約返戻金が 最も高くなる 期間経過後から 保険期間の 終了の日まで |
| 70%超 85%以下 |
保険期間の 4割相当経過まで |
保険料の60% | 保険期間の 7.5割相当経過後 |
| 50%超 70%以下 |
保険期間の 4割相当経過まで |
保険料の40% | 保険期間の 7.5割相当経過後 |
| 50%以下 | - | 0 (全額損金経理) |
- |
法人契約の生命保険契約といえば、かつては節税効果が期待できる保険商品が数多くありました。掛金の全額を保険料として全額損金経理することで、法人税等の節税効果を合わせた返戻率(実質返戻率)が掛金を大きく上回る商品もあり「保険契約=節税」というイメージがあったのは事実です。しかし、生命保険契約の本来の目的は将来起こり得るリスクを保障することであって、法人の課税回避行為のために存在するものではありません。2019年の保険通達の改正により税務当局がこのような目的を逸脱した生命保険契約を禁止したため、現在では返戻金が掛金を上回る生命保険契約はありません。
法人でがん保険に入る
節税メリット
以前と比べると節税効果は薄くなっていますが、解約返戻率が50%以下の契約については保険料を全額損金にできる場合があり、一定の節税効果はあります。
節税メリット1 従業員の福利厚生の一環として節税
従業員ががんに罹った場合、手術や治療などの負担が生計を圧迫することも充分考えられます。生計が成り立たなければ業務に専念することもままなりませんので、会社にとってもマイナスになります。法人契約のがん保険に加入していれば保険料は会社が負担してくれますし、万が一がんになった場合にも従業員は給付金を受け取れます。現在では、従業員に対する福利厚生目的でがん保険に加入する企業も増えています。がん保険は掛け捨てタイプの定期型と終身型がありますが、掛け捨てタイプの定期型だと解約返戻金がなく、被保険者1人あたりの年間保険料が30万円以下であれば全額損金として計上できる場合があり、保険料も割安です。
節税メリット2 退職金の原資目的として節税
がん保険のなかには、解約した際にお金が返戻されるものがあります。例えば積立型の終身がん保険は解約したときに返戻金が貰えるのです。この仕組みを利用して、早い段階でがん保険を契約し、退職に合わせて解約すれば、退職金の原資として使えるという仕組みです。がん保険の保障を受けつつ退職金の積立もできるというメリットがあります。保険料を全期払いではなく短期払いで払い込む場合、被保険者1人あたりの年間保険料が30万円以下であれば全額損金として計上できる場合があります。
法人でがん保険に入る際の
注意点
法人でがん保険に入る際は、以下の点に注意が必要です。
注意点1 福利厚生費として損金計上するには普遍的加入が原則
がん保険料を福利厚生費として損金計上するには普遍的加入(対象となる従業員全員が加入)が原則です。普遍的加入でなければ、がん保険料は福利厚生費ではなく被保険者に対する給与として課税される可能性があります。
注意点2 福利厚生規程を作成しておく
節税を主な目的とする法人保険契約は税務上問題視されることがありますが、福利厚生やリスク管理といった正当な目的であれば税務上問題となることはありません。がん保険料を福利厚生費として損金計上する際は、税務調査に備えて福利厚生規程を作成しておきましょう。福利厚生規程に、「従業員の福利厚生のためにがん保険に加入する」旨を明記しておけば、税務調査が入った場合でも、がん保険料を福利厚生費と認めてもらいやすくなります。
注意点3 節税効果は薄い
解約返戻率が50%以下の契約については保険料を全額損金にできますので、一定の節税効果はあります。しかし、前段でも述べましたが、現在ではかつてのような大幅な節税を目的とした生命保険契約はありません。掛金に対して返戻される金額の割合(単純返戻率)や節税効果を含めて返戻される金額の割合(実質返戻率)も掛金を上回ることはありません。
注意点4 返戻金は払込保険料よりも少なくなる
保険本来の目的であるがんに対する保障を買うことはできるものの、返戻される金額は払い込んだ保険料より少なくなります。なかには返戻率が限りなく100%に近い保険商品もありますので、返戻率を重視される方はそちらを検討してみてはいかがでしょうか。
注意点5 税理士に相談する
2019年の保険通達の改正により、法人保険の税務処理は非常に複雑になっています。また、税制は頻繁に改正されるため、常に最新情報を収集し、税務処理に反映させなければなりません。税務調査に備えて福利厚生規程を作成し、適切に運用していても、保険料の全額損金が認められない場合があります。確実にがん保険料を全額損金算入するためには、法人保険の税務処理に精通している税理士に相談するのがおすすめです。税理士の助言に基づいて適切に運用することで、税務リスクを最小限に抑えられる可能性があります。
この節税術に
必要な心構えとは
法人でがん保険に入る節税メリットは薄くなっているものの、一定の節税効果は期待できます。保険料の一部は損金として計上できますし、所定の資産計上期間を経過すると損金として扱えます。また、例外や細かい条件が存在するものの、2019年の保険通達のルール改正より前に契約したがん保険は従来のルールで経費処理が可能です。短期的な視点ではなく、長期的な視点で考えると、節税効果は十分期待できるでしょう。
2019年の保険通達の改正以降、法人保険全般において、節税を主な目的とする利用には厳しい制限が設けられています。ただし、福利厚生やリスク管理といった正当な目的で適切に運用すれば、一定の税務上のメリットを享受できる場合があります。
法人保険を適切に運用するには、その分野に詳しい税理士を選ぶことが大切です。法人保険の知識が豊富な税理士であれば、税務リスクの回避や福利厚生の最適化、長期的な節税効果の最大化に貢献できるでしょう。
がん保険の本来の目的は、がんのリスクに備えるためのものです。がんは治療可能な病気になりましたが、高額な医薬品や治療方法に頼らざるを得ない状況になることもまたリスクとして存在します。がん保険を福利厚生の一環として提供することで、従業員は万が一のがんのリスクに備えられ、安心感を得られます。従業員の満足度向上や離職防止につながる可能性もあるでしょう。がん保険は企業と従業員の双方にメリットが得られるため、加入を検討されてはいかがでしょうか。