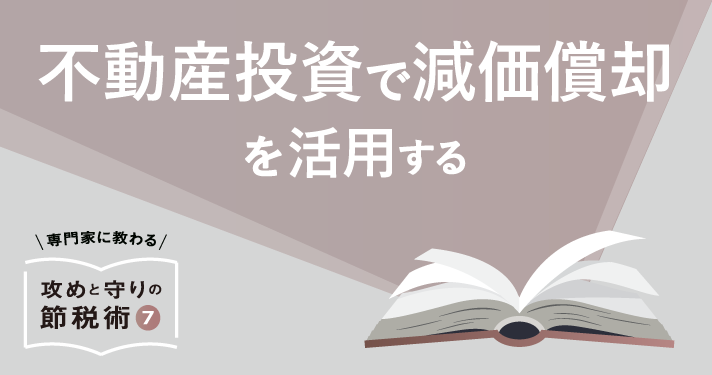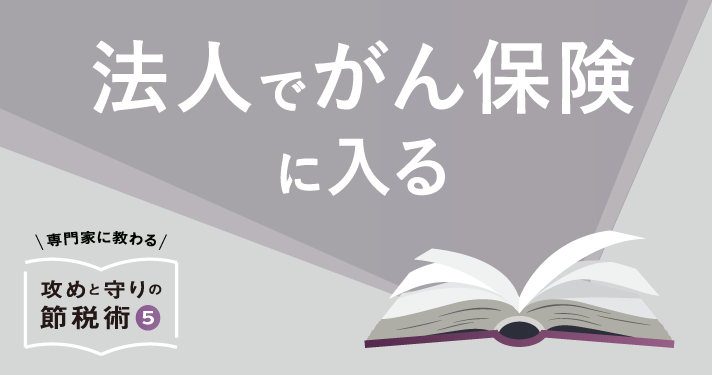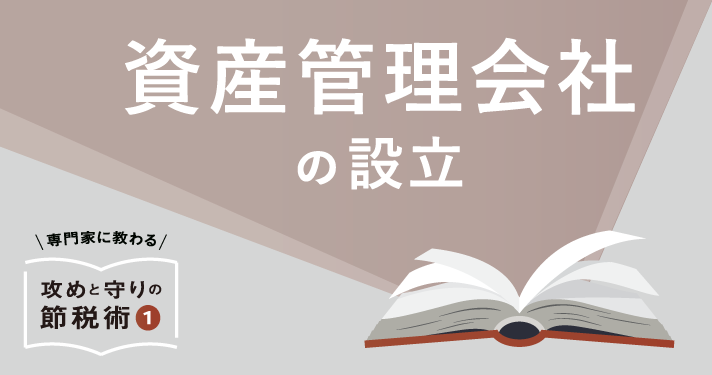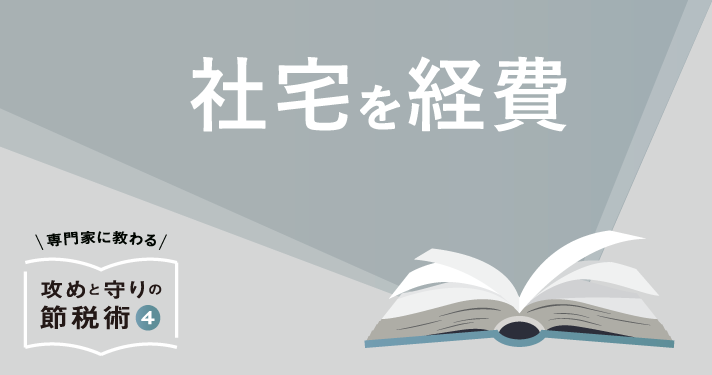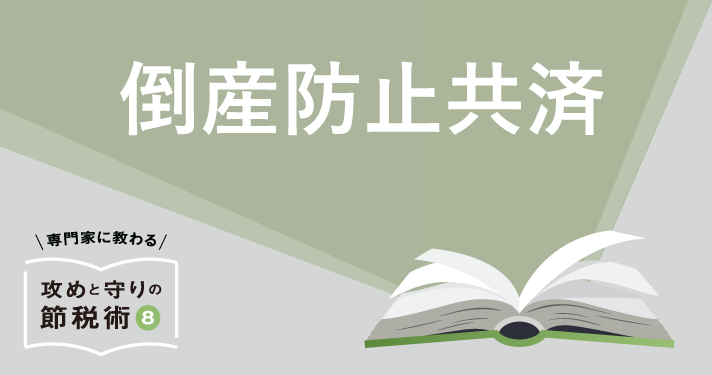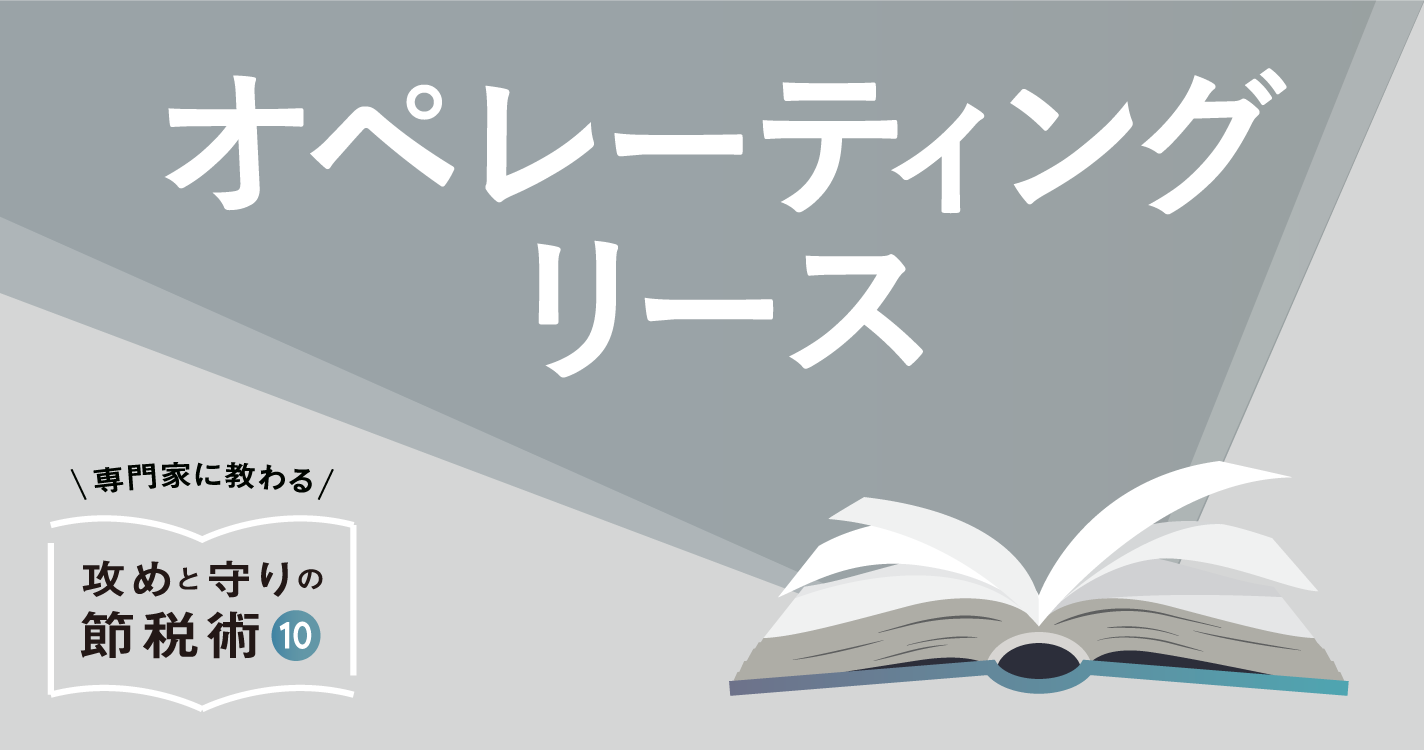
「オペレーティングリース」という節税術
オペレーティングリースは、航空機や船舶、建設機械、医療機器などの最新で高額な事業用設備を購入せずに使用でき、かつ節税にもつながる手法として活用されています。
本記事では、オペレーティングリースの仕組みや節税効果、注意点を解説し、企業経営にどう活かせるのかを考えていきます。
2027年4月1日から「新リース会計基準」が適用され、オペレーティングリースも原則としてリース資産およびリース負債としてオンバランス処理の対象となります(ただし、短期リースや少額資産のリースは例外としてオフバランス処理が可能)。これにより、企業の財務諸表への影響が大きく変わる可能性があります。
本記事では、2025年4月1日時点の現行のリース会計基準に基づいて解説していますが、「新リース会計基準」適用後の主な変更点についてもあわせて解説していますので、ぜひ参考にしてください。
オペレーティングリースとは?
オペレーティングリースとは、航空機や船舶、建設機械、医療機器などの高額な固定資産を、購入せずに一定期間レンタルするリース契約を指します。
オペレーティングリースはファイナンスリースとは異なり、「賃貸借に近い取引」であることが特徴です。例えば、企業が業務用コピー機をリース契約で導入する場合と同様に、契約期間中のみ設備を使用し、契約終了後は返却するのが基本となります。
また、リース料は基本的に全額費用として計上できるため、法人税の節税効果が期待できる点もメリットの一つです。
オペレーティングリースの対象となる固定資産
オペレーティングリースの対象となる固定資産には、次のようなものがあります。
・航空機・船舶
・土木建設機械(クレーン、ショベルなど)
・医療機器(MRI、CTスキャンなど)
・半導体製造装置
オペレーティングリースの対象となる設備は、中古市場で流通しやすく、耐用年数とリース期間のバランスが取れるものが多いという特徴があります。また、技術革新のスピードが速く、数年ごとに最新機種への更新が求められる設備もオペレーティングリースの対象になりやすい傾向があります。
オペレーティングリースとファイナンスリースの違い
オペレーティングリースは、リース期間が終了しても所有権は移転せず、リース物件の返却が必要です。一方、ファイナンスリースはリース期間が終了すると所有権が移転し、返却の必要がない(契約内容による)という特徴があります。
ファイナンスリースは実質的に資産の購入(ローン購入)に近い取引であるのに対し、オペレーティングリースは賃貸借契約に近い取引といえます。
契約内容によりますが、オペレーティングリースは中途解約が可能な場合もあるのに対し、ファイナンスリースは原則として中途解約はできません(ノンキャンセラブル)。
また、リース物件を使用中に故障した場合、オペレーティングリースではリース会社が修理費を負担するケースが多いのに対し、ファイナンスリースでは借り手が修理費を負担するのが一般的です。ただし、これも契約内容によって異なります。
オペレーティングリースの節税メリット
オペレーティングリースは高額な事業用設備を購入せずに使用できるだけでなく、以下のような節税メリットが得られます。
節税メリット1:リース料を全額経費計上できる
オペレーティングリースでは、毎月(または毎年)のリース料を支払い時に全額経費として計上できます。これにより、課税所得を減らし、法人税の負担を軽減する効果が得られます。設備投資の初期費用を抑えながら、税負担も軽減できることは大きなメリットといえるでしょう。
節税メリット2:減価償却の手続きが不要(※現行基準の場合)
オペレーティングリースでは、リース物件を企業の資産として計上しないため、現行の基準では減価償却の手続きが不要です。ファイナンスリースのように資産計上や耐用年数に応じた減価償却の計算をする必要がないため、会計処理がシンプルになるというメリットが得られます。
ただし、2027年4月1日からの新リース会計基準適用後は、オペレーティングリースも原則として「使用権資産」として計上しなければならず、減価償却が必要になります。リース料は「減価償却費」と「利息費用」に分けて費用計上されるため、現行基準とは会計処理が大きく異なる点に注意が必要です。
節税メリット3:キャッシュフローの改善
オペレーティングリースは、高額な設備を購入するための初期投資が不要で、手元資金を温存しつつ必要な設備を導入できる点が特徴です。
リース料は毎月均等に費用計上でき、法人税の負担を平準化しやすいため、キャッシュフローの安定化にもつながります。ファイナンスリースや購入では、一括で多額の支出が発生したり、減価償却費の変動が生じたりすることがありますが、オペレーティングリースだと、そのリスクの軽減が可能です。
このように、オペレーティングリースを活用することで、節税効果と資金繰りの安定化を両立できるでしょう。
なお、2027年4月1日からの新リース会計基準適用後は費用計上の方法が変わるものの、 初期投資が不要というキャッシュフロー改善のメリットは引き続き享受できます。
節税メリット4:固定資産税・保険料の負担がない
オペレーティングリースの場合、リース物件の所有権はリース会社にあるため、固定資産税はリース会社が負担します。そのため、借り手企業は固定資産税を支払う必要がありません。
また、リース物件にかかる保険料もリース会社が負担する場合が多く、借り手側で別途保険に加入する必要はありません(契約内容による)。これにより、間接的なコスト削減が可能となり、企業の利益向上に寄与します。
節税メリット5:柔軟な契約期間の設定による節税が可能
オペレーティングリースは、ファイナンスリースと比較すると、契約期間を柔軟に設定できるという特徴があります。企業の事業計画や設備の利用期間に合わせてリース期間を設定することで必要な期間だけ費用を計上でき、節税につながります。
例えば、急速に技術革新が進むIT機器や医療機器を短期間のリース契約で導入し、陳腐化する前に最新機種に乗り換えることで、常に効率的な設備を利用しながら、費用を適切にコントロールすることが可能です。
オペレーティングリースの注意点
一方、オペレーティングリースには、次のような注意点もあります。事前に理解したうえで、活用を検討するようにしてください。
注意点1 新リース会計基準ではオンバランス化が原則となる
これまでに触れてきましたが、2027年4月1日から「新リース会計基準」が適用されると、オペレーティングリースも原則としてリース資産およびリース負債としてオンバランス処理の対象となります。
したがって、減価償却の手続きが不要というメリットがなくなり、会計処理も複雑になります。節税目的でオペレーティングリースを検討する場合は、税理士などの専門家とも相談し、将来を見据えて節税効果を見極めましょう。
注意点2:長期的に見るとコストが高くなる可能性がある
リース期間が長期に及ぶ場合、トータルコストが購入するよりも高くなる可能性があることに注意が必要です。リース期間中に支払うリース料には、利息や手数料に相当する費用も含まれているため、購入するよりも割高になることがあります。
オペレーティングリースを検討する際は、リースの利便性とトータルコストのバランスを慎重に考慮することが大切です。
注意点3:中途解約が実質的には困難
オペレーティングリースは中途解約が可能な場合がありますが、解約不能期間があったり、高額な違約金が発生したりするケースが多く、実質的には中途解約は困難です。契約期間中に設備が不要になったり、事業計画が変更になったりした場合、大きなリスクが伴います。
オペレーティングリースを検討する際は、将来の不確実性も織り込んで適切な契約期間の設定が必要です。また、中途解約が可能な場合でも、違約金の額や発生条件などの条項をしっかりと確認しておきましょう。
注意点4:契約内容を細かく確認する
オペレーティングリースを契約する際はリース料だけでなく、禁止事項や中途解約の可否、リース期間満了後の扱い(返却、再リース、買い取りの条件や費用)など、その他の条件についても細かく確認する必要があります。
確認を疎かにすると、将来的に予期せぬ不利益を被ることもあるため注意が必要です。契約する際は、税理士などの専門家にも契約書の内容を確認してもらうと安心できます。
この節税術に必要な心構えとは
オペレーティングリースは、初期投資の費用の抑制や資金繰りの安定化、税負担の軽減に貢献する可能性がある有効な手法です。活用にあたっては、短期的なメリットだけでなく、長期的なコストや2027年4月1日からの新リース会計基準の影響を十分に理解しておく必要があります。契約内容をしっかりと確認し、潜在的なリスクを把握することも不可欠です。
節税効果はあくまで副次的なものと捉え、事業に必要な設備を効率的に利用するという本来の目的を見失わないことが大切です。専門家と密に連携し、自社の経営戦略に合致した賢明な判断を下すことが、オペレーティングリースを企業成長につなげるための心構えといえるでしょう。
オペレーティングリースは、企業の業種や事業規模、そして事業戦略によって適合性が異なります。特に技術革新の速い業界や、初期投資を抑えたい成長期の企業にとっては有効な選択肢となりえます。リース期間の設定は、コスト効率や陳腐化リスクに大きく影響するため、将来の事業計画を慎重に考慮することが必要です。
また、2027年4月1日からの新リース会計基準適用後は、財務諸表に与える影響も大きいため、専門家との連携が特に重要となります。税理士などの専門家とも相談し、長期的な視点で活用を検討してみてください。