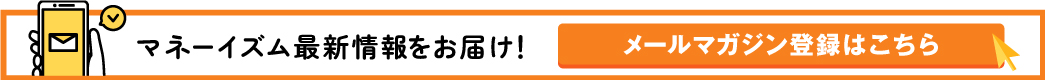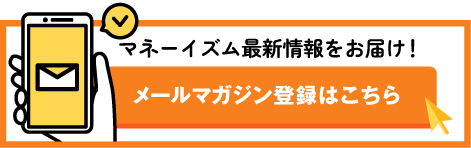親は「リア王」になってはいけない
“公平な相続”のために考えるべきこと【後編】
- 公開日:
- 2024/06/27
相続で子どもを「差別」するのはNG
――では、ここからは、先生のご経験を踏まえて、相続でトラブルを起こさないために注意すべきこと、具体的な対策についてうかがっていきたいと思います。
下川財産を渡す親の心構えとして、私がよく引き合いに出すのは、シェークスピアの『リア王』なんですよ。「リア王」のようになってはいけない、と。
――そのココロは?
下川ブリテンを治めるリア王は、高齢になったために3人の娘に領土を分け与えることを考えて、それぞれに意見を聞きます。財産目当てに父親に対して美辞麗句を並べた長女と次女に対し、末娘はそれをしなかった。腹を立てたリア王は、末娘を勘当し、上の2人に領土を与えます。
ところが、割譲が終わると、2人の娘は父親に反旗を翻しました。騙されてすべてを失ったリア王は、フランス王妃となっていた末娘を頼り、彼女たちに戦いを挑みます。しかし、あえなく敗北。その結果、末娘は処刑され、リア王も悲嘆に暮れながら亡くなった――。これが物語のあらすじです。ちなみに、実在した古代ブリトン人の伝説の王レイアがモデルだとされています。
――文字通り相続が生んだ悲劇です。
下川リア王の失敗は、2つあると思うのです。1つは、相続の間際になって、子どもたちの気持ちを試すようなことをしました。しかも、それだけで遺産分割のすべてを決めてしまった。いかにも性急に過ぎます。
もう1つは、子どもたちを「差別」したことです。リア王の場合は、騙されたわけですが、そうでなくても、あからさまに分け隔てするようなことをしたら、前編の遺言書の事例のように、後で問題を生むのが目に見えています。
本人たちが納得できる理由があれば話は別ですが、「好き・嫌い」とかの親の感情で、誰が見ても理屈の通らない相続を行った結果、争いになったりして困るのは、子どもたち。遺産分割に際しては、何よりも冷静になることが大事なのです。
法定相続分による分割=公平ではない

――財産を渡す方は、公平な分割を念頭に置く必要があるということですね。
下川そうです。ただし、「何が公平なのか」についても、よく考えなくてはなりません。単純に相続人が3人いたら、財産を1/3ずつ分けるのが公平かというと、そうはいえないこともあるのが、相続の難しさです。
例えば、私は法人のお客さまから事業承継が絡む相続の相談を受けることが、けっこうあります。そういうケースでは、基本的に自社株はもちろん、現金などの財産も含めて最大限、事業を継ぐ子どもに相続させ、他の子どもには遺留分を考慮した財産を渡すのが公平。乱暴に聞こえるかもしれませんが、それが私の考えです。それくらい、親の事業を継ぐというのは大変なことなんですよ。
――高い自社株を相続すれば、納税額も高額になります。
下川そういうことも含めて、後継者にしっかり財産を渡しておかないと、会社の存続が難しくなるようなことも考えられます。一方、後継者以外の相続人は、相続する遺産額は少なくなるかもしれませんけど、ある意味、外で自由に稼ぐことができる立場にいるわけですから。
事業承継以外にも、特定の相続人が親の介護を一手に引き受けていた、というような場合に、その「寄与分」が相続に反映されないと、トラブルの元になる可能性が高まります。
――そうしたことまで加味したのが、本当の意味での公平だというわけですね。
下川遺産分割というと、どうしても法定相続分が頭に浮かびがちなのですが、それは揉めたときの最後の裁判所の判断基準だと理解してほしいのです。いい方を変えると、親が「法定相続分による分割が公平だ」と思い込んでいたり、子どもが「その金額は絶対にもらう」という姿勢で相続に臨んだりすると、争いを生みやすい。その点には、注意が必要だと思います。
メリットの多い「自筆証書遺言書保管制度」
――おっしゃるような「公平な遺産分割」を実現するためには、具体的にはどうしたらいいのでしょうか?
下川やはり、親の意思を明示した遺言書を作るのが、ベストの手立てでしょう。遺産分割に対する親の考えを示されれば、多くの場合、子どもは納得して受け入れるものです。
――それがないから、法定相続分ウンヌンの話になって、揉めてしまう。
下川そうです。仮に受け入れ難い気持ちがあったとしても、遺留分さえ侵害していなければ、たとえ裁判で争っても勝ち目はありません。しっかりした遺言書を作っておけば、揉めようがなくなるのです。
――ただ、現実には「手間がかかる」「まだ早い」といった理由で先送りされ、さきほどの事例にもあったように、相続が差し迫ってから病床で作成せざるをえない、といった状況になることが、少なくないようです。
下川その点、私が非常にいいと思うのが、2020年に始まった「自筆証書遺言書保管制度」なんですよ。手書きした遺言書を自分で法務局に持っていけば、そこで保管・管理してくれる、という制度です。
それまで、自筆証書遺言書には、手軽でコストがかからないというメリットの半面、偽造されたり紛失したりするリスクが指摘されていました。新しい制度を利用すれば、「自筆」のメリットはそのままに、安全性が保障されます。また、従来は手軽といいながら、相続発生時に誰かが勝手に開封することはできず、家庭裁判所の「検認」という手続きが必要だったのですが、この制度では不要になりました。
自分1人で法務局に持参するので、中身を秘密にしたいときには、最後までそれが守られる、というのもいいところです。長男だけが遺言書を保管した金庫を知っていた、というような状態だと、「お父さんが、兄に有利な内容を書かされたのではないか」と疑われるかもしれませんが、そうした心配もありません。
公正証書遺言書の効力は「絶対」ではない
――一般的には、自分の考える通りの遺産分割を行うためには、公証役場で公証人に作成を依頼する公正証書遺言書にしておくのが確実だ、といわれることが多いように思います。
下川確かに公正証書にすれば、公のお墨付きを得たことにはなりますから、そういう意味での安全性は高まるでしょう。ただ、公正証書遺言書の作成には費用がかかるうえに、2人以上の証人の立会いが必要です。しかも、この証人は、あくまで遺言書が正しく作成されたことなどを証明する役回りなので、相続そのものには関与しません。被相続人の意を酌んで、相続人に話をしてくれたりはしないのです。
加えて、そうやってコストや労力を費やして作った公正証書遺言書だからといって、その効力は「絶対」ではないんですね。例えば、これも前に触れたように、相続人全員の同意があれば、遺言書に書かれているのとは異なる分割をすることが可能です。
――「自筆」か「公正証書」か、という形式は関係なく。
下川そうです。せっかく作成した公正証書遺言書が意味をなさなかったばかりか、相続人の負担になってしまった、こんな事例がありました。
事業を営んでいたお父さんが亡くなり、相続になりました。相続人は、事業を継ぐ息子と娘の2人。お父さんは、信託銀行の「遺言信託」を利用していました。
――銀行に遺言書の作成のサポートや、その執行を依頼したわけですね。遺言書は、当然「公正証書」になります。
下川本人は相続が円満にいくようにと、念には念を入れたつもりだったのかもしれませんが、肝心の遺言書の内容に問題がありました。財産分与が、息子と娘ほぼ半々だったのです。
――事業を受け継いだ人が行き詰ってしまう、というパターンですか。
下川困惑した息子さんから「公正証書遺言書の内容には、従わなくてはならないのでしょうか?」という電話がありました。私は、「そんなことはありません。相続人が合意すれば、変えることはできますよ」と答え、妹さんとの話し合いを勧めたんですよ。
このケースでも、娘さんに理解のあったことが幸いしました。最終的には、遺言書を反古にしたうえで、事業を承継する息子さんが必要な遺産を受け取る、という内容の遺産分割協議書を新たに作成し、無事相続を終えることができました。
付け加えておくと、遺言書の作成に関わった信託銀行は、結局相続には何の役にも立ちませんでした。お父さんは高い手数料を払っただけだった、というわけです。

――遺言書は形式よりも中身が大事なのだということが理解できる、典型的な事例だと思います。
下川揉めない相続のために、遺言書は間違いなく大きな効果があります。自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、煩わしい思いをすることなく、安全に遺言を残すことができるはずです。
ただし、みんなの幸せを考えて、遺産分割は可能な限り誰からも文句が出ないものになるよう、心がけましょう。くどいようですが、最低限、遺留分の問題はクリアすべき。それが大きなポイントです。
――わかりました。最後に貴社の今後の展望をお聞かせください。
下川これからも発展が期待される東京・中央区を基盤に、一般の法人や医業、社会福祉法人などの経営サポートに注力したいと考えています。相続に関しては、悩みの多い富裕層の方を中心に、生前の対策から申告、不動産売却などのワンストップサービスが可能な事務所として、引き続きお役に立ちたいですね。
――本日は、貴重なお話をありがとうございました。
注:記載の「事例」に関しては、情報保護の観点により、お話の内容を一般化したり、シチュエーションなどを一部改変したりしている場合があります。
URL:https://shimokawa-kiji-and-co.jp/