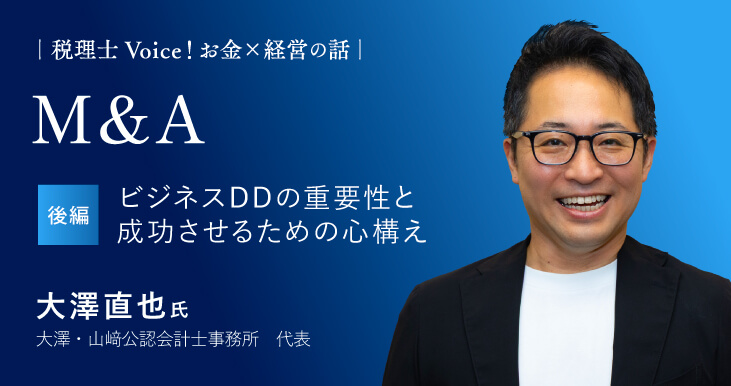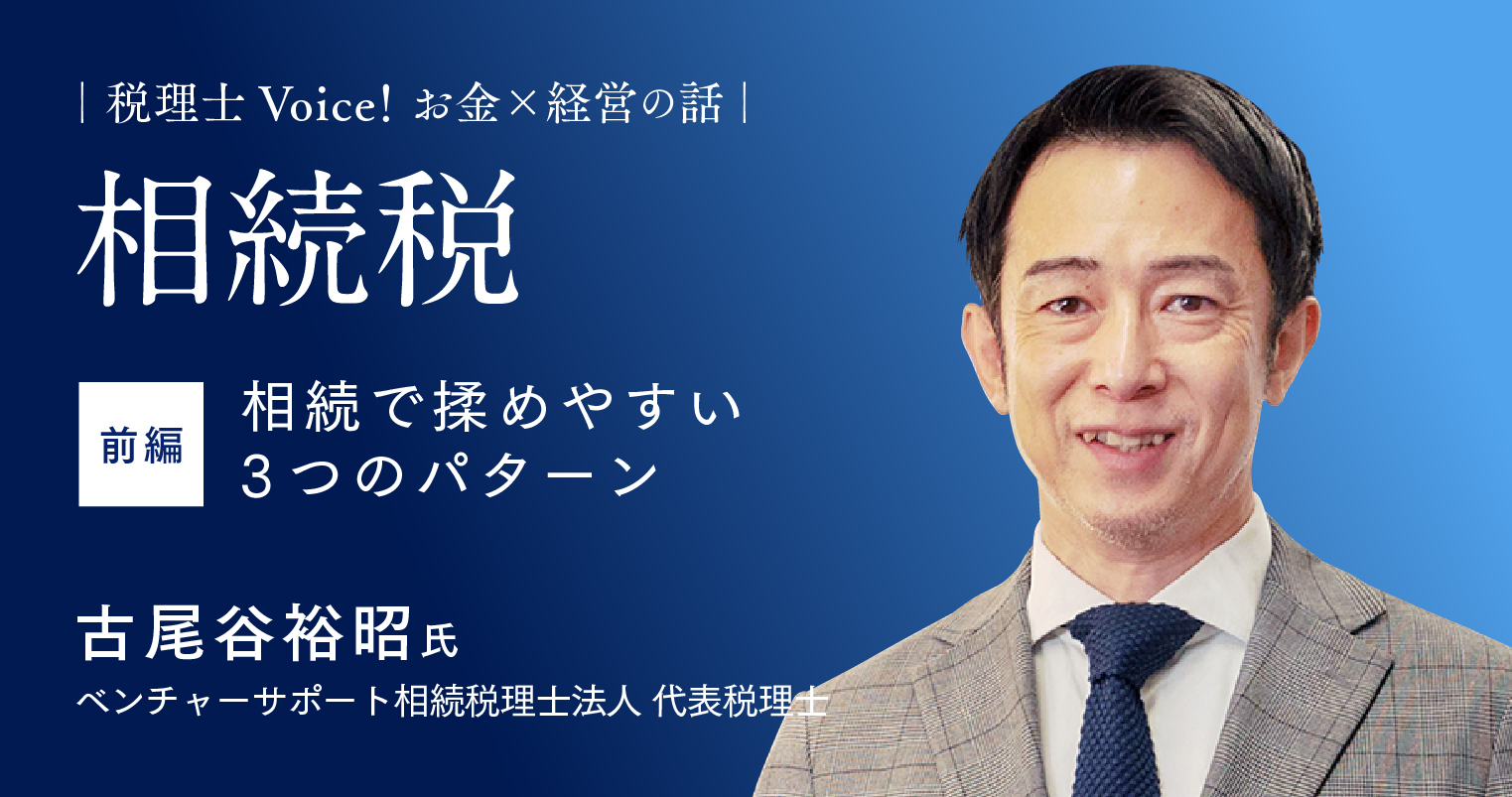【相続税対策 後編】元国税専門官が語る相続税対策のポイントと注意点 早く準備を始めるべき理由とは
中林善明税理士事務所 所長 中林善明氏親が勝手に贈与することはできない
――不動産投資の注意点についてお話がありましたが、相続対策で起こりやすいトラブルには、他にどんなことがありますか?
中林 私は国税局と税務署に勤めていたうちの15年ほどは、相続税の調査に携わっていました。その間に、被相続人が生前に行っていた贈与を否認したことが、けっこうあったんですよ。
――「これは贈与とは認められないから、全額を相続財産に加えて、相続税を納めてください」ということですね。否認の理由は何ですか?
中林 誤解されている方も多いのですが、贈与というのは、財産を「あげる人」と「もらう人」が合意して成立する諾成契約です。ところが、親が勝手に子どもに「贈与」していることが少なくないのです。子どもになり代わって、非課税分を除いた贈与税の申告をしているケースもありました。
相続になって、相続人に「お父さんから贈与を受けていましたか?」と聞くと、「もらってない」と。そんなお金がどこにあるのかも知らず、困惑されることもしばしば。これでは、諾成契約が成立していたことになりませんから、税務署としては贈与と認めるわけにはいかないわけです。
――せっかく対策したつもりだったのに、水の泡ですね。
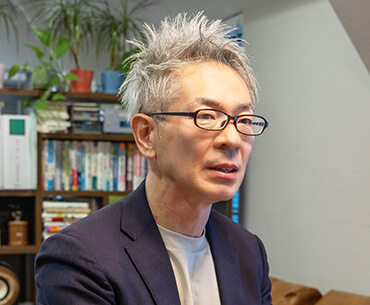
中林 そうならないためには、あげる相手にきちんと話をして、同意を得る。さらには、その証拠を残すことが重要です。毎年、契約書を作成して、自筆で署名させておくといいでしょう。
私事で恐縮ですが、私は子どもが生まれてから、ずっと贈与を続けています。未成年のうちは親権者である母親が署名、捺印し、小学生になって字が書けるようになってからは、自分の名前も書かせたんですよ。併せて、贈与とはどういうものかについての話もしてきました。
――それは、生きた「マネー教育」だと感じます。ただ、生前贈与に関しては、一方で子どもにお金を渡すと使ってしまうとか、親を頼るようになるとかを心配する方も多いのではないでしょうか。
中林 前編で、不動産保有会社を活用した節税の話をしました。実は私もその方法を実践していて、子どもに渡しているのは、会社に対する貸付債権なんですよ。これならば、譲ったお金を右から左へ使ってしまう、といった問題は起きません。相続までには、おそらく私の債権は消え、それに対する相続税の心配もなくなるでしょう。
贈与に関しては、家庭によって適したやり方があると思います。ただし、説明したような諾成契約であることを忘れずに。そこに問題があると、子どもに高い相続税を課せられる可能性があります。
事業承継のポイントは「よく話し合う」こと
―― 一般家庭の相続対策をうかがってきましたが、企業経営者の場合は、事業承継というさらに高いハードルをクリアしなくてはなりません。この分野でも多くの案件に関わってこられた先生からみて、スムーズに進めるために必要なのは、どんなことでしょう?
中林 金銭面では、場合によっては高額の税金が発生する自社株を贈与や相続でどのように譲るのか、ということが課題になります。ただ、それ以前の問題として、バトンタッチの時期や方法などをなかなか決められないケースが多いんですよ。
後継者が見つからないこともあるのですが、子どもに譲ることが決まっているのに準備が具体的に進まないようなことも珍しくないのです。せっかく息子さんを代表取締役にして、自社株についても徐々に贈与していくというお話をされていたのに、結局1株も譲らないまま亡くなった、という相続も経験しました。
――なぜそうなってしまうとお考えですか?
中林 よくあるのは、経営者の方の「思い」がネックになるパターンです。心血を注いで築き上げてきた大切な会社の実権を、ある日を境に手放すことに、どうしても踏ん切りがつかない。気持ちはわかるのですが、それで困るのは後継者の方なのです。
経験上、事業承継で大事なのは、まず現経営者と後継者でよく話し合うこと。どちらか1人で考えていても、話は一歩も進みません。ただし、これがけっこう難しい(笑)。親子だったら大丈夫かというと、逆に大変だったりするわけです。
――遠慮がないぶん、感情的にもなりやすいですから。
中林 事業承継のアドバイスの肝で、なおかつ最も骨の折れるのは、そういう話し合いの環境をつくることだと言ってもいいでしょう。親子だけではうまくいかないところに、専門知識を持った第三者が介入することで、「いつ引退しますか?」「自社株対策はどうしますか?」といった話に答えを出していくわけです。
そういう落としどころをはっきりさせられれば、自社株の節税対策などについては、ある意味やるべきことをやるだけです。
事業承継税制を使うべきケースとは
――その自社株対策の1つに、事業承継税制の活用があります。制度を使うべきかどうか、専門家の中にもいろいろ意見があるようですが、先生はどんなお考えですか?
中林 事業承継税制は、一定の要件を満たせば、非上場株の相続税・贈与税の納税が猶予される、という制度です(※)。後継者に安定的な経営を引き継がせるためには、議決権株式を分散させずに渡さなくてはなりません。多額の税負担を避けてそれができるのは、大きなメリットです。

※2026年3月末までは、納税額の全額が猶予され、要件も緩和された「特例措置」を利用できる。
ただし、この制度には、事業承継後にも守るべき要件があるんですね。例えば、後継社長は原則として5年間は退任できません。自社株の譲渡は禁止です。こうした要件を1つでも欠くと、猶予されていた税金の全部または一部を、利子税とともに一括で納めなくてはならないのです。
――納税はあくまでも猶予であって、免除ではないわけですね。
中林 免除されるのは、後継者が亡くなって相続になった場合や、後継者が次の3代目に事業を譲り、やはりこの税制の適用を受けた場合などに限られます。
このように、制度のメリットを享受するためには、ある程度しっかりした将来の見通しが必要で、要件を欠いてしまっときのペナルティがけっこう重いのです。そのため、おっしゃるように、使い勝手が悪いと考える税理士が多いのもうなずけます。実際、いろいろ説明した結果、利用を諦める方も少なくないんですよ。
私は、事業承継に当たってこの制度を利用するかしないかは、お客さんによると考えています。例えば、本来ならば上場してもおかしくないような規模のオーナー会社が、あえて非上場にとどまってこれを使えば、莫大な相続税・贈与税を回避して、一族間で経営者と資本家の地位を受け渡すことが可能です。そういうことを望まれる方にとっては、非常に魅力的な制度だといえるでしょう。
他方、規模がそれほど大きくない会社は、やはり地道に株を贈与していくような方策を基本に置くべきだと思います。「未来予想図」が完璧にできているような場合は別ですが。
――今の制度の利用も含め、事業承継の準備は、いつごろ始めるべきなのでしょう?
中林 それはもう、早ければ早いほどいい(笑)。さきほどもお話ししたように、対策以前の基本線の話をまとめる段階で、思わぬ時間がかかったりもしますから。一般の相続同様、早く始めて長く贈与などの対策を実行するほうが、税負担は間違いなく軽減されます。
例えば65歳で後継に譲りたいと思うのだったら、50歳くらいからその意識を持って動いてほしいですね。どんなに遅くとも、承継の3年前には具体的な計画を練り、実行に移す必要があると思ってください。
相続に詳しい専門家に相談を
――お話をうかがってきて、相続や贈与に関しては、まだまだ知っておくべきことが多いと感じました。疑問や不安がある場合には、誰に相談したらいいのでしょうか?
中林 同じ国税でも、相続税・贈与税は、法人税や個人の所得税とは違う世界観のようなものがあって、経験もものをいいます。みんなが得意というわけではないので、そうした資産税に詳しい税理士がいいと思います。
選ぶ際には、事務所のホームページは、1つの参考になるでしょう。ただ、お金の相談をする相手ですから、信頼できそうか、相性は合うのか、といったことも大事になります。実際に会って話してみて、そのへんのことを確かめるのも大事です。
――参考になるお話をありがとうございました。最後に、事務所の今後の展望をお聞かせください。
中林 私自身、人との出会いは縁だと思っています。なにか敷居の高いところではなく、困りごとがあれば気軽に立ち寄れるような、町医者的な税理士事務所を目指したいですね。そうやって出会った方のためには、ベストを尽くす存在でいたいと考えています。
――これからもキャリア、経験を生かしたご活躍を期待しています。
千葉県、東京都、福岡県を中心に、相続に悩む経営者を支える税理士事務所。税務署歴25年・不動産売買10年以上のキャリアを活かした相続税対策・不動産コンサルティングを得意としており、難しい相続を分かりやすく説明する。
URL:https://nakabayashi-tax-office.com/