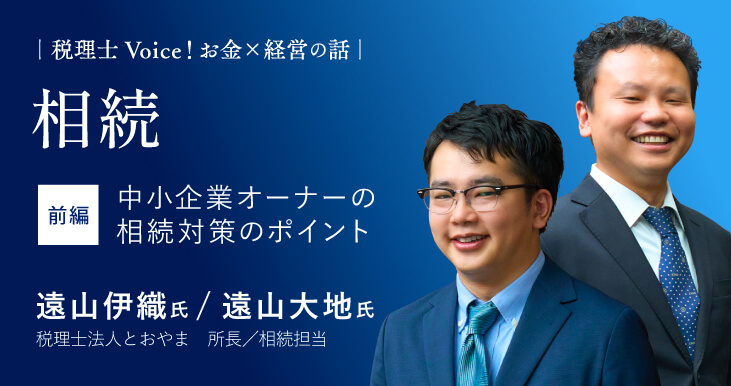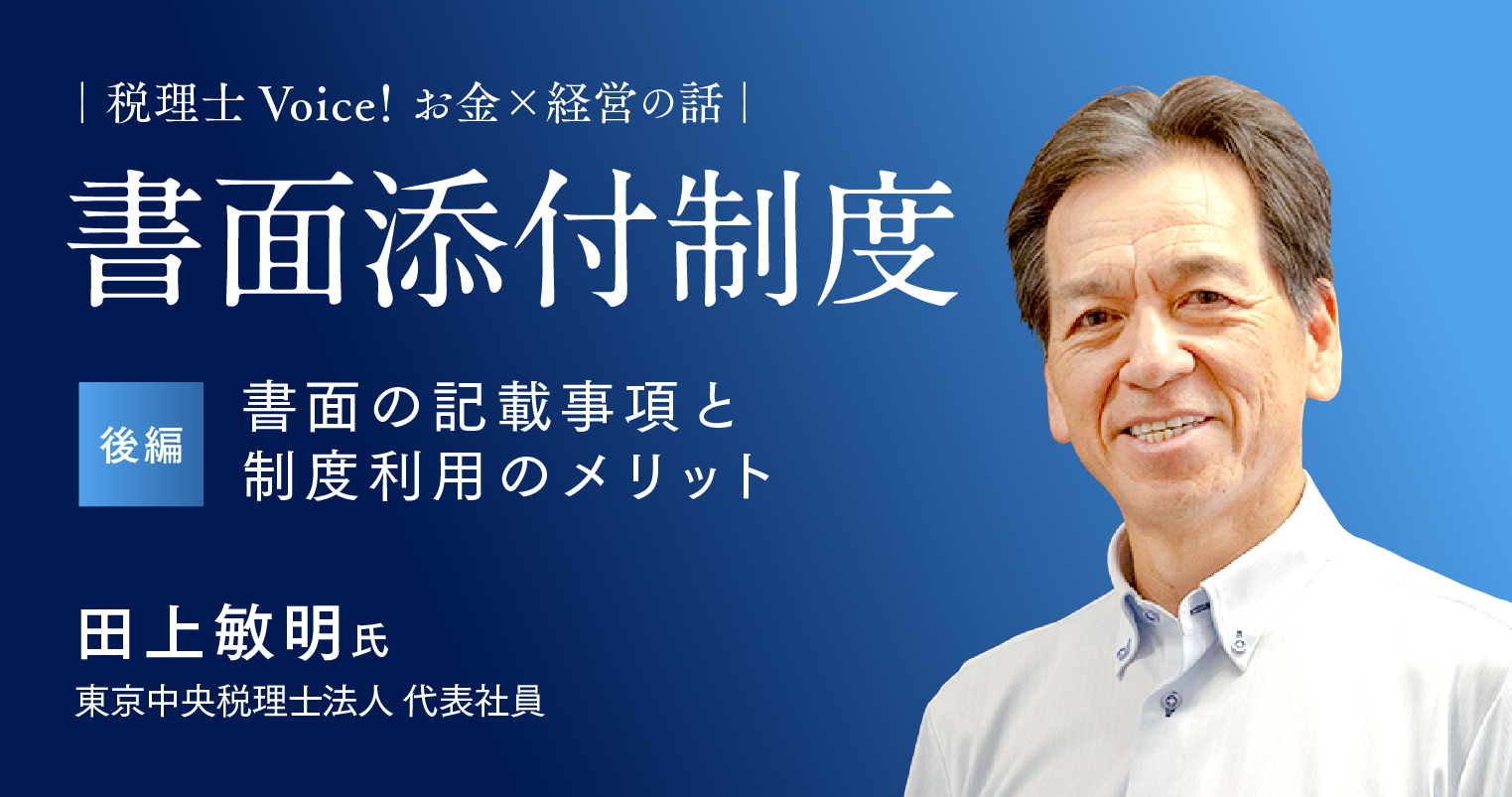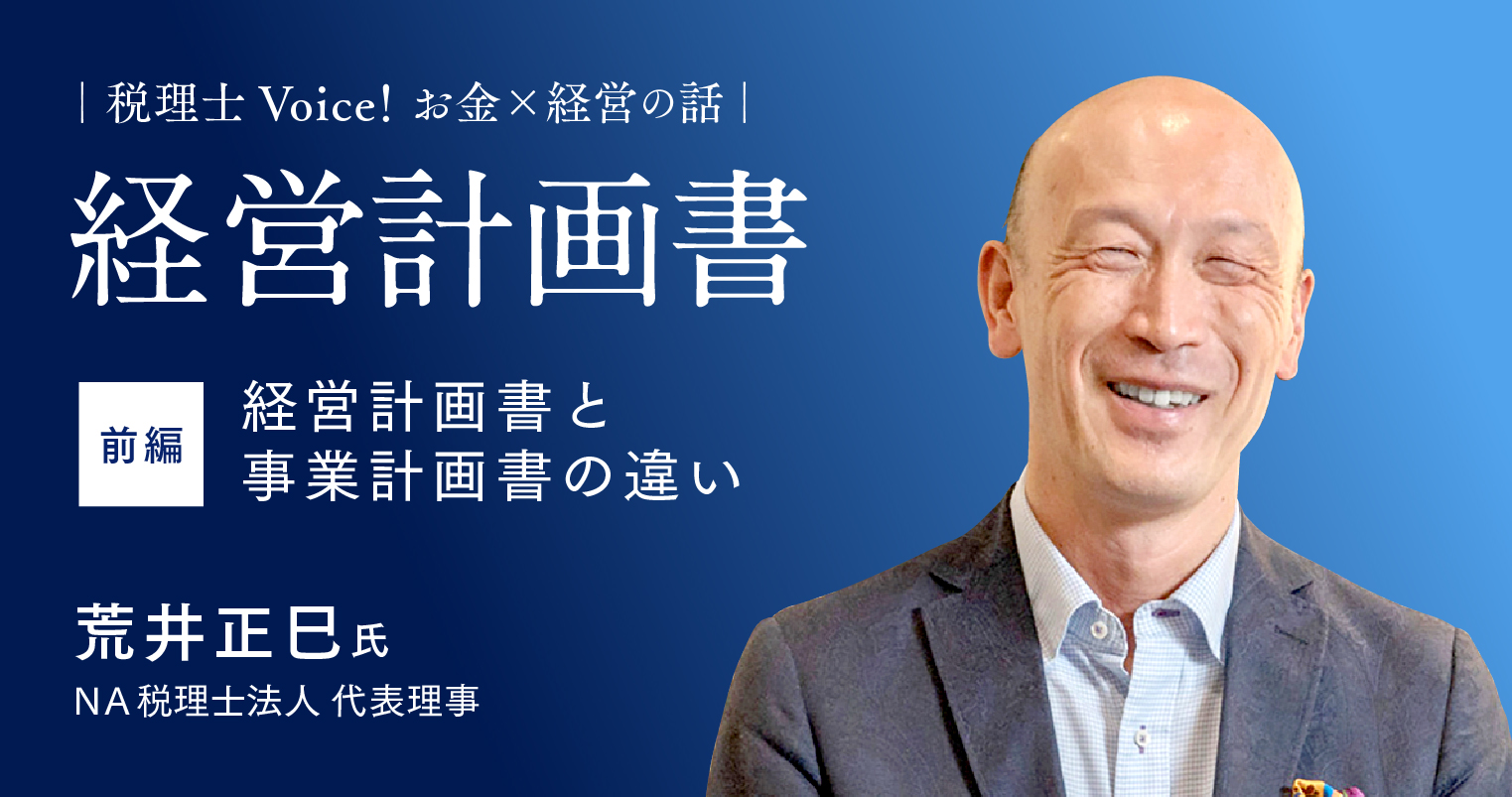【相続 後編】中小企業オーナーの相続対策は 「体重計」に乗って自らの現状を知るところから
税理士法人とおやま 所長 遠山伊織氏(左)、相続担当 遠山大地氏(右)自社株の生前贈与で納税額を圧縮
――中小企業オーナーの相続に多く関わる中で、成功した事例を紹介してください。
伊織 生前贈与の話が続くのですが、私の顧問先で、弟にも相談しながら対策を進めた結果、前編で説明したメリットがうまくハマった最近の事例があります。
この会社は、相続対策を始めた時点で、すでに先代の子どもが代表者を継いでいて、さらにその次を担う予定の孫も入社していました。ただし、自社株はすべて先代の手元にあり、高齢で健康面に不安を抱えるようになったため、早めに子どもと孫に渡しておきたい、というご相談だったんですよ。
売上規模は10億円ぐらいで、新社長がかなりのやり手だったこともあって、業績は右肩上がり。それはいいのですが、業績が良ければ、それにリンクして自社株の評価額も上がっていきます。税金の側面からは、喜んでばかりもいられない、という状況でした。
そこで、さっそく自社株の贈与を行うことになり、現社長である子どもには、さきほどの相続時精算課税制度を活用して株を渡すことにしました。
――今後株価が上がっていくのなら、そのやり方は有効ですね。
伊織 2,500万円の非課税枠をフルに使って贈与すると同時に、新設された110万円の基礎控除も活用しました。
一方、孫には基礎控除を使った暦年課税による贈与を行いました。さきほど、「生前加算贈与が3年から7年に延長されている」という話をしました。しかし、先代の法定相続人ではない孫には、そもそもこの生前贈与加算は適用されず、相続発生まで基礎控除を使った贈与が可能なんですよ。
さらに、2人への贈与を一度に行うのではなく、2年に分けて実行しました。
――それには、どんな意味があるのでしょう?
大地 贈与税の基礎控除は、1人につき年間110万円です。2人に贈与することで年220万円、さらに2年になると、非課税枠は440万円まで「増額」されるのです。
加えて、贈与税は渡す金額が大きいほど税率が上がっていく累進税率になっているので、歴年課税の場合、1年間の贈与額を抑えたほうがより低い税率で渡していける、というメリットもあるんですね。

伊織 ですから、2年といわずさらに分割して贈与できれば、節税効果はより大きくなります。ただし、このケースでは、一方で「なるべく早く株を渡したい」というオーナーの意向がありました。「健康に自信が持てないから」とおっしゃって。万が一、贈与している途中で亡くなれば、思ったような財産の分割や節税ができない可能性もあります。
――なるほど。そうしたいろんなファクターを考慮した「連立方程式」を解いた結果が、今お話しのやり方なんですね。
伊織 会社の現状や様々な前提条件を知る法人担当と、経験のある相続担当が協力したからこそ、こうした強力なスキームが使えました。その点は自負しています。
あえて付け加えておけば、長期的な相続対策は、大きな節税効果などが期待できる半面、リスクもあります。相続時精算課税でも、今は将来的な株価の上昇が間違いないと見えていても、実はその保証はないんですね。実際数年前には、想定外のコロナ禍により、絶好調だったはずの業績が急降下した会社がたくさんあったわけです。
円満に終われば相続は「成功」
――今のは成功例ですが、そうした対策を考える前に揉めてしまうようなこともあるのでしょうか?
大地 それもありますね。けっこう多いのは、親の相続で子どもたちの仲が悪くなる、というパターン。私が経験した例では、お兄さんはわりと楽天的な方で、「兄弟で喧嘩したことはないから、大丈夫」とおっしゃっていたのに、親が亡くなって相続になったら、いきなり弟さんに弁護士を立てられて争いになってしまった、ということがありました。
――何が問題になったのでしょう?
大地 これは事業承継が関係する事例ではなかったのですが、弟さんが亡くなった親の介護を積極的にやっていたのに対して、お兄さんのほうは、親が体調を崩しても1年に1回、顔を見せるぐらい。それなのに財産を半分に分けるのはおかしいだろう、と弟の怒りが爆発したのです。
伊織 今の「親の介護」が「会社経営」に置き換わるようなかたちで、同様の争いの起こることも珍しくありません。例えば、兄は早くから会社に入って、事業の立て直しとか従業員との関係性の構築とか、見えない貢献をしてきた。他方、弟は好きに自分のやりたいことをしてきたにもかかわらず、いざ相続になったときに、どちらがどれだけ株を持つだとか、後継者争いのようなことになってしまう。
――事業承継絡みの相続では、自社株を相続する後継者と他の相続人の遺産額の不均衡が、争いの種になりやすいですね。
伊織 会社の経営を考えれば、後継社長にできるだけ多く、できれば100%の自社株を譲るのが理想です。株が分散してしまうと、重要な議決ができなくなったり、入手した人から高額の株の買い取りを迫られたり、といった事態になる危険性もありますから。
ところが、そうすると、やはり遺産額の受け取り分が少なくなる後継者以外の相続人からは、不満が出やすくなります。
――そうした場合、他の相続人の遺留分(民法に定められた最低限受け取れる遺産の割合)を考慮しつつ、生前贈与や相続で対策を講じる必要がある、といわれますよね。
伊織 現実には、自社株が相続財産の大半を占めていたりして、そう教科書通りにいかないケースも多いように感じます。
大地 自社株に限らないのですけど、完全に平等な遺産の分割は、不可能に近い。ですから、そうした場合には、しっかり話し合って着地点を見つけるというのが、現実的な解決策になると思うのです。
確かに民法には、相続人の法定相続分や遺留分などについての定めがありますが、その通りにしなければならない、という性格のものではありません。相続人で合意すれば、遺産はどのように分けても問題ないのです。
――遺留分もあくまでも権利だから、主張しないこともできる。
大地 そうです。それに、非上場企業の株は、市場で売って現金化したりすることができません。その点が上場企業の株や不動産などとの違いで、会社経営に関わらない人にとっては、本来「持っていても仕方のない財産」なんですよ。相続税法上の評価額を考えると不平等に感じるかもしれませんが、実際のところは、少額でも現金を相続できればそれでいい、という考え方もできるはずです。
――そうしたことも説明しながら、落としどころを探っていくわけですね。
大地 もちろん、遺産の分け方や節税は大事ですけど、最優先すべきは相続人の争いを生まないこと。円満に相続を終えることができれば、それだけで十分成功だったといえるのではないか、と私は思っています。
コミュニケーションの重要性
――経験を積んだ専門家がそう指摘するくらい、円満な相続というのは簡単なものではない、ということですね。「争続」にならないために、必要なことは何でしょう?
大地 ひとことでいうのは難しいですが、常日頃から家族でコミュニケーションを取り、風通しを良くしておくというのは大事だと思いますね。いざ相続になって、それぞれ考えていたことが違ったりすると、衝突が始まってしまいますから。
理想をいえば、やはり財産を渡す親の側が遺産分割の方針を決めて、生前贈与するなり、遺言書を残すなり、しっかり相続のイニシアチブを取って進めるのがベストです。親の意向がはっきり伝われば、子ども同士は揉めにくいものですから。
伊織 今の話にも通じるのですが、事業承継になるケースでは、なおさら先代経営者と後継者のコミュニケーションが重要になります。社長の息子が後を継ぐというのは、外から見ると当たり前のように思えても、継ぐ本人にとっては人生の一大事なんですね。実際、会社を経営していくというのは、容易なことではありません。「商才」だけではなくて、従業員をまとめ、取引先との関係を良好に保つような力も求められるわけです。
――確かにそうですね。
伊織 私の知る例でも、父の会社を継いで張り切ってやっていたものの、周囲をうまく動かすことができずに、5年ほどで、相続した会社の株をすべてM&Aで手放した方がいました。
――事業承継は、単に「相続税対策」では終わらない、というのがよくわかる事例だと思います。
中小企業オーナーの相続は、誰に相談すべきか
――そうしたことも踏まえて、中小企業オーナーは、いつごろ相続対策を始めるべきなのでしょう?
伊織 節税対策については、基本的に早ければ早い方が、大きな効果が期待できます。対策の「王道」である生前贈与は、さきほどの事例でご説明した通り、長い期間に渡って少額ずつ行う方が、納税額は少なくて済みます。活用できる節税スキームの選択肢も増えるでしょう。
一方、事業承継に関しては、早ければいいというものでもありません。経営者として未熟なうちにバトンを渡せば、社内が混乱するかもしれません。反対に遅すぎると、先代とともに事業に携わる、という後継者の成長の機会が奪われる可能性があるでしょう。

この両者のタイミングが合えばベストなのですが、現実にはなかなかそうはいきません。「いつから対策を始めるべきか」は、ケースバイケースというしかないですね。
――相続について相談するのは、やはり顧問税理士がいいのでしょうか?
伊織 必ずしも中小企業オーナーに限りませんが、相続が発生してから、例えば相続専門の事務所に依頼しても、申告以外にできることはほとんどないわけです。顧問税理士は、会社のことに精通しているだけでなく、経営者個人の申告もやりますから、その「財布の中身」もある程度わかっています。相続についても、より経営者の方に寄り添ったかたちでの対応が可能になると思います。
ただし、相続税は法人税などと税体系が異なるため、顧問税理士自身は専門外なのが普通です。ですから、相続税に詳しい専門家としっかり連携のとれていることが大事なポイントになりますね。
――わかりました。本日は中小企業オーナーの相続についてのためになるお話をありがとうございました。最後に、今後の目標についてお聞かせください。
伊織 我々も昨年経営を引き継いでみて、税理士の仕事と経営というのは別物であることが、あらためてわかりました。自分自身、今まで以上に事業承継を応援したいという思いを強くしています。同じように世代交代を迎えているお客さまも多く、覚悟を持って頑張っていかれる経営者を、全力でサポートしていきたいと思います。
大地 最初にご説明した通り、当社はお客さまに対するワンストップサービスの提供を目指しています。その中で、私の守備範囲である相続についてさらに実績を重ね、伊織や社内のベテランのスタッフなどとも連携しながら、貢献していきたいですね。
――ますますのご活躍を期待しています。
「お客様の成功へのお手伝い」をモットーに、税務・労務・会計のワンストップサービスを通じて、経営者のあらゆる相談に真摯に向き合うプロフェッショナル集団。幅広い業種で培われたベテランの経験と、最新のITツールを駆使し、上場企業から中小企業までサポートする。
URL:https://www.to-yama.com/