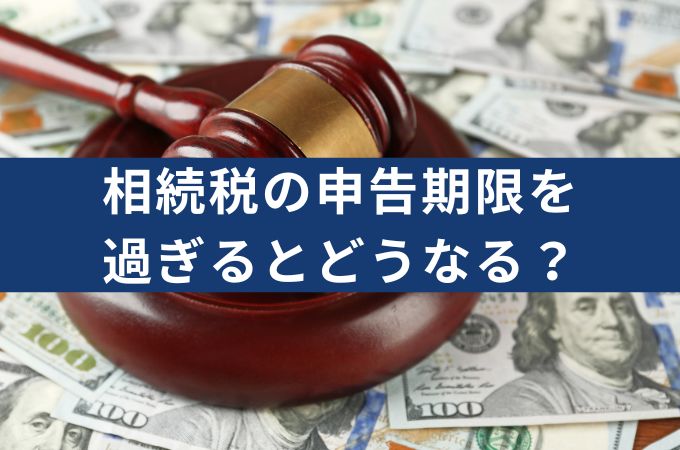相続税の申告期限とは?基本ルールをおさらい
「亡くなった日を知った日の翌日から10ヶ月以内」が原則
相続税の申告期限について、多くの方が「お亡くなりになった日から10ヶ月」と考えがちですが、これは正確ではありません。実は、相続税の申告期限は「死亡の事実を知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められています。
相続開始日のカウント方法
例えば、1月15日に親族が亡くなり、その連絡を1月20日に受けた場合、申告期限は1月20日の翌日から10ヶ月後となります。この「知った日」を起点とする考え方は、次のような特殊なケースに配慮したものです。
- 海外在住の親族が亡くなり、現地での手続きで連絡が遅れる場合
- 遠方に住む親族の訃報が数日後に届く場合
- 災害などの特殊な状況で死亡の事実確認に時間がかかる場合
申告期限と納付期限は同日
相続税については、申告書の提出と税金の納付を同じ期限内に完了させる必要があります。これは国税庁が定める原則です。
具体的な手続きは次の通りです。
申告書の提出先:
被相続人(亡くなった方)が最後に住んでいた場所を管轄する税務署に提出します。例えば、東京都港区にお住まいだった方の場合は、麻布税務署が提出先となります。
納付方法:
- 現金納付:税務署の窓口で直接支払い
- e-Tax:オンラインでの電子納税
※詳細はこちら - ダイレクト納付:登録した金融機関口座から引き落とし
- クレジットカード納付:国税庁指定のウェブサイトから手続き
- 窓口納付:金融機関での支払い
土日・祝日の場合は翌営業日に繰り下げ
申告期限が土曜日、日曜日、祝日と重なった場合は、その次の平日が期限となります。たとえば、本来の期限が日曜日だった場合、自動的に翌月曜日が期限日となります。
なお、郵送での提出や電子申告(e-Tax)を利用すれば、窓口の営業時間を気にせず、期限日ぎりぎりまで対応することは可能です。ただし、システムトラブルや配送の遅延などのリスクを考慮すると、できるだけ余裕を持った申告が望ましいでしょう。
このように、相続税の申告期限には様々なルールがありますが、期限超過による追徴課税を避けるためにも、早めの準備と対応を心がけることが重要です。不安な点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
申告期限・納付期限までの具体的な流れ
相続税の申告・納付は、相続人の確認から税務署への提出まで、いくつかのステップを踏んで進めていく必要があります。ここでは期限内に完了させるための具体的な流れを解説します。
相続人・相続財産の確認
相続税の申告に向けた第一歩は、相続人と相続財産の確認です。戸籍謄本等を収集して法定相続人を確定し、預貯金や不動産などの相続財産を洗い出します。この段階で相続放棄を検討する場合は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。
遺産分割協議・必要書類の準備
相続税の申告には多くの書類が必要となります。まずは基本的な添付書類を把握しておきましょう。
申告には次のような書類を用意する必要があります。
- 戸籍謄本一式(被相続人と相続人全員分)
- 被相続人の除籍謄本
- 遺産分割協議書(原本)
- 財産評価に関する書類(預貯金の残高証明書、不動産の評価証明書など)
- 債務や葬式費用の領収書
- 贈与税の申告書の写し(過去3年以内に贈与を受けた場合)
これらの書類収集には相応の時間がかかるため、できるだけ早めに準備を始めることが重要です。なお、期限内に遺産分割協議が整わない場合でも、法定相続分に基づいて申告することが可能です。
申告書の作成
相続財産が確定したら、申告書の作成に入ります。この段階では、不動産の評価計算や、上場株式・非上場株式の評価、各種特例(小規模宅地等の特例など)の適用判断が必要となります。相続税の申告は専門知識が必要な作業です。
税理士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
- 財産評価の適正な判断が可能
相続財産の評価方法は資産の種類によって異なり、特に不動産の評価は複雑です。税理士は豊富な経験から適切な評価方法を選択できます。 - 各種特例の適用判断
小規模宅地等の特例など、相続税の軽減につながる特例の適用可否を正確に判断できます。 - 確定申告との調整
被相続人の準確定申告など、相続に関連する他の税務申告との調整も一括して対応が可能です。
納税資金の確保
申告と同時に納税も必要となるため、早い段階から資金計画を立てることが重要です。相続財産の現金化や金融機関からの借入れなど、具体的な資金確保の方法を検討し、10ヶ月の期限内に間に合うよう準備を進めます。
税務署への申告・納付手続き
最終ステップは、税務署への申告書の提出と納付です。申告書は被相続人が亡くなった時の住所地を管轄する税務署に提出します。提出方法は窓口持参、郵送、e-Taxから選択可能です。納付については、金融機関の窓口での現金納付のほか、電子納付やクレジットカード納付など、複数の方法から選べます。
相続税の申告・納付は一連の流れの中で進めていく必要があります。特に相続人が複数いる場合は合意形成に時間がかかることもあるため、できるだけ早めに着手することをお勧めします。期限内の申告・納付が難しいと感じた場合は、早めに税理士などの専門家に相談することで、スムーズな手続きが可能となります。
申告期限に遅れそうな場合の対処法
相続税の申告期限が迫っているものの、書類の準備や財産の把握が間に合わないケースがあります。ここでは、申告期限に間に合わない可能性が出てきた場合の対応策を解説します。
申告期限の延長が認められるケース
相続税の申告期限の延長は、限定的な場合にのみ認められます。具体的には以下のような事由が生じた場合、税務署への申請により最大2ヶ月の範囲で延長が認められる可能性があります。
- 遺言書の新たな発見や遺贈の放棄があった場合
- 相続人となる胎児が生まれた場合
- 認知等により相続人に異動が生じた場合
- 死亡退職金の支給が確定した場合
また、以下のような特殊な事情がある場合も、延長が検討される場合があります。
- 海外在住の相続人が必要書類を準備できない場合
- 災害により資料が散逸した場合
- 相続財産の把握に著しく時間を要する場合
期限延長の申請手続き
期限延長を申請する場合は、以下の点に注意が必要です。
・申請時期:申告期限よりも前に申請する必要があります
・必要書類:延長が必要な理由を具体的に示す資料を提出します
・申請窓口:所轄の税務署での事前相談が必要です
ただし、これらの事由に該当する場合でも、安易な延長は認められません。延長が認められた場合も、その期間内に速やかに申告・納付を行う必要があります。
早期相談の重要性
申告期限に間に合わない可能性が出てきた場合、最も重要なのは早期の専門家相談です。期限延長の検討は専門的な判断が必要なため、できるだけ早い段階で税理士に相談することをお勧めします。早期相談には以下のようなメリットがあります。
- 期限までのスケジュール管理ができる
- 必要書類の準備に余裕を持てる
- 相続人間の調整に時間的余裕が生まれる
- 万が一の場合の代替案を検討できる
納付期限に間に合わないときの具体策
相続税の納付について、資金面での準備が整わないケースは少なくありません。ここでは、納付が困難な場合の具体的な対応策を解説します。
延納制度の利用
延納制度は、相続税を分割して納付することができる制度です。以下の要件を満たす必要があります。
- 納付税額が10万円を超えていること
- 金銭で一時に納付することが困難な事情があること
- 担保を提供できること
- 延納税額に対して利子税が課されることを了承すること
申請には、延納申請書のほか、担保提供関係書類、財務状況を示す書類などが必要です。延納が認められると、最長20年にわたる分割納付が可能となります。
物納制度の活用
延納を利用しても納税が困難な場合は、物納制度を検討できます。物納とは、現金の代わりに不動産や有価証券などで納税する制度です。物納できる財産には以下の優先順位があります。
- 第1順位:国債、地方債など
- 第2順位:不動産
- 第3順位:その他の財産
納税資金の確保方法
物納・延納以外にも、以下のような資金確保の方法があります。
不動産の売却
相続財産である不動産を売却して納税資金を確保する方法です。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 売却までの時間を考慮する
- 適正価格での売却を心がける
- 相続人全員の合意が必要
金融機関からの借入
金融機関では相続税の納付に対応した様々な融資制度を用意しています。
不動産担保ローン
相続した不動産や既存の不動産を担保として融資を受ける方法です。一般的な不動産担保ローンと比べて金利が低く設定されていることが多く、比較的長期の返済期間を設定できます。ただし、担保評価や返済計画の審査があるため、申込から融資実行まで1ヶ月程度の時間が必要です。
相続税対策専用ローン
相続税の納付に特化した金融商品で、一般的な不動産担保ローンよりも手続きが迅速です。都市銀行や信託銀行を中心に取り扱っており、相続税額の最大90%程度まで借入できる場合もあります。審査基準も相続税納付に配慮した設計となっているのが特徴です。
事業性融資(事業用資産を相続した場合)
事業用の不動産や事業そのものを相続した場合、事業性の融資を活用できる可能性があります。この場合、事業の収益性や将来性も考慮した審査となるため、純粋な不動産担保融資よりも有利な条件となることもあります。
なお、いずれの借入方法も、金融機関によって融資条件や審査基準が異なります。また、借入から実際の融資実行まで一定の時間を要するため、納付期限に余裕を持って相談することが重要です。
生命保険金の活用
被相続人の生命保険金がある場合は、納税資金として活用できます。比較的早期に受け取れ、相続税の課税対象からも一定額が控除されるメリットがあります。
このように、納付資金が不足する場合でも様々な対応策があります。ただし、いずれの方法も申請や手続きに時間を要するため、できるだけ早い段階での検討と準備が重要です。不安な点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
-
申告期限に遅れるケースが絶対にないとは言えません。ただし、専門家(税理士)へ依頼があって正式に受託された相続税申告において期限後申告となるケースは少ないでしょう。専門家である以上、期限内申告にこだわっているという点もありますが、期限に間に合わなそうな依頼を受け付ける税理士が少ないという背景もあります。
当該「期限に間に合わなそう」と専門家が判断する最も典型的なパターンが相続人同士揉めている(遺産分割協議がまとまらない)場合です。双方とも代理人(弁護士)を立てて争うという状況下では税理士はご依頼の受託を躊躇します。
専門家が仕事を受けられないようなケースにおいては申告期限に間に合わないという事態も予想されます。 - 徳永税理士事務所
所長 徳永 圭
申告期限を過ぎた場合のペナルティと軽減策
相続税の申告期限を過ぎてしまった場合、追加的な税負担が発生します。しかし、その後の対応次第で負担を軽減できる可能性もあります。
期限超過による追加負担
申告期限を過ぎると、以下のような追加の税負担が生じます。
- 延滞税:納付遅延に対する利息的なもの
- 無申告加算税:期限内に申告しなかった場合のペナルティ(税額の15%~20%)
- 重加算税:悪質な場合の重いペナルティ(税額の35%~40%)
早期対応による負担軽減
期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く対応することが重要です。例えば、税務署からの指摘前に自主的に申告を行えば、加算税が軽減される場合があります。
このような事態に直面した場合は、すぐに税理士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、追加的な税負担を最小限に抑えることができます。
特殊なケースで申告期限が変わる・手続きが複雑になる例
相続税の申告は、状況によって手続きが複雑になったり、通常より時間を要したりすることがあります。ここでは、特に注意が必要な特殊なケースについて解説します。
海外在住の相続人がいる場合
近年、海外在住の相続人がいるケースが増えています。この場合、書類の取得や連絡調整に通常以上の時間がかかるため、早めの対応が必要です。
海外在住者との相続手続きで特に時間を要する点として、戸籍謄本等への署名や押印の取得、現地の公証手続き、書類の国際郵送などがあります。これらの問題に対処するため、日本国内の親族や専門家に包括的な委任状を作成してもらい、代理人として手続きを進めることも検討に値します。
また、海外在住の相続人が日本の相続手続きに不慣れな場合も多いため、現地の法律専門家と日本の税理士が連携して対応することで、スムーズな手続きが可能となります。
相続放棄・限定承認の検討
相続人は、相続開始を知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄や限定承認を選択することができます。この熟慮期間は相続税の申告期限(10ヶ月)より短いため、まずはこの判断を優先して行う必要があります。
相続放棄を選択した場合、その人の相続税申告は不要となりますが、他の相続人の税負担が増える可能性があります。例えば、被相続人に多額の借金があった場合、相続放棄をした人の分の債務も他の相続人が負担することになります。
限定承認の場合は、相続財産の範囲内でのみ被相続人の債務を返済する責任を負います。ただし、手続きが複雑で専門家のサポートが必要になることが一般的です。
遺産分割協議が長期化したとき
相続人間で遺産分割の協議が長引くケースは少なくありません。しかし、申告期限は協議の進行状況に関係なく設定されているため、期限内に分割が確定しない場合でも申告は必要です。
このような場合、法定相続分などに基づいて一旦申告を行い、その後分割が確定した時点で修正申告を行うという対応が可能です。具体的には次のような流れになります。
- 申告期限までに:法定相続分などで暫定的に申告
- 遺産分割協議成立後:実際の分割内容に基づいて修正申告
このように、特殊なケースでは通常以上に慎重な対応が求められます。特に、海外在住者がいる場合や遺産分割協議が難航しそうな場合は、早い段階から税理士などの専門家に相談し、期限に余裕を持って手続きを進めることが重要です。
相続税申告を成功させるためのポイント
相続税の申告を円滑に進めるためには、事前の準備と適切な専門家の選択が重要です。ここでは、申告を成功に導くための具体的なポイントを解説します。
スケジュール管理と情報整理
相続税の申告を成功させるためには、できるだけ早い段階からの準備が欠かせません。理想的には被相続人の生前から、相続が発生した際の対応を検討しておくことが望ましいでしょう。
相続発生後の主なスケジュールは以下の通りです。
死亡直後にすべきこと
- 死亡診断書の取得と死亡届の提出
- 相続人の把握と連絡調整
- 預貯金の凍結手続き
- 葬儀の手配
3ヶ月以内に決めること
- 相続を受けるか放棄するかの判断
- 限定承認を選択するかの検討
- 相続人間での基本的な方針確認
10ヶ月以内の申告に向けて
- 財産の調査と評価
- 遺産分割協議の実施
- 必要書類の収集
- 納税資金の準備
税理士の選び方
相続税の申告を任せる税理士は、慎重に選ぶ必要があります。相続税に精通した税理士を見極めるポイントとして、以下のような点に注目します。
専門性の確認
- 相続税の申告実績件数
- 相続税専門のチームの有無
- 相続に関連する税務以外の知識
報酬体系の確認
- 着手金と成功報酬の内訳
- 追加費用が発生する条件
- 分割払いなどの柔軟な対応
なお、税理士選びで重要なのは、単に経験や報酬だけでなく、相談のしやすさや説明の丁寧さなども重要な判断基準となります。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
-
相続税申告をスムーズに進めるために重要な点を何か一つ挙げるとするなら、相続開始前の「被相続人が行う準備」につきます。相続が発生してからではできることが限られてしまうからです。
現行法において日本は、各相続人が一定の権利を主張できるため法定相続分から逸脱した遺産分割案を受け入れるのは難しく、そのような案を考えているのであれば被相続人が生前から遺言書を準備する、生命保険に加入するなどの対策が必要となります。
また、各相続人へ資産を平等に分配しようと考えていたとしても、主たる資産が不動産のみでは分割が難しく売却や共有を検討しなくてはなりません。売却を急げば、適正価額での取引が損なわれるし、所有権者が多くなる共有は権利関係が複雑になり、おススメできません。生前から分割しやすい資産に組み替えるなどを検討しておきましょう。 - 徳永税理士事務所
所長 徳永 圭
まとめ
相続税の申告は、多くの方にとって人生で数少ない重要な手続きです。本記事で解説してきた重要なポイントを最後にまとめておきましょう。
相続税の申告期限は「亡くなった日を知った日の翌日から10ヶ月以内」と法律で定められています。この期限は申告と納付の両方に適用され、土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日が期限となります。
万が一、申告期限に間に合わないことが予想される場合でも、諦めることはありません。延納制度や物納制度の活用、また場合によっては期限の延長申請も可能です。ただし、これらの制度を利用するためには、事前の準備や要件の確認が必要となります。
申告期限を過ぎた場合は、延滞税や加算税などのペナルティが課されます。しかし、自主的な修正申告を行うことで、ペナルティを軽減できる可能性もあります。
特に、海外在住の相続人がいる場合や遺産分割協議が長期化する可能性がある場合など、特殊な事情がある場合は、早めの情報収集と対策が重要です。このような場合こそ、経験豊富な税理士への相談が有効です。私たち税理士紹介センタービスカスでは、お客様の状況に応じた最適な税理士をご紹介させていただきます。相続税申告に関する不安や疑問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

- この記事の監修者
- 徳永税理士事務所
所長 徳永 圭
事務所公式ホームページはこちら