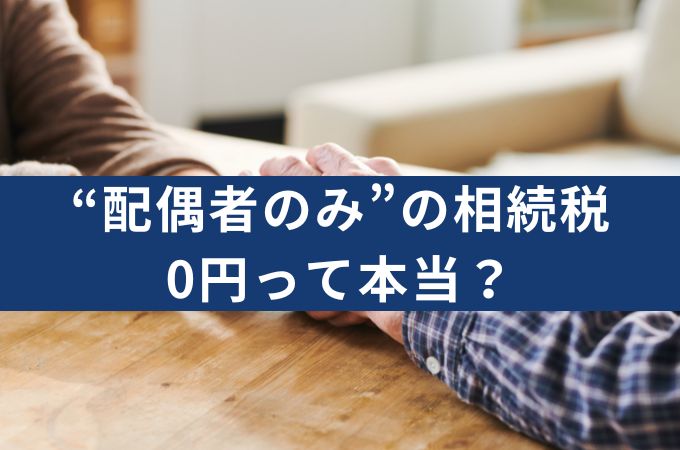最初に結論!「配偶者のみの相続」で知っておくべき3つのポイント
ポイント1.「配偶者の税額軽減」で相続税0円になるケースが多い
配偶者が相続する場合、「配偶者の税額軽減」という特例により、最大1億6,000万円まで、または法定相続分相当額までの相続について税金がかかりません。この制度は、長年連れ添った配偶者の生活基盤を守るために設けられた重要な特例です。ただし、この特例は自動的に適用されるわけではありません。相続税の申告を行わないと、せっかくの優遇措置を受けられないため、注意が必要です。
ポイント2.「基礎控除」との組み合わせでさらに安心
相続税には基礎控除という制度があり、「3,000万円+法定相続人数×600万円」までの金額については課税対象から除外されます。配偶者のみが相続人となる場合、法定相続人は1人となるため、基礎控除額は3,600万円となります。この基礎控除と先ほどの配偶者の税額軽減を組み合わせることで、多くのケースで相続税の負担を大きく軽減できます。特に遺産総額が比較的小さい場合は、そもそも相続税が発生しないケースも少なくありません。
ポイント3.「子あり・子なし」で手続きや遺産分割の考え方が変わる
相続の手続きや税額計算は、子どもの有無によって大きく変わってきます。
子どもがいない場合、被相続人の両親・祖父母など直系尊属や兄弟姉妹が法定相続人となり、相続の範囲が広がることがあります。
子どもがいる場合にも、配偶者だけに全財産を相続させるか、子どもにも一部を分けるかという判断が必要になります。この選択によって、最終的な相続税額が変わってくるため、慎重な検討が求められます。財産の規模や家族関係に応じて、最適な相続の方法を選択することが重要です。
「配偶者のみ」で相続した場合の具体的な仕組み
「配偶者のみが財産を相続する」といっても、実際には子どもや親、兄弟姉妹が相続人となるケースもあります。その場合でも、遺産分割協議で配偶者が全財産を取得する形にすることは可能です。法定相続人の構成や遺産分割方法によって適用される特例や手続きが変わるため、事前にしっかり確認しましょう。
1.なぜ配偶者は相続税が大幅に軽減されるのか?
配偶者の税額軽減(いわゆる「配偶者控除」)は、夫婦が共に築き上げた財産を surviving spouse(残された配偶者) が安心して引き継ぐことができるようにするための制度です。この制度では、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額 のいずれか大きい金額まで、相続税が非課税となります(ただし、遺産分割協議などで「配偶者が実際にその財産を取得する」ことが確定していることが要件となります)。これは、婚姻期間中に夫婦で協力して形成した財産について、実質的な共有財産としての性質を認め、配偶者の生活基盤を守ることを目的としています。特に高齢化社会において、残された配偶者の生活保障を国として支援する重要な制度となっています。
2.相続税の申告は必要?基礎控除との関係をおさらい
相続税の基礎控除は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」という計算式で算出されます。配偶者のみが相続人となる場合、法定相続人は1名となるため、基礎控除額は3,600万円となります。基礎控除額(3,600万円)を超えない総遺産額の場合は、原則として相続税は発生せず、申告も不要となります。ただし、重要な注意点として、配偶者の税額軽減を受けるためには、たとえ結果として税額が0円になる場合でも、必ず申告書を提出する必要があります。期限内に適切な申告を行わないと、この有利な特例が適用されないため、特に注意が必要です。
3.「子あり・子なし」で相続人が変わる
相続人の範囲は、子どもの有無 によって大きく変わってきます。子どもがいない場合、民法の規定により、被相続人の両親・祖父母等、直系尊属(第二順位)や兄弟姉妹(第三順位)まで相続人の範囲が広がります。
一方、子どもがいる場合は、配偶者と子どもが法定相続人となり、その間での遺産分割をどうするかが重要な検討事項となります。特に注目すべきは、遺産分割の方法によって将来の相続税負担が変動する点です。例えば、配偶者が一旦全額を相続し、その後子どもに生前贈与をする など、長期的な視点での検討が必要になります。このため、相続の際は税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
ケース別!相続税シミュレーション
ケース1.子なし・総財産5,000万円の場合
このケースでは、基礎控除額3,600万円と配偶者の税額軽減の組み合わせにより、相続税が実質0円となります。具体的な計算を見てみると、総財産5,000万円から基礎控除3,600万円を差し引いた1,400万円が課税対象となりますが、これは配偶者の税額軽減の上限(1億6,000万円)を大きく下回るため、最終的な相続税額は0円となります。
ただし、配偶者の税額軽減を確実に受けるためには、申告書の提出が必要です。申告をせずに特例を逃してしまうことのないよう、専門家への相談を検討することをお勧めします。
ケース2.子あり・総財産1億円の場合
子どもがいる場合、民法上の法定相続分は配偶者が1/2(5,000万円)、子どもが1/2(5,000万円)となります。この場合の税額計算には複数のシナリオが考えられます。
配偶者が全額(1億円)を相続する場合、配偶者の税額軽減の適用により、相続税を最小限に抑えることが可能です。一方、子どもに一部を相続させる場合は、子ども分には配偶者の税額軽減が適用されないため、総額での税負担が増えます。ただし、将来の相続も考慮に入れると、段階的な財産移転が有利になるケースもあるため、総合的な判断が必要です。
ケース3.不動産が多い場合の注意点
不動産が相続財産の大部分を占める場合は、特に慎重な検討が必要です。自宅や投資用不動産などの評価額が予想以上に高くなり、相続税の課税対象額が膨らむ可能性があるためです。ただし、自宅などの居住用不動産については「小規模宅地等の特例」を活用することで、最大80%の評価額減額が可能です。
この特例の適用を受けるためには、たとえば以下のような要件を満たす必要があります。
- 被相続人が居住用として利用していた宅地であること
- 配偶者や同居親族が相続後も引き続き居住していること
- 一定の期限内に申告を行うこと
ケースによっては80%ではなく50%減額となる宅地もあるため、詳細は税理士等の専門家に確認することをお勧めします。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
-
配偶者のみに財産を相続させる場合、配偶者の生活を確保する事が可能になる反面、相続争いになりかねません。
それは、他の相続人がいる場合、遺留分侵害額請求をされる可能性があるからです。子供や父母・祖父母などの相続人には、遺産の最低限の取り分が法律で認められており、遺留分といいます。この遺留分を侵害している場合は、金銭の支払いを要求されることがあり、注意が必要です。
また、配偶者の税額軽減制度は、先に亡くなった配偶者のみ利用できるので、遺された配偶者に相続が発生した場合は、相続税負担が重くなることが考えられます。よって、立て続けに相続が起こってしまった場合なども想定してシミュレーションする事が重要となります。 - スエナガ会計事務所
代表 末永 寛
「配偶者のみ」でも申告漏れに注意!具体的な手続きの流れ
1.相続発生から相続税申告までのスケジュール
相続税の申告は、被相続人の死亡を起点として10か月以内に完了させる必要があります。このスケジュールを具体的に見ていくと、まず被相続人の死亡後、戸籍謄本の収集や預貯金、不動産などの財産調査を行います。次に、それらの財産評価を行って遺産の総額を確定させ、遺言書の有無を確認します。遺言書がない場合は、相続人間での分割協議が必要になります。
これらの準備が整ってから、相続税の申告書類を作成し、管轄の税務署へ申告・納税を行います。10か月という期限は、これらの手続きを考えると決して余裕のある期間ではないため、早めの準備開始が重要です。
2.必要書類のリスト
相続税の申告には多くの書類が必要となります。基本的な書類として、以下のものが挙げられます。
- 被相続人と相続人の戸籍謄本(被相続人については出生から死亡までの連続した戸籍)
- 住民票除票
- 固定資産税評価証明書
- 預金通帳の写し
- 有価証券の残高証明書
特に配偶者の税額軽減を受ける場合は、婚姻期間を証明する戸籍謄本や、配偶者が相続した財産の明細など、追加の書類も必要となります。これらの書類の取得には時間がかかることもあるため、できるだけ早い段階から準備を始めることをお勧めします。
3.申告をしないと受けられない特例がある
配偶者の税額軽減をはじめとする相続税の特例は、自動的に適用されるものではありません。必ず期限内に正しい申告を行う必要があります。特に、「どうせ税金はかからないから」という安易な判断で申告を怠ると、後になって大きな問題となる可能性があります。
申告漏れが発覚した場合、追徴課税に加えて延滞税や加算税などのペナルティが課される可能性があり、予想以上の負担となることがあります。また、一度期限を過ぎてしまうと、有利な特例を受けられなくなってしまうため、専門家に相談しながら、慎重に手続きを進めることが賢明です。
※特例として、未分割で分割見込書を添付して期限内申告を行い、申告後3年以内に分割が整った場合に限り、適用ができます。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
-
相続税の申告で相続人が配偶者のみの場合、相続税額が0円になるケースが考えられます。
この場合に注意が必要なのは、どの計算過程において相続税が0円になったのかという事です。
具体的には、①相続財産の総額が基礎控除以下のため0円、②配偶者の税額軽減適用により0円、③小規模宅地等の特例の適用により0円となるケースです。この場合、②又は③の適用により、結果的に相続税額が0円になった場合は、相続税の申告書を期限内に提出する事によりはじめて適用できます。
このように同じ相続税額0円でも、どの段階で0円になったかにより、手続きが大きく異なり、意味合いが全く異なります。自身の相続において、どの計算過程において相続税が0円になったのかを確実に把握し、整理するようにしましょう。 - スエナガ会計事務所
代表 末永 寛
まとめ&よくある質問
本記事のおさらい
配偶者が単独で相続する場合の重要なポイントを振り返ってみましょう。まず、配偶者の税額軽減制度により、多くのケースで相続税が0円となる可能性が高いものの、この特例を受けるためには必ず申告が必要です。次に、子どもの有無によって法定相続人の範囲が変わり、それに伴って最適な申告方法も変化します。さらに、相続税の申告は被相続人の死亡から10か月以内という期限があり、必要書類の準備や各種特例の適用漏れがないよう、計画的な対応が求められます。早めに専門家に相談し、適切な準備を進めることで、スムーズな相続手続きが可能となります。
よくある質問(FAQ)
Q1.配偶者が全額相続すれば常に相続税は0円?
配偶者の税額軽減には上限があり、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか大きい金額を超える場合は、超過分に対して相続税が課税されます。特に多額の遺産がある場合は、専門家に相談して適切な対策を検討することが賢明です。
Q2.子どもに少しでも財産を譲ると税額に影響する?
子どもへの相続は配偶者の税額軽減の対象とならないため、相続時点での税負担は増える可能性があります。ただし、将来の相続を見据えた場合、段階的な財産移転が総合的に見て有利になるケースもあるため、長期的な視点での検討が必要です。
Q3.そもそも申告しなくてもバレないのでは?
税務署は、金融機関や法務局から様々な情報を入手できる体制が整っており、申告漏れの発見は比較的容易です。発覚した場合、追徴課税に加えて重い加算税が課されるリスクがあります。また、配偶者の税額軽減などの有利な特例も受けられなくなってしまうため、必ず適切な申告を行うことが重要です。

- この記事の監修者
- スエナガ会計事務所
代表 末永 寛
事務所公式ホームページはこちら