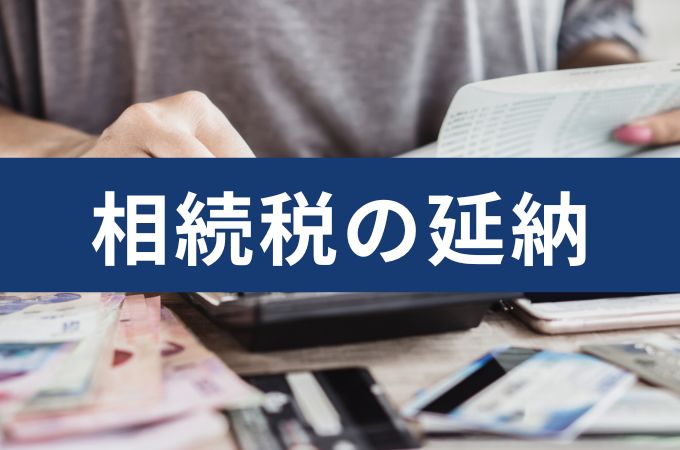相続税の延納とは?基本的な仕組み
相続税の延納制度とは、相続税の納付が困難な場合に、税務署長の許可を得て税金を分割して納める特例制度です。本来、相続税は相続開始を知った日の翌日から10か月以内に一括納付するのが原則ですが、相続財産の状況によっては一度に全額を支払うことが難しいケースもあります。そこで相続税法では、一定の条件を満たす場合に年賦(毎年分割)での納税を認めています。
延納が必要となる主な場面
延納が必要となるのは、主に以下のようなケースです。
- 相続財産が現金化しづらい資産中心の場合:不動産や事業用資産、非上場株式など、すぐに換金できない資産が相続財産の大半を占めるケース
- 高額な相続税の一括納付が生活や事業に支障をきたす場合:納税額が数千万円以上で、一度に支払うと日常生活や事業継続に大きな影響が出る可能性がある場合
- 資産価値を維持したい場合:不動産市況が悪い時期に急いで売却すると損失が生じるため、資産を保持しながら分割納付したい場合
延納と物納の違い
相続税の納付が困難な場合の救済措置として「延納」と「物納」がありますが、両者には重要な違いがあります。
延納(えんのう)は、相続税の分割納付制度です。一括払いが困難な場合に、一定の条件のもと年賦(毎年分割)で納税を認める仕組みとなっています。納税者の申請と税務署長の許可により、相続税を何年かに分けて支払いますが、その間は利子税(延納利息)がかかります。
一方、物納(ぶつのう)は、延納でも支払えない場合の最終手段として、相続財産そのものを納税に充てる制度です。不動産や有価証券など一定の財産を国に納め、税金の代わりに充当します。物納は延納よりさらに厳しい条件下で認められ、どんな財産でもよいわけではなく国が定める順位に沿った資産に限られます。
つまり、延納は「納税の猶予(分割払い)」であるのに対し、物納は「納税手段の変更(現物納付)」です。延納は将来的に現金で支払う必要がありますが、物納は現金の用意が困難な最終手段として財産そのもので納税します。
どんな人が延納を選ぶべき?
延納制度は誰でも利用できるわけではなく、また状況によっては他の選択肢の方が有利な場合もあります。以下のような方は延納を選ぶことで恩恵を受けられる可能性があります。
- 手元資金では納税が難しい人:預貯金だけでは相続税を全額用意できない場合
- 将来の収入で納税見込みがある人:不動産収入や事業収入などから計画的に納税できる見通しがある場合
- 資産をすぐに手放したくない人:相続財産を急いで売却せず、保有資産の維持を優先したい場合
- 専門家のサポートを受けられる人:税理士など専門家と連携して手続きを進められる場合
相続税の延納を利用するための条件
相続税の延納制度を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。税務署は申請内容を厳格に審査し、条件を満たしていないと判断すれば延納申請は却下されます。
延納申請の基本条件
| 条件項目 | 内容 |
|---|---|
| 相続税額 | 10万円超であること |
| 金銭納付困難 | 金銭での一括納付が客観的に困難と認められること |
| 担保要件 | 延納税額が100万円超の場合や延納期間が3年超の場合は担保提供が必要 |
| 申請要件 | 『延納申請書』及び『担保提供関係書類』を納期限までに提出すること |
延納の申請期限とスケジュール
申請期限は相続税の納期限まで
延納の申請は、相続税の申告・納付期限(被相続人の相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに行う必要があります。この期限を過ぎてからの申請は一切認められないため、延納を検討している場合は早めに準備を始めることが重要です。
申請から許可までの期間
延納申請後、税務署による審査が行われます。通常、延納申請書の提出期限の翌日から起算して3か月以内に許可または却下の通知が送付されます。ただし、担保の評価等で時間がかかる場合は審査期間が最長6か月まで延長されることもあります。
担保書類の提出期限延長
申請期限までに担保関係書類の準備が間に合わない場合、「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出することで、担保書類のみ提出期限を延長できます。1回につき3か月、最長6か月の延長が可能ですが、納期限までに延納申請自体は出しておく必要があります。
納付スケジュール
延納が許可された場合、延納許可通知書に記載されたスケジュールに従って年賦払いを開始します。不許可(却下)の場合は延納申請却下通知書が届き、速やかに全額に加え、利子税と延滞税を納付する必要があります。
延納の利子税とは?
延納を利用する場合、本来の相続税に加えて「利子税」が課されます。これは分割払いの特例を利用する対価として支払う利息のようなものです。
利子税率と延納期間の関係
- 不動産等の割合が75%以上:不動産等は最長20年延納可能、利子税率は低め(3.6%や5.4%等程度)
- 不動産等の割合が50%以上75%未満:不動産等は最長15年延納可能も利子税率は低め(3.6%や5.4%等)
- 不動産等の割合が50%未満:不動産等は最長5年延納可能、利子税率は高め(6.0%等)
延納期間や利子税の割合は、不動産等の割合(不動産、立木、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並びに特定同族会社の株式及び出資の割合)に応じて計算されます。延納期間中は固定金利で適用されます。この利子税は経費にはならず全額が相続人の負担となるため、銀行借入れとの比較も検討する価値があります。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
-
相続税の延納制度は、誰でも簡単に利用できる制度ではなく、「金銭納付が困難である」と認められる必要があります。
ここで注意したいのは、相続した財産だけでなく、ご自身が保有している預金や有価証券も審査対象になる点。また、生活費や事業経費を計算することも明示されており、納税後の資金繰りも考慮する必要があります。
申請の結果、許可された延納額が想定より少ないと、不足分を手元資金で補うことになり、生活に影響を及ぼすこともあります。こうしたリスクを避けるためにも、まずは早めに専門家へ相談し、延納が認められる見込み額や支払計画を具体的にシミュレーションしておくことが大切です。
延納以外の方法も含めて事前の検討を十分に行い、納税への負担を最小限に抑えましょう。 - 鈴木洋輔税理士事務所
所長 鈴木 洋輔
相続税の延納の手続きと必要書類
相続税の延納を利用するためには、正確な手続きと必要書類の提出が不可欠です。申請内容に不備があると審査に通らず、延納が認められないリスクがあります。
延納申請の流れ
-
延納計画の検討
延納条件の確認、税額・分割回数・担保財産を検討。財産評価額や自己資金の状況を整理し、税理士など専門家に相談するのが望ましい。 -
申請書類の準備
「相続税延納申請書」に延納申請税額や分割回数を記入。「金銭納付を困難とする理由書」と担保提供関係書類も準備。自己資金や相続財産の状況、一括納付が困難な理由を具体的数値で説明することが重要。 -
税務署へ提出
相続税納期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに申請書と添付書類一式を提出。相続税申告書も同日までに提出し、延納できない部分は納付。 -
担保書類の延長手続き(必要時)
担保書類が間に合わない場合は「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出。最長6か月*延長可能だが、届出自体は納期限内に必要。
*1つの届出で延長できる期限は3か月以内で、再延長できる期間は、延納申請期限の翌日から起算して6か月を超えることができない -
審査と結果通知
約3か月以内に延納許可または却下の通知書が送付される。審査中は追加資料依頼に速やかに対応する。 -
延納期間の開始
許可通知受領後、記載されたスケジュールに従い分割納付を開始。各期限までに分納税額と利子税を納付。
必要書類一覧
| 書類名 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 相続税延納申請書 | 延納申請税額、分割回数、納付スケジュールを記載。税額等は申告書と整合性を取ること。 |
| 担保目録及び担保提供書 | 担保財産の種類・価額・所在地や銘柄等を明記。不動産は時価に近い評価額が必要。 |
| 担保提供関係書類 | 担保の種類に応じた証明書類。不動産:登記事項証明書、固定資産税評価証明書、有価証券:供託書正本 |
| 金銭納付を困難とする理由書 | 一括納付が困難な理由を具体的数値で説明。相続財産と自己資金の状況を明示し、客観的に困難と判断できる内容にする。 |
| その他必要書類 | 状況に応じて税務署から指示される追加書類。 |
申請時の注意点とよくあるミス
提出期限の厳守
延納申請は期限内提出が絶対条件です。1日でも遅れると受理されず延納できなくなります。一括納付が困難だとわかったら、お早めに延納の検討を始めるのが理想的です。
書類の不備・漏れ
延納申請書や担保関係書類に記載漏れ・誤りがあると、税務署から補完を求められます。提出前にチェックリストで書類不備がないか再確認することが重要です。記載内容の整合性も重要で、相続税申告書の内容と延納申請書の数値が一致しているか確認しましょう。
担保の選定ミス
担保にできない財産を提示すると却下原因になります。例えば法律上担保設定が禁止されている財産や、共有持分のみの不動産、争いのある財産などは担保不適格とされます。担保は余裕をもった評価額のものを準備するのが安全です。
「納付困難」の誤解
税務署は相続人本人の既存の預貯金や有価証券も含めて審査します。生活費3か月分等の必要最低限以外は納税に充てる前提で計算されるため、「相続財産では不足でも自分の貯蓄で補える」と判断されると延納は認められません。
単に「支払いたくない」「面倒だから分割にしたい」といった理由では延納は認められません。客観的に見て、一括納付が本当に困難と判断できる状況でなければ許可されない点を理解しておきましょう。
相続税の延納が認められないケース
どんなに準備を整えて申請しても、延納が認められないケースがあります。ここでは、延納申請が却下される理由と、延納できない場合の代替手段について解説します。
申請が却下される理由
条件を満たしていない
延納の法定要件(税額10万円超、一括納付困難など)を満たさない場合は許可されません。例えば、相続税額は高額でも申請者自身の預金額が十分にあり、一括納付可能と判断された場合などは延納が却下されます。
書類不備・手続きミス
延納申請は手続きの正確性も重視されます。申請書の記載内容に重大なミスがある場合や、期限内に必要書類が揃わず補完もされなかった場合は却下されます。「金銭納付を困難とする理由書」の根拠が不十分であると、その妥当性が認められず延納申請が却下されることもあります。
担保要件を満たせない
延納税額が大きいのに担保を用意できない、担保評価額が延納税額に足りない、担保不適格な資産しかない、といった場合も許可されません。例えば、相続税5,000万円の延納を希望しても、提供できる担保が評価額3,000万円の不動産しかない場合、不足分の担保がないため全額の延納は認められません。
申請期限後の申し出
納期限を過ぎてから「やはり延納したい」と申し出ても認められません。一度却下された後に再申請は基本的にできないため、チャンスは一度きりと心得て正確に手続きする必要があります。
延納中の条件違反
延納許可後の話ですが、延納期間中に担保財産を無断で処分したり、分納税額を滞納したりすると許可が取り消される場合があります。特に、毎年の分納税額の納付を怠った場合は、ほぼ確実に延納許可が取り消されます。
延納できない場合の代替手段(物納・借入など)
物納を検討する
延納が却下された、または延納でも支払いきれない場合は、物納の制度利用を検討します。物納は延納でもなお金銭納付が困難な金額について、不動産や有価証券などで納付する方法です。
ただし物納にも厳格な要件と提供できる財産の順位制限があり、延納以上にハードルが高い制度です。物納できる財産も順位が定められており、国が管理・換金しやすいものから順に受け入れられます。
金融機関からの借入
延納の利子税や手続きの手間を考慮すると、銀行ローンで納税資金を借り入れる方が得策な場合もあります。最近は低金利環境のため、延納利子税より銀行ローン金利の方が安いこともあり、総支払額で有利になるケースも少なくありません。
不動産を担保に入れれば、相続財産を売却せずに納税資金を調達できる可能性もあります。
親族間での資金融通
相続人間で話し合い、納税資金が不足する人に対して他の相続人が一時立て替える・貸し付ける方法もあります。後日に資産売却で得た資金で返済する約束を交わすことで、延納による利子負担や手続きなしに納税を完了させることができます。
ただし親族間の金銭貸借はトラブル防止のため書面に残すなど配慮することが大切です。
資産の一部売却
どうしても現金が足りない場合、相続資産の一部売却も選択肢です。延納や物納は手続きが煩雑で時間もかかるため、比較的売却しやすい不動産や株式があるなら早めに売却し納税資金を確保する方が結果的に楽な場合もあります。
被相続人の相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間に不動産を売却した場合、「取得費加算の特例」を活用すれば、譲渡所得税の軽減が可能になり、売却による納税も税務上有利になるケースがあります。
滞納という選択肢はNG
延納が認められないからといって、納税せず放置(滞納)するのは厳禁です。延滞税が日々加算される上、最悪の場合資産の差押えなど強制徴収が行われます。どうしても納税が難しい状況であれば、早めに税務署に相談することをお勧めします。
相続税の延納を利用するメリット・デメリット
相続税の延納制度を利用すべきかどうかを判断するためには、そのメリットとデメリットを十分に理解しておく必要があります。
延納を活用するメリット
納税資金繰りの緩和
延納の最大の利点は、相続税を分割払いできるため、一度に多額の現金を用意する必要がない点です。毎年の収入に応じた計画的な納税が可能になり、生活費や事業資金への圧迫を和らげられます。
例えば、3,000万円の相続税を一括納付すると生活資金が枯渇する場合でも、15年間の延納が認められれば年間200万円程度の納付となり、毎年の収入から捻出しやすくなります。
資産の維持が可能
延納を利用すれば、相続した不動産や株式を直ちに売却せずに済みます。市場状況が悪い中で急いで売却して損をするリスクを避け、資産価値の回復や上昇を待つ余裕が持てます。
特に不動産市場が低迷している時期に相続が発生した場合、延納を利用して売却タイミングを待つことで、資産価値の減少を防ぐことができます。
正式な猶予で安心
税務署から延納許可を受けていれば、未納の状態でも合法的に猶予されているので安心感があります。延滞税がかからず差押えの心配もなく、計画通りに納付していけばよいので、心理的負担が軽減されます。
将来繰上返済も可能
延納は一度許可されたら途中で残額を一括返済することも可能です。経済状況が好転した場合には繰上げ返済する選択肢があり、利子税を抑制することができます。
延納のデメリットとリスク
利子税の負担増
延納を利用すると、本来の相続税額に加えて利子税(利息)を支払う必要があり、トータルの支払額が増えます。延納期間が長いほど利子税の累計額も大きくなる点は大きなデメリットです。
例えば、3,000万円の相続税を15年間延納する場合、利子税率が年2%だとすると、15年間で約450万円の利子税が発生します。つまり、総支払額は3,450万円となり、一括納付より450万円多く支払うことになります。
担保の必要性
高額の延納では担保提供が必須となり、大切な財産に抵当権等を設定することになります。担保に入れた財産は売却や処分が自由にできなくなり、精神的な拘束感があります。
不動産を担保に提供した場合、原則として税務署の許可なくその不動産を売却することはできません。また、担保設定には登記費用などの諸経費も発生します。
手続きの煩雑さ
延納申請には多くの書類準備と専門知識が必要で、手間と時間がかかります。専門家への報酬も含めると、延納申請のためだけに数十万円の費用がかかることも少なくありません。
利用できる人が限られる
延納は誰でも気軽に使える制度ではなく、要件を厳格に満たす一部の人のみが利用できます。例えば、相続財産の大部分が預貯金や上場株式など換金しやすい資産である場合、基本的には延納は認められません。
延納許可後の制約
延納期間中は、税務署の許可なく担保財産の処分ができない、年賦の納付を怠ると即延納取り消しになる*など、行動が制約されます。
*基本的には延納許可を取り消す場合には納税者の弁明を聴くこととされており、即延納取り消しにはなりません。ただし、延納税額に係る担保物につき強制換価手続が開始されたとき、または、当該延納の許可を受けた者が死亡し、その相続人が限定承認をしたときには弁明を聴かなくて良いとされています。
15年や20年という長期にわたって毎年納付を続ける義務を負うことになるため、この間の経済状況の変化などのリスクを考慮する必要があります。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
-
延納を申請する際、担保として提供できる財産には審査があり、想定していた資産だけでは不足する場合があります。申請した担保について、評価額が不足したり、適格でないと判断されると、追加の担保を求められ、希望している担保の範囲で収まらないケースもあります。
また、延納の審査には時間がかかるため、審査結果に満足できず延納を諦めてから不動産等の売却を検討しても、納税期限に間に合わないことがあります。急いで売却を進める場合、売り急ぎと見なされ、買い手に足元を見られて相場より低い価格で売却を迫られるリスクもあります。
こうしたリスクを回避するためには、延納と一括納付の両方のケースを想定し、資産売却による資金確保も視野に入れてスケジュールを組むことが大切です。 - 鈴木洋輔税理士事務所
所長 鈴木 洋輔
相続税の延納に関するよくある質問(FAQ)
相続税の延納について、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1. 延納の審査期間はどのくらいですか?
通常3か月以内、最長6か月かかります。審査中は追加資料の要請にすぐ対応できるようにしておきましょう。この間は納税が猶予されますが、却下された場合は速やかに相続税の全額に加え、利子税と延滞税を納付する必要があります。
Q2. 途中で一括返済はできますか?
できます。例えば15年延納の5年目で完済すれば、残り10年分の利子税が不要になります。
Q3. 延納中に相続財産を売却できますか?
担保財産の場合は事前に税務署の承認が必要です。売却代金で未納額を全額清算するか、代わりの担保を提供するかのいずれかを選択します。無断売却は延納許可取消の原因になりますのでご注意ください。
一方、担保に入れていない財産は自由に売却できます。その売却資金で繰上返済することも可能です。
まとめ
相続税の延納は「誰でも簡単に利用できる制度」ではなく、厳格な要件と手続きが必要です。利用を検討する場合は、早い段階から税理士などの専門家に相談し、自分の状況に最適な納税方法を選ぶことが重要です。
相続税の問題は複雑で専門性が高いため、延納を含む相続税対策については、税理士紹介センターにご相談いただくことをお勧めします。当センターでは、4,200所以上の登録税理士事務所から、お客様の状況に最適な税理士をご紹介いたします。創業29年、20万件以上の相談実績に基づき、あなたの相続税に関する悩みを解決するお手伝いをいたします。

- この記事の監修者
- 鈴木洋輔税理士事務所
所長 鈴木 洋輔
事務所公式ホームページはこちら
YouTubeチャンネル、Instagram