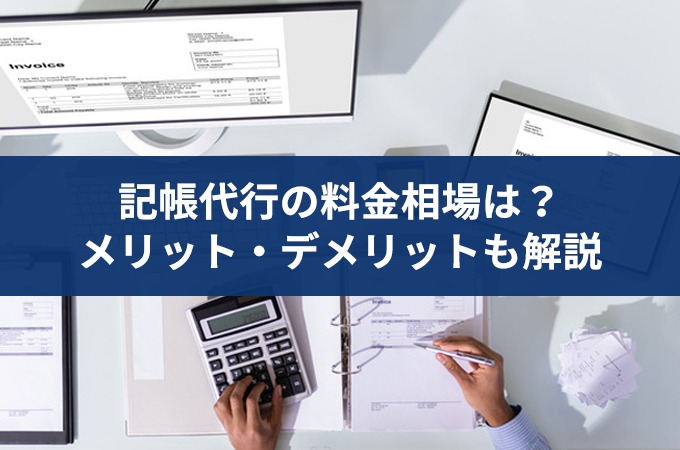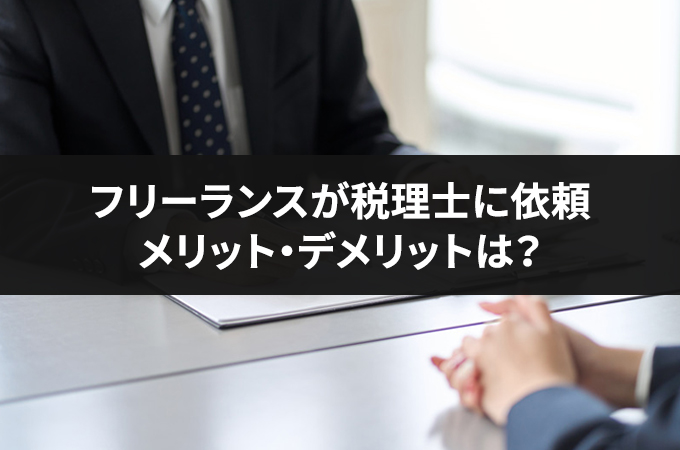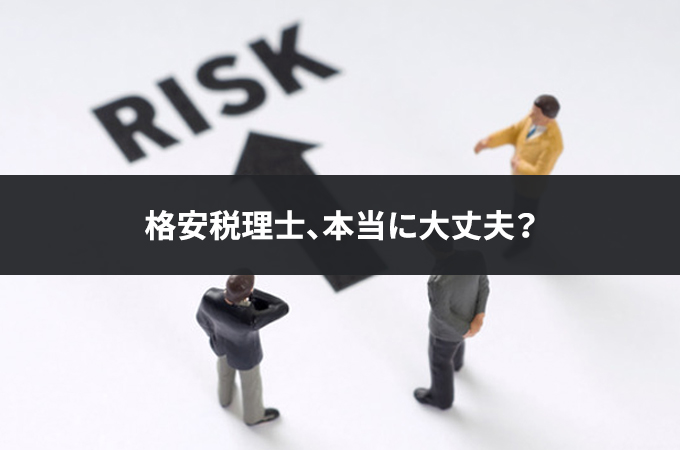経理事務や税務申告の作業を、どこまで税理士に任せるべきか迷っていませんか?
たとえば「記帳代行も含め、すべての経理業務をまるっと依頼している」という方もいれば、「そもそも税理士には依頼せず、会計ソフトを使ってすべて自分で処理している」という方も少なくありません。
実際、記帳代行を利用することで大幅に業務負担を減らせる一方、費用やコミュニケーションの手間といったデメリットもあります。
この記事では、記帳代行を中心に、税理士へ依頼する場合のメリット・デメリットや料金相場、丸投げとの違いをわかりやすくまとめました。
目 次
記帳代行とは?
記帳代行の定義
「記帳代行」とは、税務申告に必要な帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)の作成を、会計事務所や税理士といった専門家に委託するサービスのことです。
もともと「記帳」とは、売上や経費などの取引を正しく仕訳し、帳簿に記録する作業を指します。
実際には税務申告や決算業務などと一体化していることが多いため、「うちは税理士に丸投げしている」という言い方をされるケースも少なくありません。
ただし、一口に「丸投げ」と言っても、日々の現金取引を記録する「現金出納帳」だけは自分(自社)でつけ、それ以外をすべて専門家に任せる場合と、現金出納帳の作成も含めて完全にお任せする場合があります。
見た目は同じようでも、どこまでを自力で行い、どこからを外注するかによって、得られるメリットやコストのかかり方が変わってくる点には注意が必要です。
以下に、一般的な「丸投げ」と「記帳代行」の違いをまとめました。
| 丸投げ | 領収書・請求書・通帳のコピーなど、必要資料をすべて会計事務所に送り、記帳から税務申告まで一括して任せる方法。 |
|---|---|
| 記帳代行 | 日々の「現金出納帳」だけは自分(自社)で作成し、それ以外の帳簿や申告業務を会計事務所に委託する方法。 |
記帳代行が必要な理由
実は、事業を行う以上は帳簿の作成が「義務」です。
確定申告には、より厳格な記帳と申告を行う代わりに税制上の優遇を受けられる 「青色申告」と、簡易な方法で申告を行う「白色申告」があります。
2013年までは白色申告の場合、帳簿を作成しなくても認められていましたが、2014年以降は白色申告でも記帳や帳簿の保存が義務化されました。
一方、青色申告は複式簿記による記帳が必要な反面、最大65万円の特別控除など節税メリットが大きいのが特徴です。結果として「白色のほうが楽」という従来の考え方も、近年ではあまり大きなメリットがない場合が多く、正確な帳簿を作成して青色申告を選ぶことが主流になりつつあります。
そこで、手間のかかる記帳業務を外注してしまい、本業に集中するために記帳代行を活用する事業者が増えているのです。
記帳代行を税理士に依頼するメリット・デメリット
まずは、税理士に記帳代行を依頼するメリット・デメリットを一覧でご紹介します。
【メリット】
- 本業に集中しやすくなる
- 税務のプロとしてワンストップ対応
- 税務調査にも安心感がある
- 経営全般のアドバイスを得られる
- 人件費削減につながる
- 記帳の品質が上がる
【デメリット】
- 費用が割高になりやすい
- どの範囲まで依頼するか明確化が必要
- リアルタイムで数字を把握しづらい
- 社内にノウハウが溜まりにくい
税理士に依頼する主なメリット
税理士に記帳代行を任せると、経理の煩わしさから解放されるだけでなく、税務申告や節税対策まで幅広くサポートしてもらえるのが大きな魅力です。以下では、主なメリットをご紹介します。
本業に集中できる
記帳作業は、直接的に利益を生むわけではないものの、時間と手間がかかるため大きな負担となりがちです。税理士に任せれば、貴重なリソースを本業に専念させることができます。
また、自分で処理した際の入力ミスや計算違いなどを避けられるので、結果的に時間と労力のロスも抑えられます。
税務のプロとしてワンストップ対応
税理士は記帳代行に加えて、確定申告や決算書類の作成・提出まで一括で依頼できる税務のプロフェッショナルです。「税理士には税務代理権がある」ため、税務署への申告や複雑な税法上の手続きも任せられます。
個人事業主の青色申告であれば、記帳から節税対策までカバーできるので、65万円の特別控除などによる大きな減税効果を得られる可能性も高まります。
税務調査にも安心感
税理士に依頼していれば、帳簿の精度が高くなり、税務調査の際にもスムーズに対応できます。
不備や誤りが見つかってから慌てるリスクが減り、適切なアドバイスをもらいながら書類を整えられるため、税務署とのやり取りでも安心感が得られます。
アドバイスを得られる
記帳作業だけでなく、経営全般に関する相談ができるのも税理士の強みです。「自分で記帳して間違えたら困る」「節税できる方法が分からない」といった不安や疑問も気軽に質問でき、最新の税法改正やインボイス制度への対応など、プロの視点でアドバイスを受けられます。
人件費削減になる
業務拡大に伴い、伝票処理や仕訳計上などの事務負担が増えると、社内で新たに経理担当を雇う必要が出てくるケースもあります。しかし、記帳代行を利用すれば、追加採用せずに現行人員で経理を回せるため、人件費の大幅な増加を抑えられる可能性があります。
記帳の品質が上がる
税理士は会計・経理の専門家ですから、取引内容を確認しながら的確な仕訳を行ってくれます。2023年10月施行のインボイス制度や、2024年1月の改正電子帳簿保存法など、法改正にも柔軟に対応してくれるため、記帳の品質を常に高いレベルで維持できます。
税理士に依頼する際のデメリット
一方で、税理士への依頼には費用面や業務範囲の明確化など、注意すべきポイントも存在します。ここでは代表的なデメリットを2つ挙げます。
費用が割高になりやすい
税理士へ「丸投げ」に近い形で依頼するほど、費用は高くなるのが一般的です。
また、料金体系は「1仕訳あたり○○円」や「月額○○円で仕訳数は上限○○件」といった具合に、事務所ごとで大きく異なります。オプションの有無によっても最終的な金額が変わるため、総合的に見て適正価格かどうかを判断しにくい面があります。過大なコストを避けるためにも、見積もりや契約内容をしっかり確認しましょう。
どの範囲まで対応するか明確化が必要
記帳業務をすべて任せると、リアルタイムで数字を把握しづらい場合があります。
会計事務所が仕訳・試算表をまとめるのに2~3ヵ月かかることもあり、 その間に経営環境が変化してしまうと、タイムリーな判断が難しくなるでしょう。
また、社内に記帳や経理のノウハウが蓄積されにくい点もデメリットです。「どこまで外注し、どこを自分たちで行うか」事前にしっかりと整理し、税理士とコミュニケーションを取ることが重要です。
記帳代行業者や経理代行との違い
記帳代行業者の特徴
記帳代行業者は、仕訳帳や総勘定元帳など記帳に特化した代行サービスを提供しています。
具体的には「領収書や請求書の内容をもとに帳簿を作成する」ことがメインで、税務相談や給与計算などの周辺業務は基本的に含まれません。
記帳業務に絞って依頼したい場合、コストを抑えながら必要最低限のサポートを受けられる点が大きなメリットです。
経理代行との業務範囲比較
記帳代行業者と経理代行業者の違いは、ひとことで言えば「どこまで経理業務を任せられるか」です。
経理代行は、給与計算や支払い処理、請求書管理、税金関連の手続きサポートなど、経理業務全般を幅広くカバーするサービスを指します。会社が経理部門そのものを“丸ごとアウトソーシング”したい場合には経理代行のほうが便利ですが、業務範囲が広い分、コストも上がる傾向があります。
一方、記帳だけを依頼して負担軽減を図りたい企業には、記帳代行業者が適しているでしょう。
税理士事務所 vs. 記帳代行業者 vs. 経理代行業者
それぞれのサービス内容や特徴を比較すると、依頼の範囲やコスト、サポート体制に大きな違いがあります。
自社がどこまでの経理作業を外注したいか、税務申告まで任せる必要があるか、などを考えながら選ぶとよいでしょう。
| 比較項目 | 税理士事務所 | 記帳代行業者 | 経理代行業者 |
|---|---|---|---|
| 依頼できる範囲 |
記帳業務から税務申告、税務相談まで 一気通貫で対応可能 |
記帳作業がメイン 提携税理士がいれば申告も可 |
給与計算・支払い処理・請求書管理など 経理全般をアウトソーシング |
| コスト | 幅広いサポート分 費用は高め |
記帳に特化する分 比較的安価 |
業務範囲が広い分 やや高コスト |
| サポート体制 |
税理士資格保有者が担当 税務調査なども安心 |
帳簿作成が中心 税務相談は範囲外 |
経理負担を大幅軽減 税務関連は別途 |
記帳代行の費用相場と料金プラン
記帳代行にかかる主な費用項目
記帳代行の料金は、仕訳数(領収書や伝票の枚数など)に応じて変わるのが一般的です。
たとえば「月に200仕訳まで○○円」「それを超える場合は追加料金」といった形で従量制の課金形態を採用しており、作業量が増えるほど費用も上がります。
また、税理士や会計事務所に依頼する場合は、税務申告や顧問契約をセットにすると記帳代行の単価が割安になるケースもあります。
料金プランの例(税理士事務所の場合 / 記帳代行業者の場合 / 経理代行業者の場合)
税理士事務所に依頼する場合の費用相場
下表は、税理士に記帳代行を依頼した場合の目安料金です。
あくまで相場の一例ですが、税務申告や顧問契約など他の業務とまとめて依頼すると記帳代行が割安になることもあります。
| 仕訳数 | 金額の目安 |
|---|---|
| ~200枚 | 15,000円 |
| 201~300枚 | 20,000円 |
| 301~400枚 | 25,000円 |
| 401~500枚 | 30,000円 |
| 501枚~ | 35,000円 |
記帳代行業者に依頼する場合の費用相場
記帳代行を専門に請け負う業者は、比較的低価格に設定しているのが特徴です。
目安としては「仕訳数100枚で10,000円」「200枚で20,000円~」といった料金形態が一般的で、記帳に特化している分だけ税理士事務所よりも費用を抑えられるメリットがあります。
経理代行業者に依頼する場合の費用相場
経理代行は、企業の経理業務をまるごとアウトソーシングするサービスで、記帳代行もその一環として行われます。
仕訳数による料金相場は次のとおりです。
| 仕訳数 | 金額の目安 |
|---|---|
| ~100枚 | 10,000円 |
| 101~200枚 | 15,000円 |
| 201~300枚 | 20,000円 |
| 301~400枚 | 25,000円 |
| 401枚~ | 30,000円 |
請求書管理や支払い処理、給与計算といった経理全般をまとめて任せられるため負担が大幅に減りますが、税務申告まで含める場合は別途税理士との連携が必要になり、追加費用が発生することもあります。
安さだけで判断するリスク
記帳代行サービスの料金は事業者ごとに異なり、「仕訳数当たりの単価が安い」からといって必ずしもお得とは限りません。
業務範囲やサポート体制によっては追加費用が発生する場合や、コミュニケーション面で不満が出る可能性もあります。
また、税理士事務所に依頼する場合は税務申告や顧問契約など幅広いサポートが含まれるケースもあり、長期的に見るとコストパフォーマンスが高い場合も少なくありません。
料金だけでなく、業者の実績・サポート範囲・追加費用などを総合的に検討し、自社に最適なサービスを選ぶことが大切です。
記帳代行の依頼先を選ぶポイント
記帳代行を利用すれば、経理の負担を大幅に減らすことができます。しかし、依頼先によってコストやサポート内容が異なるため、選び方を間違えるとトラブルや追加費用が発生する場合もあります。以下のポイントを押さえながら、自社に合ったサービスを見極めましょう。
資格・実績(税理士資格、経験年数、クチコミなど)
記帳代行を行う事業者には、税理士資格を持つ事務所と、そうでない業者があります。税理士資格のある事務所は税務申告や税務相談まで一括で任せやすいメリットがありますが、その分費用が高めになるケースもあるため、実績やサービス内容を総合的に比較しましょう。また、依頼先が自社と同規模・同業種のクライアントを多く抱えているかどうか、利用者のクチコミなども確認すると、スムーズな対応が期待できます。
セキュリティ・守秘義務への対策
記帳代行では領収書や通帳のコピーなど、機密性の高い資料を扱うことになります。情報漏えいやデータの紛失を防ぐため、セキュリティ管理の仕組みや守秘義務に関する契約内容を必ずチェックしてください。たとえば、暗号化技術の導入や個人情報保護への取り組みが明確になっている事業者であれば、安心して業務を任せられます。
サポート範囲(税務申告、資金繰り相談など)
記帳業務だけでなく、資金繰りや経営相談など、どこまで対応してもらえるかは重要な選択基準です。税理士資格を持つ事務所なら確定申告まで一貫してサポートしてくれる場合が多く、経営状態を踏まえた節税対策の助言も受けやすいでしょう。逆に、記帳代行のみを安価に請け負う業者の場合は、税務書類の作成や相談業務は含まれないケースがあるため、依頼内容を事前に整理しておくことが大切です。
コミュニケーション方法(オンライン・電話・訪問対応)
記帳代行を依頼すると、資料の受け渡しや進捗確認などで定期的にやり取りが発生します。オンラインでのやり取りを中心にしたいのか、電話や対面による打ち合わせが必要なのか、自社のやりやすい方法をあらかじめ決めておきましょう。事業者によって対応可能なコミュニケーション手段が異なるので、契約前に確認しておくとスムーズです。
記帳代行を依頼するタイミング・準備すべきこと
記帳代行の導入は、経理負担の大きさによって判断するのが一般的です。仕訳数が増えて本業に支障をきたしたり、専門知識が足りずに税務リスクを抱えているようなら、早めに検討する価値があります。依頼にあたって必要な書類や情報も事前に整理しておくと、スムーズに業務を進められます。
依頼を検討するべきサイン
仕訳数が増加して経理業務に割く時間が増え、本来の事業活動に支障が出始めたら、記帳代行を検討するよいタイミングです。さらに、会計ソフトを使ってはいるもののミスや漏れが多く、結局修正に追われることが多い場合もアウトソーシングを検討するきっかけになります。加えて、税務申告や決算時期に大きな負担を感じるようであれば、外部の専門家に任せることで業務効率を大幅に高められる可能性があります。
必要書類・情報整理(領収書、請求書、通帳コピーなど)
記帳代行を依頼する際には、領収書や請求書、通帳のコピーなどの一次資料を正確に揃えておく必要があります。資料を時系列や取引先ごとに分類しておくと、代行業者がスムーズに仕訳を行えるだけでなく、確認や修正のやり取りも最小限で済むでしょう。また、経理に関する過去のデータや会計ソフトの設定情報などもまとめておくと、引き継ぎがスムーズになり、導入後すぐに本来の業務へ集中できます。
- 領収書・レシート(経費を証明するため)
- 請求書・納品書(売上・仕入を確認するため)
- 通帳のコピー(入出金履歴の裏付け資料として)
- クレジットカード明細(カード経費を計上するため)
- 現金出納帳(現金管理を明確にするため)
- 給与明細・源泉徴収簿(給与計算や源泉税の処理が必要な場合)
記帳代行の具体的な流れと注意点
記帳代行を利用する際には、初回の相談から書類の受け渡し、最終的なレポート確認まで、いくつかのステップを踏んで進めます。それぞれの段階で押さえておくべきポイントや注意点を理解し、スムーズに業務を進行させましょう。
初回の相談・見積もり取得
まずは依頼先の業者や税理士事務所に連絡し、記帳代行の内容や料金、サポート範囲などを相談します。仕訳数や業務範囲を伝えることでおおよその見積もりを出してもらい、費用対効果を検討する段階です。業者によってはオンラインや電話での無料相談を受け付けているため、複数社を比較検討するのがおすすめです。
業務委託契約の締結
見積もり内容とサービス内容に納得できたら、正式に契約を結びます。ここでは、料金体系や業務範囲、納期、守秘義務、解約条件などを明確にしておきましょう。契約書を取り交わすことで、万が一トラブルが発生した際の対応がスムーズになります。
書類の受け渡し・クラウド会計連携
実際に業務が始まったら、領収書や請求書、通帳のコピーなど必要書類を業者へ渡します。郵送やオンラインストレージなどの受け渡し方法は事業者によって異なり、クラウド会計ソフトを導入している場合はデータの連携で省力化を図ることも可能です。書類の提出タイミングを月次や週次で決めておくと、記帳作業の遅延を防げます。
記帳結果のチェック・レポート
業者が記帳を完了すると、試算表や仕訳データをフィードバックしてくれます。これをもとに経営状況を把握し、必要に応じて修正や追加の情報提供を行います。月次のレポートや会計ソフトの画面をチェックすることで、経理担当者や経営者は常に最新の数字を確認できるようになります。
注意点
記帳代行に任せきりにすると、リアルタイムでの資金繰りや経費状況を把握しづらくなる場合があります。必要書類の提出が遅れれば、経理処理そのものも遅延するため、定期的なコミュニケーションが欠かせません。また、対面での打ち合わせが少ない分、オンラインや電話でのやり取りを頻繁に行い、疑問点や追加要望を素早く共有することが大切です。記帳結果に不明点がある場合は早めに問い合わせ、次回以降の改善に活かしましょう。
自力での会計ソフト入力 vs. 記帳代行の比較
事業の規模や状況によっては、会計ソフトを導入し自力で記帳するのか、プロに任せて効率化を図るのか迷うところです。どちらにもメリット・デメリットがあり、コストや手間、精度の面で差が出ることがあります。ここでは両者の特徴を比較し、自社に合った方法を検討できるように整理しました。
会計ソフトで自計化する場合
市販の会計ソフトを利用すれば、比較的安価に自力で帳簿を作成できます。多くのソフトがクラウド対応しているため、パソコンやスマートフォンからいつでも入力・確認が可能です。リアルタイムで経営状況を把握しやすく、データの連携や自動仕訳機能を活用すれば、入力作業の負担を軽減できます。
ただし、仕訳の知識が不足していると操作や設定でミスを起こしやすいのが難点です。入力ミスや勘定科目の誤設定によって、決算時に修正作業が増えるケースもあるため、最低限の簿記知識やITリテラシーが求められます。税務申告や難しい経理処理は、最終的に専門家へ相談が必要になることもあるでしょう。
記帳代行で時短・効率化を狙う場合
記帳代行を活用すれば、面倒な仕訳や帳簿入力作業をプロに一任できるため、経営者や担当者は本業に集中しやすくなります。帳簿の正確性が向上し、税務申告や融資審査の際にも安心感が得られる点が大きなメリットです。会計ソフトの導入や設定についてもアドバイスを受けられる場合があるため、初期の立ち上げ段階から手間を省けます。
一方、依頼する範囲や仕訳数に応じてコストが膨らむ可能性があり、コミュニケーション不足だと経営状況をリアルタイムで把握しにくいというリスクもあります。自社の経理担当者との役割分担を明確にし、月次レポートの確認や追加書類の提出をこまめに行うなど、頻繁なコミュニケーションを心がけることでデメリットを最小限に抑えられるでしょう。
それぞれの向き・不向き
会計ソフトによる自計化は、事業規模が小さく取引数が少ないうちは負担が軽く、コストを安く抑えやすい一方、正確な仕訳や税務対応に自信がない場合は後々の修正作業で苦労する恐れがあります。記帳代行は、仕訳の正確性と専門家によるサポートを確保できる反面、ランニングコストがかかりがちです。予算や経理担当のリソース、税務面のリスクを総合的に考え、どの方法が自社に適しているか慎重に判断しましょう。
失敗しない記帳代行の活用ポイント
記帳代行を導入すれば、経理の負担を軽減しながら正確な帳簿管理を実現できます。ただし、依頼範囲やコミュニケーション方法を間違えると、追加コストや作業の遅れが発生することもあるため注意が必要です。以下のポイントを押さえておけば、失敗を避けつつ効果的に記帳代行を活用できるでしょう。
契約範囲・費用の明確化
記帳代行と一口にいっても、対応範囲や料金設定は業者ごとに異なります。たとえば仕訳数が一定数を超えると追加費用がかかったり、税務申告や給与計算などはオプション料金になることも。サービス内容を細かく確認し、見積もりの段階で不明点を解消しておくと、後から予想外のコストが発生するリスクを抑えられます。
定期的なコミュニケーションの重要性
記帳代行を利用する場合、領収書や請求書などの書類提出が遅れると、試算表や月次レポートの作成も遅れがちになります。経営判断に使う数字は、リアルタイムで把握してこそ価値があるため、業者との連絡頻度や書類提出のタイミングを明確に決めておきましょう。オンライン会議やチャットツールを活用すれば、疑問点や追加情報のやり取りをスムーズに行えます。
データ連携とクラウド活用
クラウド会計ソフトやオンラインストレージを活用すると、書類の受け渡しや仕訳作業を効率化できるうえ、リアルタイムで進捗や残高を確認しやすくなります。オフィスにいなくても必要なデータを確認できるため、経理担当者や経営者がどこにいても状況を把握可能です。依頼先の業者が使用しているツールやシステムと自社の環境を連携させることで、業務の無駄が大幅に減り、正確かつスピーディな対応が実現します。

中川 麻未
監修税理士からのワンポイントアドバイス
1.契約時に試算表の報告頻度を確認する
契約時は、金額だけでなく、試算表の報告頻度、つまりレシートを渡す期限や、会計事務所が試算表を作成する期限を確認しましょう。
月次報告や定期的な面談の有無など、記帳内容に問題がないかどうかを随時確認するための仕組みが整っているかも重要です。
2. 税理士に事業内容や経費内容をきちんと伝える
税理士は税金のプロではありますが、お客さんの事業内容を詳しく知っているわけではないので、レシートの内容を見て、プライベート用途なのか事業用途なのかを判別できないこともあります。
税理士に記帳代行を丸投げしていると、「おそらくこれはプライベート用だろう」と判断されて経費から除外されてしまうケースもあります。
一般的にプライベート用だと判断されるレシート(アミューズメント施設、コスメ等)であっても、実は立派な経費ということもあります。
例えば、コスメ系の配信をされるYouTuberの方であれば、コスメ関係の領収書も一定割合経費に入れることもできます。
このように、「レシートを渡せば税理士が正しく処理してくれる」というわけではなく、事業内容を税理士に正しく伝えたり、レシートに手書きで「〇〇に利用」など経費であることを伝えるなど、工夫が必要です。
まとめ
記帳代行を活用すれば、面倒な経理作業を専門家に任せ、本業に専念できるだけでなく、正確な帳簿管理と税務対応を実現できます。
一方で、費用面の負担やコミュニケーション不足、リアルタイムでの経営数値の把握が難しくなるリスクもあるため、依頼範囲や料金、サポート内容をしっかり確認したうえで導入を検討することが重要です。
特に税務申告や資金繰り相談までカバーできる税理士事務所に依頼する場合は、コストだけでなく「総合的なメリット」も評価し、長期的なコストパフォーマンスを考慮して選びましょう。
税理士を探すなら、専門家の紹介サービスがおすすめ
もし「税理士に記帳代行を頼みたい」「自社の状況に合ったプロを探したい」とお考えなら、税理士紹介サービスの活用も検討してみてください。
ご希望の地域や業種、予算などに合った税理士事務所を紹介してもらえるため、スムーズに比較・検討が進められます。
実績のある税理士なら、記帳や経理だけでなく、節税や経営アドバイスといった部分までトータルでサポートを提供してくれるはずです。
本業に集中しながら、安心して経理・税務を任せたい方は、ぜひ一度、税理士紹介サービスを活用してみてはいかがでしょうか。
税理士紹介センタービスカスでは、記帳代行に対応できる税理士を完全無料でご紹介しています。【こんなお悩みありませんか?】
- 予算の範囲内で、記帳代行を税理士に依頼したい
- 経理業務の負担を軽くしたい
- 苦手な事務作業を税理士に依頼して、自分は本業に専念したい
- 会計ソフトを上手く使いこなせない
- 税理士探しに時間や費用をかけたくない
記帳代行に対応できる税理士事務所の登録多数!まずは無料でお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)
記帳代行とは何ですか?
記帳代行の料金は、仕訳数や業務範囲によって異なります。一般的には「○仕訳まで月額○円」「1仕訳あたり○円」といった従量制が多いですが、税理士や会計事務所に依頼する場合は税務申告や顧問契約とセットにすると割安になるケースもあります。見積もりを取る際は、仕訳数やオプションの有無を細かく伝え、総額をしっかり確認しましょう。
記帳代行の費用はどのくらいかかりますか?
記帳代行とは、事業の取引記録を代行して帳簿に記載するサービスのことです。税務申告に必要な帳簿を作成するために利用されます。
記帳代行だけ依頼しても、税務申告もやってもらえますか?
記帳代行業者の場合、税務申告の代行は含まれないことが多いです。税理士資格を持つ事務所なら、記帳に加えて申告書の作成や提出代行までワンストップで対応可能です。ただし、別途オプション料金がかかるケースもあるため、契約範囲を明確に確認しておきましょう。
会計ソフトを使っているのですが、途中から記帳代行に切り替えても大丈夫?
すでに会計ソフトを導入している場合でも、途中から記帳代行に切り替えることは可能です。仕訳データや設定情報を引き継いで作業してもらえるため、過去の帳簿との整合性も保ちやすくなります。クラウド会計を使っているなら、オンライン連携によってさらにスムーズに引き継ぎができます。
領収書や請求書は紙ではなくデータでも問題ありませんか?
多くの代行業者や税理士事務所がPDFや画像などデジタルデータでの提出を受け付けています。電子帳簿保存法に準拠した形式で保管すれば問題なく処理可能です。ただし、事前に業者へ確認しておくとスムーズにやり取りできます。
リアルタイムで経営数値を知りたい場合、どうすればいいですか?
記帳代行では月次や週次で帳簿を作成することが多いため、リアルタイム把握が難しくなりがちです。
ただし、クラウド会計ソフトと連携し、領収書や請求書を都度アップロードする運用体制を整えれば、ほぼリアルタイムでデータを共有できます。あらかじめ業者とのコミュニケーション頻度を決め、タイムリーに資料を渡すことが重要です。
税理士紹介サービスはどう活用すればいいですか?
初めて税理士や会計事務所を探す場合は、税理士紹介サービスを利用するとスムーズです。希望の地域や業種、予算などに合った事務所を提案してもらえるため、自社にぴったり合う専門家を見つけやすくなります。合いそうな事務所を複数紹介してもらい、費用や得意分野を比較検討してみましょう。