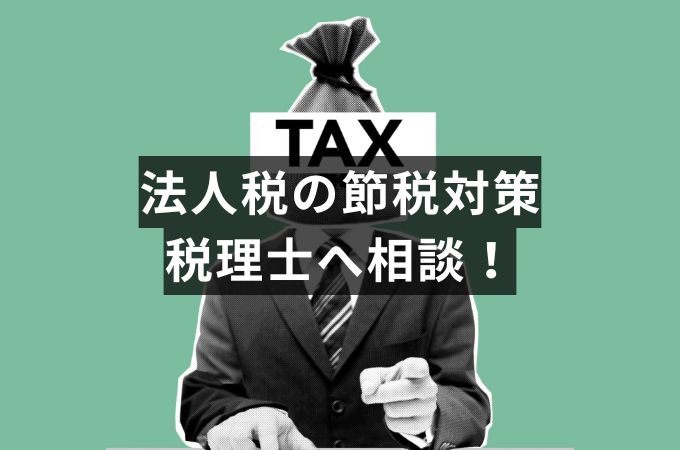法人税とは?法人にかかる税金の種類・計算方法・申告手続きまで徹底解説

- 最終更新日:
- 2025/01/29

- この記事の監修者
- 髙谷公認会計士・税理士事務所
代表 髙谷 武司(税理士・公認会計士)
法人税の基礎知識
法人税とは?
法人税とは、法人の事業活動によって得られた所得に課される国税です。株式会社や合同会社などの法人が稼得した利益に対して、一定の税率で課税される仕組みとなっています。
法人の種類や規模によって課税関係は異なります。一般的な営利法人(株式会社・合同会社など)は原則としてすべての所得が課税対象となりますが、NPO法人や公益法人は収益事業から生じた所得のみが課税対象となります。
法人税率と課税所得の考え方
法人税率は、法人の規模によって異なります。資本金が1億円以下の中小法人の場合、年間所得のうち800万円以下の部分には軽減税率15%が適用され、800万円を超える部分には23.2%の税率が適用されます。一方、資本金1億円超の大法人は、所得金額にかかわらず一律23.2%の税率となります。
課税所得の計算では、企業会計上の利益をベースとしながらも、税法特有の調整が必要となります。例えば、接待交際費は税務上で経費として認められる金額に制限があり、役員給与も事前に定めた金額を超過する部分は原則として経費として認められません。
法人にかかる主な税金の一覧
法人税は、法人にかかる税金の一つに過ぎません。実際の経営では、以下のような税金も併せて負担する必要があります。
法人住民税は、地方自治体の行政サービスを受けるために課される税金です。都道府県民税と市町村民税があり、法人税額を基準とした法人税割と、一定額を納める均等割があります。均等割は赤字でも納める必要があります。
法人事業税は、地方自治体が提供するインフラやサービスの対価として課される税金です。所得金額を基準に計算され、業種や事業規模によって税率が異なります。
このほかにも、固定資産税(土地・建物などを保有する場合)や、償却資産税(機械設備などを保有する場合)、印紙税(契約書の作成時)など、事業活動に応じて様々な税金が発生します。事前に把握して、適切な納税準備をすることが重要です。
個人事業主との税金の違い
個人事業主にかかる代表的な税金
法人化のメリット・デメリット
税務面では、所得が増えても税率が一定というメリットがあります。中小法人の場合、所得800万円以下は15%、超過分は23.2%という税率が適用されます。また、役員報酬を経費として計上できることや、退職給与引当金などの各種引当金制度を活用できることも大きな利点です。
ただし、法人化に伴う主なコストとして以下の項目を考慮する必要があります:
設立時の必要経費:
- 定款認証費用:5万円
- 登録免許税:資本金の0.7%(最低15万円)
- その他諸費用:印鑑作成、銀行口座開設など
さらに法人として運営していく上では、社会保険料の事業主負担(月額給与の約15%)や労働保険料が毎月の固定費として発生します。また、適切な経理処理のために税理士に依頼する場合は、月額5万円程度からの顧問料と会計ソフトの利用料も考慮する必要があります。
法人成り(個人→法人)する際の注意点
個人事業から法人への移行には、細かな実務的対応が必要です。まず、以下の届出を期限内に行うことが重要です:
主な届出と期限:
- 個人事業の廃業届:廃業後1か月以内
- 法人設立届出書:設立後2か月以内
- 青色申告の承認申請書:設立後3か月以内
事業用資産の移行も慎重に進める必要があります。現金・預金の移管方法を決め、在庫商品の評価方法を選択し、固定資産の時価評価を行います。また、売掛金・買掛金の引継ぎ方法も検討が必要です。
損益の引継ぎに関しては特に注意が必要です。個人事業の繰越損失は法人へ引き継ぐことができません。また、売掛金の回収時期によっては二重課税が発生する可能性もあるため、確定申告の対象期間や消費税の課税期間の調整が重要になります。
法人成りの時期は、事業年度の開始時期に合わせることが望ましいですが、在庫調査や棚卸しのしやすさ、取引先への影響なども考慮して決定します。これらの手続きは、税理士などの専門家と相談しながら進めることで、スムーズな移行が可能となります。
法人化を検討する際に知っておくべき税務上のポイントは?

髙谷 武司
監修税理士からのワンポイントアドバイス
個人事業主が法人成りを検討する目的は、事業を拡大したい場合と節税したい場合の2つが大半です。
このうち、事業を拡大したい場合は、法人成りに伴って増加する社会保険料や税理士報酬などの検討が重要になります。なぜなら、会社の成長によって資金が多く必要となり、資金繰りが重要となるからです。
一方、節税をしたい場合は、法人成りによって、どれだけ節税できるかの検討が重要となります。ここで注意したいのは、中長期的な視点を持つことです。所得税は累進税率であるのに対し、法人税は利益によって税率が変動しません。そのため、安定的に利益を計上できる見込みがないと、法人成りの節税効果が得られない結果となります。
法人税の計算方法
益金・損金とは?
法人税の計算の基本となるのは「益金」と「損金」という考え方です。簡単に言えば、益金は会社の収入に当たるもの、損金は経費に当たるものですが、会計上の収入や経費とは異なる部分があります。
益金には、商品やサービスの販売による売上はもちろん、受取利息、資産売却益、雑収入なども含まれます。一方、損金には仕入費用、人件費、家賃、水道光熱費など、事業活動に必要な支出が含まれます。
ただし、税務上で経費として認められない、または制限される項目もあります。例えば交際費は、中小法人でも年間800万円までしか経費として認められません。また、役員給与も事前に定めた金額を超えると経費として認められないなど、いくつかの制限があります。
赤字の場合の取り扱い
会社が赤字を計上した場合、その年度の法人税は原則として発生しません。しかし、赤字でも必ず支払わなければならない税金があります。
その代表例が法人住民税の均等割です。この税金は企業の規模(資本金の額や従業員数)によって金額が決まり、最も小規模な法人でも年間7万円程度の負担が生じます。
ただし、赤字を出した場合の救済措置として「欠損金の繰越控除」という制度があります。これは、赤字額を10年間にわたって繰り越し、将来の黒字から差し引くことができる制度です。ただし、資本金が1億円超の大法人では、控除できる金額が年間所得の50%までに制限されています。
計算事例(シミュレーション)
実際の法人税額の計算方法を、中小法人の具体例で見てみましょう。
【設定条件】
- 個人事業の廃業届:廃業後1か月以内
- 法人設立届出書:設立後2か月以内
- 青色申告の承認申請書:設立後3か月以内
【法人税の計算】
- 所得800万円以下の部分: 800万円 × 15% = 120万円
- 所得800万円超の部分: 400万円 × 23.2% = 92.8万円
- 法人税額の合計: 120万円 + 92.8万円 = 212.8万円
なお、この金額は法人税の基本税額であり、別途、法人住民税や法人事業税が発生します。例えば法人住民税は、この法人税額に一定の税率を掛けて計算します(地域によって税率は異なります)。また、均等割額も別途加算されます。
このように、法人税の計算は基本的な仕組みは単純ですが、実際の申告時には様々な税務調整が必要となります。そのため、特に決算期を迎えた際は、税理士に相談しながら適切な申告書類を作成することをお勧めします。
法人税を納付しないとどうなる?
延滞金・加算税の発生
法人税の納付が期限を過ぎると、直ちに延滞金と加算税が発生します。延滞金は納付が遅れた期間に応じて日割りで計算され、法定納期限の翌日から納付日までの期間について課されます。具体的には、納期限から2か月以内は年7.3%(令和6年の場合)、2か月経過後は年14.6%の利率で計算されます。
加算税には主に2種類あります。期限内に申告しなかった場合の無申告加算税(税額の15%)と、申告したものの納付が遅れた場合の延滞税(税額の10%)です。特に、税務調査で所得隠しなどが発覚した場合は、これらの加算税が最大で35%まで引き上げられる可能性があります。
督促や滞納処分のリスク
法人税を納付期限までに納めないと、以下のような段階的な対応が取られます。
まず納期限から50日以内に督促状が送付されます。この督促状を無視すると、税務署は滞納処分として、会社の財産を差し押さえることができます。差し押さえの対象となるのは、預金口座、売掛金、不動産、その他の資産です。
さらに深刻なのは、金融機関や取引先に滞納の事実が知られてしまうリスクです。これにより、新規融資が受けられなくなったり、取引条件が厳しくなったりする可能性があります。最悪の場合、取引停止などの事態に発展することもあります。
滞納を防ぐためのポイント
滞納を防ぐための最も重要なポイントは、計画的な資金準備です。具体的な対策として以下のような方法があります。
- 納税資金の確保:毎月の売上の一定割合(例:15~20%程度)を納税準備金として別口座に積み立てていきます。特に、事業年度終了後の決算期には法人税だけでなく、消費税や住民税なども重なることがあるため、余裕を持った準備が必要です。
- 資金繰り管理の徹底:毎月の資金繰り表を作成し、納税時期までに必要な資金がいくらになるかを事前に把握します。特に、季節変動が大きい業種では、繁忙期の利益を閑散期の納税に充てられるよう、計画的な資金管理が重要です。
- 早めの相談・対応:資金繰りが厳しくなりそうな場合は、早めに税理士や税務署に相談することをお勧めします。納期限前であれば、納税の猶予制度を利用できる可能性があります。また、分割納付などの相談にも応じてもらえる場合があります。
滞納は一度発生すると、延滞金や加算税による負担増に加え、事業継続にも大きな影響を及ぼす可能性があります。そのため、適切な経理体制の構築と、計画的な資金管理を心がけることが重要です。
法人税の納付で起こりがちなエピソードはありますか?

髙谷 武司
監修税理士からのワンポイントアドバイス
確定申告は、申告書の作成はもちろん、納税までして初めて完了します。
ただ、申告書の作成で安心して、納税を忘れるパターンがたまにあったりします。例えば、申告書は税理士が代理で作成・申告するが、納税は会社でする場合です。この場合、税理士からの連絡がなかったり、会社では進行期の業務を進めていたりして、前期分の法人税等の納付を忘れてしまうことがあります。
また、予定納税をする場合も納付を忘れることがあります。予定納税の場合、申告書の作成がなく、納付のみとなります。そのため、事前に予定しておかないと、納付を忘れてしまうことがあります。
いずれにせよ、納付漏れは、延滞税や加算税の対象となるため、十分に注意しましょう。
法人税は税理士に相談しよう
税理士に依頼するメリット
法人税の申告は個人の確定申告と比べてはるかに複雑です。税理士に依頼することで、複雑な申告書類の作成を正確に行えるだけでなく、税務調査への対応も安心です。
特に、日々の会計処理や経費計上についての適切なアドバイスを得られることは、経営判断の上でも大きなメリットとなります。また、補助金や助成金の活用、税制改正への対応など、企業の成長に関わる様々な支援を受けることができます。
税理士紹介サービスの活用方法
税理士を探す際は、税理士紹介サービスの活用がお勧めです。例えば、税理士紹介のパイオニアである株式会社ビスカスが運営する税理士紹介センターでは、4,200事務所以上の税理士ネットワークから、企業の状況や要望に最適な税理士を紹介しています。
専任の税理士コーディネーターが、企業規模や業種、予算などを考慮しながら、経験豊富な税理士を厳選。29年の実績で20万件以上の相談実績があり、初回相談は無料で利用できます。
スムーズな申告・納付を実現するために
税理士との効率的な連携のためには、日々の会計処理を正確に行い、不明点は早めに確認することが重要です。また、納税資金の準備も計画的に行う必要があります。
税理士は単なる申告書の作成者ではなく、企業の成長をサポートする重要なビジネスパートナーです。定期的なコミュニケーションを通じて、経営状況の改善や事業の発展につながる関係を築いていくことが大切です。
まとめ
法人税を正しく理解して事業を安定させよう
法人税は事業活動において避けて通れない重要な税金です。売上や利益に応じた税率の違い、個人事業主との税負担の比較、計算方法から納付の流れまで、基本的な仕組みを理解しておくことが経営の安定につながります。
特に重要なのは、法人税は法人住民税や法人事業税など他の税金とも密接に関連していることです。そのため、年間を通じた計画的な資金準備が欠かせません。納税資金の積立てや、資金繰り管理を適切に行うことで、安定した事業運営が可能となります。
困ったら早めに税理士に相談を
法人税の申告は複雑で、専門的な知識が必要です。特に、設立初期や事業拡大期には、適切な税務処理や節税対策が経営に大きな影響を与えます。
税理士紹介センターでは、経験豊富な税理士コーディネーターが企業の状況を丁寧にヒアリングし、最適な税理士を無料で紹介しています。税務の専門家との連携を通じて、正確な申告・納付はもちろん、経営改善やビジネスの発展につながるサポートを受けることができます。
法人税について不安や疑問がある場合は、一人で抱え込まず、ぜひ専門家に相談することをお勧めします。企業の成長ステージに応じた適切なアドバイスを得ることで、より確かな経営の土台を築くことができるでしょう。

- この記事の監修者
- 髙谷公認会計士・税理士事務所
代表 髙谷 武司(税理士・公認会計士)
事務所公式ホームページはこちら
- 税理士・税理士事務所紹介のビスカス
- 税理士探し相談ガイド
- 税金情報 >
- 法人税とは?法人にかかる税金の種類・計算方法・申告手続きまで徹底解説