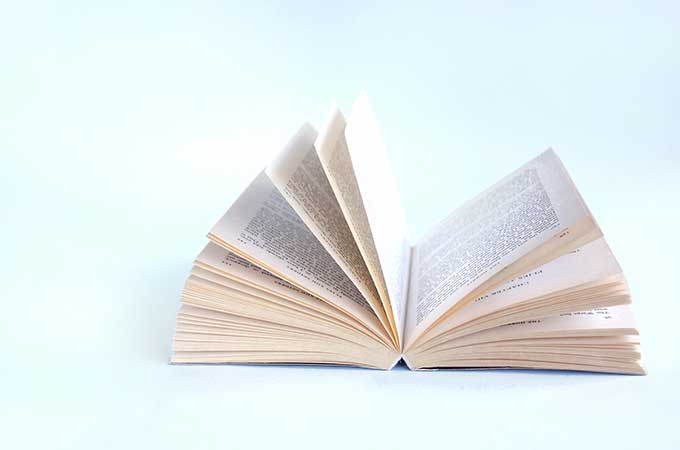仮想通貨の税金を税理士に相談すべき理由|個人事業主・経営者が知るべき節税のポイント
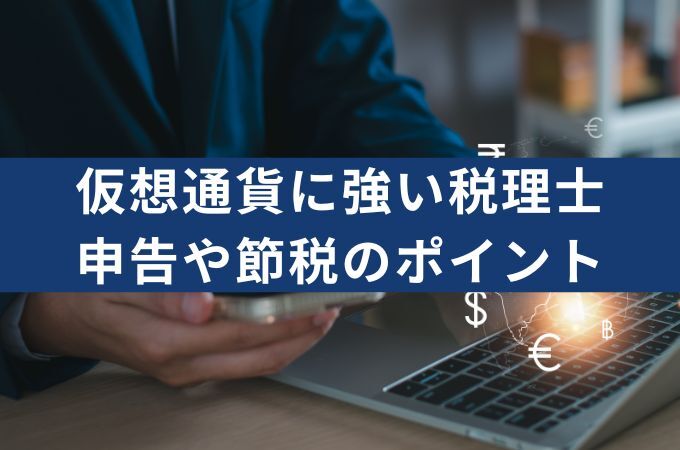
- 最終更新日:
- 2025/03/25

- この記事の監修者
- おだね税理士事務所
代表 小田根 大輔(税理士)
仮想通貨における税理士の役割とは?
仮想通貨取引に関する税務は、一般的な税務とは異なる専門知識が必要です。取引所が複数にまたがる場合や、DeFiやNFTなど、新しい取引形態も増えており、正確な申告を自力で行うのは非常に困難になってきています。ここでは、仮想通貨に強い税理士がどのようなサポートを提供できるのかを解説します。
仮想通貨取引の申告リスクを軽減する専門知識
仮想通貨取引は通常の金融商品と異なり、24時間365日取引が行われ、頻繁な価格変動があります。この特性により、以下のようなリスクが発生します。
仮想通貨取引における申告リスク:
- 取引履歴の網羅的な把握が難しい
- 複数取引所での取引を一元管理する必要がある
- 計算方法(移動平均法・総平均法)の選択と一貫した適用
- 国内外の取引所での取引における為替レート換算の複雑さ
- マイニング報酬やステーキング収入など特殊な収入の区分判断
仮想通貨に精通した税理士は、これらの複雑な状況に対応できる専門知識を持っています。税務調査が入った際にも、適切な書類準備や説明を行い、追徴課税や罰則のリスクを大幅に軽減することができます。
「仮想通貨とは」財産的価値を持つデジタルデータで、法定通貨ではないものの、決済手段や投資対象として利用されるものです。税務上は「暗号資産」と呼ばれ、2019年の税制改正で法律上も「暗号資産」と定義されました。
法人口座や事業としての仮想通貨管理のコツ
個人事業主や法人として仮想通貨を保有・取引する場合は、適切な会計処理が不可欠です。
法人の仮想通貨会計処理ポイント:
- 期末時の仮想通貨評価(時価評価が原則)
- 帳簿への適切な記帳方法
- 取引履歴と証憑書類の保管
- 法人税申告時の注意点
例えば、法人が仮想通貨を保有している場合、活発な市場がある仮想通貨は期末時に時価評価を行い、評価損益を計上する必要があります。また、仮想通貨による給与支払いを行う場合は、支払時点の時価で給与計算を行う必要があります。
これらの複雑な処理を正確に行うには、仮想通貨の税務に詳しい税理士のサポートが効果的です。税理士は最新の税制改正情報も把握しており、常に正確な申告をサポートしてくれます。
仮想通貨の税金基礎知識|申告が必要なケースと仕組み
仮想通貨取引で得た利益は課税対象となりますが、その仕組みを正しく理解している方は意外と少ないものです。ここでは、基本的な仮想通貨の税金知識を解説します。
仮想通貨の課税対象となる主なタイミング
仮想通貨取引では、実に様々なタイミングで課税対象となることを知っておく必要があります。まず法定通貨への換金時はもちろん課税対象ですが、注意すべきなのは仮想通貨同士の交換も課税対象になるという点です。例えばビットコインをイーサリアムに交換した場合、ビットコインの取得価額と交換時の時価との差額に対して課税されます。
また、仮想通貨で商品やサービスを購入した場合も、その時点での仮想通貨の価値と取得価額との差額が課税対象となります。つまり、円に戻さなくても課税対象になるケースが多いのです。
さらに専門的な取引としては、マイニング報酬やステーキング報酬の受け取り時、エアドロップやハードフォークで新しいコインを入手した時、そしてNFT(非代替性トークン)の売買で利益が出た時なども課税対象となります。法定通貨に換金していなくても、取引のタイミングで利益が確定し、納税義務が生じることを忘れないようにしましょう。
所得区分は雑所得?事業所得?法人の場合の扱いは?
仮想通貨取引による所得は、取引の規模や頻度によって所得区分が変わってきます。一般的な個人投資家の場合は「雑所得」として扱われますが、取引頻度が高く、継続的・反復的に行っている場合は「事業所得」と判断される可能性があります。法人の場合は、法人税の課税対象となる「益金」として扱われます。
所得区分による大きな違いは損益通算の可否です。雑所得の場合、他の所得区分(給与所得や不動産所得など)との損益通算はできません。一方、事業所得であれば他の事業所得との損益通算が可能です。また法人の場合は、仮想通貨取引による所得も他の事業による所得と合算して課税されるため、より柔軟な税務処理が可能となります。
所得区分の判断は複雑なケースも多く、税務署の判断によって事後的に変更されるリスクもあります。こうした不確実性を減らすためにも、仮想通貨取引を始める段階から税理士への相談を検討することをおすすめします。
確定申告が必要なケースと免除される例
仮想通貨取引による所得が年間20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。ただし細かな条件によって状況は変わってきます。給与所得がある方で、仮想通貨の年間所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になりますし、給与所得のみの方でも、仮想通貨を含む雑所得の合計が20万円を超えると申告が必要です。
また事業所得として認定される場合は、金額にかかわらず申告が必要になる点も覚えておきましょう。一方、給与所得のみで年間の仮想通貨所得が20万円以下の場合は確定申告が免除される可能性がありますが、自治体によっては住民税の申告が別途必要になることもあります。
特に注意すべきは、たとえ所得が20万円以下であっても、住民税の申告は別途必要な場合があることです。また事業的規模と判断される場合は、20万円以下でも申告が必要になります。自分のケースがどれに該当するのか判断に迷う場合は、税理士に相談することで正確な判断ができるでしょう。
正しい損益計算方法と必要書類の準備
仮想通貨の利益計算は複雑で、多くの投資家が苦労するポイントです。ここでは正確な損益計算方法と、申告時に必要となる書類について解説します。
移動平均法・総平均法を使い分ける際の注意点
仮想通貨の取得価額を計算する方法には、主に「移動平均法」と「総平均法」の2種類があります。移動平均法は取得するたびに平均取得価額を計算する方法で、リアルタイムでの損益把握が容易というメリットがあります。ただし計算が複雑で、取引記録を細かく管理する必要があるというデメリットもあります。
一方、総平均法は売却時点で保有している仮想通貨の平均取得価額を計算する方法です。計算がシンプルというメリットがありますが、取引の都度の損益計算が難しいというデメリットがあります。
重要なのは、一度選択した計算方法は翌年以降も継続して適用しなければならないという点です。途中で変更する場合は税務署への届出が必要になります。また同じ種類の仮想通貨であれば、すべて同じ計算方法を使用する必要があります。
自分の取引スタイルに合った計算方法を選ぶことが大切ですが、判断に迷った場合は税理士に相談するのが賢明です。税理士に依頼すれば、自分の状況に最適な計算方法の選択アドバイスから、実際の計算処理まで一貫してサポートしてもらえます。
取引履歴の収集と保管のポイント
仮想通貨取引の証拠として、各取引所の取引履歴(CSVデータなど)、入出金記録、ウォレット間の送金履歴、取引時の価格証明(スクリーンショットなど)、外部サービスでの計算結果などを収集・保管しておくことが重要です。特に複数の取引所を利用している場合は、取引データの一元管理が欠かせません。
取引所によってはCSVデータのダウンロードが可能ですが、形式が統一されていないため、データの集計には工夫が必要になります。こうした煩雑な作業を効率化するため、多くの税理士事務所では仮想通貨の取引履歴を一元管理できる専用ツールを使用しています。税理士に依頼することで、複雑なデータ集計の手間を大幅に省くことができるでしょう。
経費や手数料の計上で損をしないためのコツ
仮想通貨取引において見落としがちなのが、経費として計上できる各種費用です。取引手数料はもちろん、送金手数料(ガス代など)、取引ツールの利用料、情報収集のための書籍・セミナー費用、取引用PCやスマートフォンの費用(按分)なども、状況によっては経費として認められる可能性があります。
特に注意すべきは取引所間の送金手数料やガス代(イーサリアムネットワーク利用料など)です。これらは一見小さな金額に思えますが、取引を重ねるごとに積み重なり、最終的には大きな金額になることがあります。
税理士に依頼することで、計上可能な経費を漏れなく把握し、適切に処理することができます。特に事業所得と判断される場合は経費計上の範囲が広がるため、税理士のアドバイスを受けることで節税効果を高められるでしょう。
損をしないために注意すべき点は?

小田根 大輔
監修税理士からのワンポイントアドバイス
税理士の視点から重要な注意点として3点挙げさせていただきます。
①所得区分を正しく理解する
・暗号資産取引による所得は、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されますが、取引の規模、事業内容により事業所得として申告することも可能です。
・所得区分により、損益通算の可否や経費として計上できる範囲が異なるため、ご自身の取引状況を正しく把握することが重要です。
・法人の場合には、期末時点において保有する暗号資産を時価評価して、評価益が出る場合には法人税が課されることがあります。
②経費の計上を漏れなく適切にする
・売却の際に支払う手数料のほか、インターネット等の回線利用料、パソコン等の購入費用も暗号資産の取引のために直接必要な支出は必要経費に参入できます。
・これらの費用を漏れなく適切に申告することで所得から差引でき税金の発生を抑えることができます。
③税制改正に注意を払う
・令和7年度与党税制改正大綱に暗号資産取引に係る課税についてその見直しを検討すると記載されております。
・最新の税制改正情報を常に把握し、適切な税務処理を行うことが重要です。
仮想通貨の節税対策と税務リスク管理
仮想通貨投資では、適切な節税対策を行いながら、税務リスクを最小化することが重要です。ここでは、仮想通貨投資における節税のポイントと税務リスク管理について詳しく解説します。
損失繰越や通算は可能?個人と法人での違い
仮想通貨取引における損失の扱いは、個人と法人で大きく異なります。個人の場合、雑所得の損失は他の所得との損益通算ができません。また雑所得の損失は翌年以降に繰り越すこともできないため、一度損失が確定すると税務上のメリットは得られなくなります。ただし事業所得と認められ、青色申告をしていれば3年間の損失繰越が可能になります。
一方、法人の場合は仮想通貨取引による損失も他の所得と合算できるうえ、現行制度では青色申告であれば10年間の繰越控除が可能です。このように法人化することで税務上の柔軟性が高まる場合があります。
ただし法人化には設立費用や維持コスト、事務負担などもかかるため、単純に節税だけを目的に法人化するのは得策とは言えません。自分の取引状況や将来計画に基づいて、税理士に相談しながら総合的に判断することが大切です。
仮想通貨専門の税理士が教える節税テクニック
仮想通貨投資における節税テクニックにはさまざまな方法があります。例えば含み損のある仮想通貨を年内に売却して損失を確定させる方法や、複数年にわたって売却計画を立てて一度に大きな利益を出さない方法などが考えられます。また適切な所得区分の選択と申告、経費の適切な計上、取引規模が大きい場合の法人化検討、状況によっては家族への贈与活用なども節税につながる可能性があります。
特に効果的なのは年度をまたいだ計画的な売却です。一度に大量の仮想通貨を売却すると、累進課税により税率が大幅に上がる可能性があります。複数年に分けて売却することで、各年の所得を抑え、結果的に税負担を平準化できるのです。
ただしこうした節税対策を実行する際は、税務上の問題がないか事前に税理士に確認することが重要です。過度な節税策は税務調査のリスクを高める可能性があるため、合法的かつ適切な範囲内で対策を講じることが大切です。
税務調査時に指摘されがちなポイント
仮想通貨取引に関する税務調査では、取引履歴の不備や欠落、計算方法の一貫性の欠如、取得価額の計算ミス、申告漏れの取引(特に仮想通貨間の交換)、マイニング報酬やステーキング報酬の申告漏れ、経費計上の妥当性などがよく指摘されます。
特に注意すべきは、取引所が海外に存在する場合でも、日本の税務当局は国際的な情報交換の枠組みを通じて情報を入手できるという点です。「海外の取引所なら申告しなくても大丈夫」という考えは非常に危険であり、将来的に大きなリスクとなる可能性があります。
税理士に依頼していれば、こうした税務調査のリスクポイントを事前に対策し、調査が入った場合も適切に対応してもらえます。税務のプロである税理士のサポートを受けることで、安心して仮想通貨投資に取り組むことができるでしょう。
税理士に依頼する費用相場とメリット・デメリット
仮想通貨の確定申告を税理士に依頼する際の費用相場と、依頼することのメリット・デメリットについて詳しく解説します。
税理士報酬の一般的な算出方法と注意点
仮想通貨の確定申告に関する税理士報酬は、取引量(年間取引回数)、利用している取引所の数、取引の複雑さ(DeFi、NFTなど)、所得金額、依頼する業務範囲(単純な申告だけか、節税対策も含むか)などの要素によって決まります。
一般的な費用相場としては、基本的な確定申告サポートが5万円〜20万円程度、複数取引所や高頻度取引などの複雑なケースでは20万円〜50万円程度、法人の場合は月額顧問料として3万円〜10万円程度が目安となります。
税理士を選ぶ際は、単に費用の安さだけで判断するのではなく、複数の事務所から見積もりを取り、サービス内容と費用のバランスを比較することが重要です。また初回相談無料の税理士事務所も多いので、まずは相談してみることをおすすめします。
自力での申告と専門家への依頼、どちらが得か?
自力で確定申告を行うか、税理士に依頼するかは、状況によって判断が分かれるところです。自力申告のメリットとしては、費用がかからないことや自分で税務知識を身につけられることが挙げられます。一方でデメリットは、多大な時間と労力が必要なことや、誤った申告をした場合の追徴課税リスク、税務調査への対応負担、そして節税機会を逃してしまう可能性などがあります。
税理士に依頼する場合のメリットは、専門的なアドバイスによる適切な節税が可能になること、確定申告にかかる時間と労力を大幅に節約できること、適切な申告による税務リスクの軽減、税務調査時の専門家によるサポート、そして最新の税制情報に基づいたアドバイスを受けられることなどです。もちろん、費用がかかることや依頼のために必要な情報提供の手間といったデメリットもあります。
特に取引量が多い場合や、DeFi、NFTなど複雑な取引がある場合は、税理士への依頼がコスト以上の価値をもたらす可能性が高いでしょう。また、単に申告作業だけでなく、中長期的な税金対策のアドバイスを受けられることも大きなメリットです。翌年以降の取引プランや法人化の検討など、総合的な資産形成戦略についてのサポートを受けることができるのは、専門家に依頼する大きな利点といえるでしょう。
税理士に依頼する際のポイントは?

小田根 大輔
監修税理士からのワンポイントアドバイス
暗号資産に関する税理士への依頼で気をつけるべき点は以下の通りです。
①暗号資産に強い税理士を選ぶ
・暗号資産の税法は複雑であり、一般的な税理士でも対応が難しい場合があります。暗号資産の税務に精通した税理士をお選びください。
②料金体系を確認する
・暗号資産の取引量や複雑さ、利用する取引所の数により料金が変わるため事前に見積りをとり、料金体系を確認するようにしましょう。
③コミュニケーションが取りやすい
・暗号資産の税務は専門用語が多く、分かりにくい場合がありますので、質問に丁寧に答えてくれるコミュニケーションが取りやすい税理士をお選びください。
④税務調査に対応できる
・万が一、税務調査が入った場合に適切に対応してくれるかどうか事前に確認しましょう。
仮想通貨に精通した税理士の探し方
ただ「税理士」といっても、仮想通貨の税務に強い専門家を見つけることが重要です。以下に効果的な探し方を紹介します。
仮想通貨に詳しい税理士を見つけるステップ:
- 専門分野を明記しているかチェック(Webサイトで「仮想通貨」「暗号資産」の対応実績の有無)
- 税理士紹介サービスを利用し、「仮想通貨対応可能」と明記されている税理士を探す
- 無料相談を活用して、仮想通貨の税務知識をどの程度持っているか確認する
- 取引履歴の集計や損益計算の方法について具体的な質問をして対応力を見る
税理士紹介センタービスカスでは、全国4,200所以上の税理士事務所の中から、お客様の状況や要望に合わせて最適な税理士を紹介しています。仮想通貨の税務に強い税理士を探す場合も、専任の税理士コーディネーターが適切な税理士をご紹介可能です。
まとめ
仮想通貨の税務は複雑で、自力での対応は時間と労力がかかるだけでなく、誤った申告によるリスクも伴います。特に個人事業主や経営者の方は、所得区分の判断や法人化の検討など、専門的な判断が必要なケースが多いでしょう。
本記事の重要ポイント:
- 仮想通貨取引は様々なタイミングで課税対象となる
- 所得区分(雑所得か事業所得か)によって税負担が大きく変わる
- 損益計算方法は継続して適用する必要がある
- 取引履歴の保管は税務調査対策として不可欠
- 個人と法人では損失の扱いが大きく異なる
- 適切な節税対策には専門知識が必要
特に複雑な仮想通貨取引を行っている方は、年内に一度税理士に相談することで、年末までの対策を講じる時間的余裕が生まれます。
まずは無料相談から始めて、ご自身の状況に合った税理士を見つけましょう。適切な税務サポートを受けることで、安心して仮想通貨投資に取り組むことができます。

- この記事の監修者
- おだね税理士事務所
代表 小田根 大輔(税理士)
事務所公式ホームページはこちら
- 税理士・税理士事務所紹介のビスカス
- 税理士探し相談ガイド
- 税金情報 >
- 仮想通貨の税金を税理士に相談すべき理由|個人事業主・経営者が知るべき節税のポイント