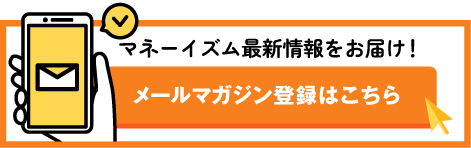一般的に退職した労働者には、あらかじめ定めていた労働契約を元に、退職手当が支給されます。この退職金は税務上、通常の賃金と同様に扱ってもよいのでしょうか。今回は退職手当と源泉徴収について、特殊な例まで詳しく解説していきます。
退職所得とは?
退職手当などの、退職を機に労働者へ一時に支払われる給与は、税法上では退職所得と呼ばれ、課税の対象となります。退職所得には各種社会保険制度による一時金なども含まれ、該当する所得は多岐にわたりますが、原則として退職しなければ支払われなかったものに限られます。従って退職者に支払われた給与であっても、他の引き続き勤務している労働者へ支払う賞与等と同質のものであると認められる場合には、退職所得ではなく給与所得とされます。逆に定年退職後にも引き続き勤務する労働者や、使用人から執行役員になった人に対して、定年までの、あるいは使用人としての勤続期間に基づいて支払われる一時金は、退職手当等と同等に扱われ、退職所得に含まれます。
源泉徴収の方法
退職所得は、実際に退職者へ支払われる前に所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されますが、退職者自身から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けているかどうかで源泉徴収額の計算方法が異なります。退職者から受理した「退職所得の受給に関する申告書」はその後、支払い先の税務署長や住所地の市町村長から提出を求められた場合を除いて、会社側が保管します。これは、税務調査を受ける際に税務署への提示を求められる場合があるためです。
「退職所得の受給に関する申告書」がある場合とない場合では退職所得にかかる所得税額が大きく変わるため、「退職所得の受給に関する申告書」は重要なものになってきます。以下では具体的にその違いを見ていきましょう。
「退職所得の受給に関する申告書」がある場合
「退職所得の受給に関する申告書」が提出されている場合、所得税等が課せられる課税退職所得金額は、次の式によって計算されます。
(収入金額-退職所得控除額)×0.5=課税退職所得金額
退職所得控除額は、勤務年数に応じて額が変わります。勤続年数が20年以下の場合、その年数に40万円をかけた額が退職所得控除額となり、収入金額が80万円を下回る際には非課税になります。勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は以下のように求められます。
800万円+70万円×(勤続年数-20年)=退職所得控除額
なお、いずれの場合も1年に満たない勤続年数の端数は切り上げて計算されます。
以上で得られた課税退職所得金額を基に、次の計算を行うことによって、源泉徴収で引かれる税額が求められます。
(課税退職所得金額×所得税率-控除額)×102.1%=税額
上記の計算式において用いられる所得税率と控除額は、課税退職所得金額の額に応じて変動します。以下の速算表をご覧ください。
| 課税退職所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
「退職所得の受給に関する申告書」がない場合
「退職所得の受給に関する申告書」が提出されない場合、退職者は退職所得控除を受けることができません。退職金等の支給額がそのまま課税対象となり、通常の所得税率及び復興特別所得税率の20.42%をかけることで税額が求められます。
「退職所得の受給に関する申告書」の有無による税額の違い
それでは、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合としない場合とでは、源泉徴収額にどれほどの違いが出るのでしょうか。勤続年数29年5ヶ月で、退職手当として2,000万円が支給されるというケースを基に比較してみましょう。
1.「退職所得の受給に関する申告書」がある場合
まずは退職所得控除を求めます。勤続年数は端数を切り上げて30年として計算します。
800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
次いで、課税退職所得金額を求めましょう。
(2,000万円-1,500万円)×0.5=250万円
上掲の速算表にある通り、この場合の所得税率は10%、控除額は97,500円となります。従って税額は、
(250万円×10%-97,500円)×102.1%=155,702.5円
であり、小数点以下は切り捨てで155,702円となります。
2.「退職所得の受給に関する申告書」がない場合
この場合、支給額に通常の所得税率がかけられますので、税額は、
2,000万円×20.42%=4,084,000円
となります。
以上から、「退職所得の受給に関する申告書」の有無によって、実に26倍以上の差が出ることになります。これは逆から言えば、申告書さえ提出すれば税額を大きく抑えることができるということであり、退職所得は通常の給与と比べて、所得税上かなり優遇されていると言うことができます。この措置は、一般的に退職金が老後の生活に充てられることが多いことを考慮したものです。
こんな場合はどうなる? 特殊なケース
同じ年に複数の会社から退職金が支給される場合
退職金を支払う際に、すでに当該の退職者が同じ年に他の会社や企業年金基金などから、退職所得に含まれる手当や一時金を受給している場合があります。このような場合に支払者は、他の支払者が支払った退職手当等も含めて、源泉徴収額を計算する必要があります。上記の通り、退職金を支払う際には退職者から「退職所得の受給に関する申告書」を受け取りますが、その年中に他の支払者から支払済の退職手当等がある場合、申告書には、その支払済の退職手当等の支払者の氏名または名称、退職手当等の額、源泉徴収された税額、支払年月日及び勤続年数などを記入し、さらにその支払済の退職手当等の「退職所得の源泉徴収票」と一緒に提出しなければなりません。
この場合の源泉徴収額の求め方は、基本的に上記の通常のものと手順や計算式に違いはありませんが、以下の点が異なりますので注意が必要です。
1.退職所得の収入金額は、すでに支払われている他の退職手当の額と、今回の退職手当の額の合計額です。
2.勤続年数は、支払済みの他の退職手当の勤続期間と今回の退職手当の勤続期間のうち、最も長いものを選びます。ただし、当該の勤続期間と重複していない期間が、他の勤続期間内に含まれる場合は、その重複していない部分の期間を、最も長い勤続期間に足したものを勤続年数とします。
3.退職所得控除額を求めた際、本年分の退職手当等が前年以前に支払われた退職手当等の勤続期間を通算して計算されている場合や、前年以前の4年間に他の支払者から支払われた退職手当等がある場合には、重複する期間の年数に基づいて計算した退職所得控除に相当する額を、今回の分の退職所得控除額から引きます。
4.以上を踏まえて求められた今回の退職手当に課される税額から、支払済みの退職手当の源泉徴収額を引いた額が、最終的な源泉徴収額となります。この額がマイナスになる場合、源泉徴収される額はゼロになりますが、マイナス分の還付を受けるには退職者本人が確定申告を行う必要があります。
では、同じ年に次の2社を退職したというケースを検討してみましょう。
 |
A社 就職日:平成19年4月1日 退職日:平成28年3月31日
退職手当支給月:平成28年5月
退職手当支給額:400万円 |
 |
B社 就職日:平成21年4月1日 退職日:平成28年7月31日
退職手当支給月:平成28年9月 |
まずA社が先に退職者に退職金を支払うので、A社は自社が支払う退職手当のみに関わる「退職所得の受給に関する申告書」を受け取ります。勤続年数は9年、退職所得控除額は40万円×9年で360万円ですので、課税退職所得金額は、
(400万円-360万円)×0.5=20万円
となります。
従って、所得税率と控除額はそれぞれ5%、0円となり、税額は、
(20万円×5%-0円)×102.1%=10,210円
となります。
次にB社ですが、上記の通りB社は、A社が交付した「退職所得の源泉徴収票」を「退職所得の受給に関する申告書」と一緒に受け取る必要があります。またB社の勤続年数は平成21年4月1日から平成28年7月31日の7年4ヶ月になるので、A社の勤続期間の方が長いことになります。従って、A社と重複しないB社の勤続期間とA社の勤続期間を足した年数を勤続年数とします。なお、これは最も古い就職の日から今回の退職の日までの期間と同じになりますので、A社に就職した平成19年4月1日からB社を退職した平成28年7月31日までの9年4か月となり、端数を切り上げて勤続年数は10年と計算されます。よって退職所得控除額は、40万円×10年で400万円になります。
次に課税退職所得金額を求めますが、収入金額はA社とB社の退職手当の合計を用いるので、
{(400万円+180万円)-400万円}×0.5=90万円
となります。
従って、ここでも所得税率と控除額はそれぞれ5%、0円ですので、税額は、
(90万円×5%-0円)×102.1%=45,945円
と計算されます。
そして最後に、この額からA社で源泉徴収された10,210円を引いた額、すなわち35,735円が、B社が源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の額となります。
退職者が特定役員として5年以下勤務していた場合
課税退職所得金額は通常、収入金額から勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を引いた残額の2分の1とされていますが、役員等としての勤続年数が5年以下でその勤続年数に応じた退職金を受け取る場合は、その限りではありません。退職手当が役員退職手当のみであるかどうか、役員退職手当以外のものが含まれるのであれば重複期間があるかどうかで、課税退職所得金額の求め方が異なります。
-
支払われる退職手当等が特定役員退職手当のみの場合
この場合の課税退職所得金額は、次の式によって求めます。
特定役員退職手当の収入金額-退職所得控除額
-
退職手当が特定役員退職手当と特定役員退職手当以外の退職手当の場合
この場合の課税退職所得金額は、次の2つを合計したものとなります。
特定役員退職手当の収入金額-特定役員退職所得控除額
{退職手当の収入金額-(退職所得控除額-特定役員退職所得控除額)}×0.5
どちらの式にもある特定役員退職所得控除額は次のように求めますが、役員の勤続期間と役員でない勤続期間に重複がある場合は調整計算を行うので、重複がない場合とは計算方法が異なります。
-
重複期間がある場合
40万円×(特定役員勤続年数-重複勤続年数)+20万円×重複勤続年数
-
重複期間がない場合
40万円×特定役員勤続年数
以上を踏まえ、次の2つのケースで課税退職所得金額がいくらになるかを見てみましょう。
-
ケース① 使用人として20年勤務し、その後役員に就任して5年間勤務した後に退職
使用人退職金 1,000万円 役員退職金800万円
勤続年数:25年(うち役員勤続年数5年)
この場合、勤続年数が20年を超えるので退職所得控除額は、
800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円
となります。
使用人としての雇用期間と役員としての雇用期間に重複がないため、特定役員退職所得控除額は、
40万円×5年=200万円
と計算されます。
以上より、このケースの課税退職所得金額は、
(800万円-200万円)+{1,000万円-(1,150万円-200万円)}×0.5=625万円
となります。
-
ケース② 使用人として10年勤務した後、使用人兼務役員に就任して2年間勤務、その後3年間は役員専任として勤務し退職
使用人退職金(使用人兼務役員期間の使用人部分を含む)1,500万円
役員退職金(使用人兼務役員期間の役員部分を含む)1,000万円
勤続年数15年(うち役員勤続年数は使用人兼務役員の期間2年と役員専任
期間3年の合計5年)
この場合、勤続年数は20年を下回るため、退職所得控除額は
40万円×15年=600万円
となります。
特定役員退職所得控除額については、このケースでは使用人兼務役員の期間が2年間あるため、上記の調整計算を行います。
40万円×(5年-2年)+20万円×2年=160万円
以上より、ケース②の課税退職所得金額は、
(1,000万円-160万円)+{1,500万円-(600万円-160万円)}×0.5=1,370万円
となります。
まとめ
退職金の源泉徴収額の計算は、最後に扱ったような特殊なケースに関しては確かに複雑な計算が必要になりますが、基本となる通常の計算は、思ったほど難しくないということが分かって頂けたのではないでしょうか。記事中で述べたように、退職所得に課せられる所得税は通常より低い額となっています。しかしこれには「退職所得の受給の関する申請書」が必要ですので、退職者には必ず提出させるようにしましょう。