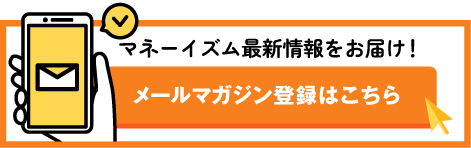「会社の解散」を会社の消滅と考える方が多いようです。しかし、実際には、解散決議から会社の消滅までには長期にわたる手続が必要ですから、その間は清算中の会社の存在を認めて毎期確定申告を義務付けています。本稿では、「会社の解散」を「会社の解散+清算」と考え、その間に納付すべき税金について解説します。
会社の解散・清算とは
会社を消滅させるための会社の解散
会社の解散とは、あくまでも会社を消滅させるために必要な法的手続きのことです。株式会社は、株主総会の決議ですぐ消滅するものではなく、解散をした会社は清算という目的で存続しているため、清算手続きに移行し、清算手続の終了をもって会社は消滅します。
債務超過でない株式会社が株主総会の特別決議で解散する場合の手続
1.株主総会の特別決議
実質的に債務超過でない株式会社が、株主総会で解散決議を行う場合には、普通決議ではなく特別決議が必要です。特別決議とは、発行済み株式総数の過半数の株式を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもってする決議です。
この株主総会では、清算人の選任も同時に行われます。殆どの場合取締役が清算人に横滑りしています。
解散決議をもって営業活動は停止しますが、解散決議以降は清算手続き終了まで清算中の会社として存続します。
2.解散・清算人選任の登記
解散の日から2週間以内に、法務局で定款、株主総会議事録を添えて解散及び清算人選任登記申請をします。登録免許税(収入印紙)は解散登記が3万円で、清算人選任登記が9千円です。
3.税務署等への解散の届出
会社を解散したら、税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険事務所、ハローワー
ク及び労働基準監督署などへの届出をします。
4.財産目録・貸借対照表の作成
清算人は、会社の財産を調査した上で財産目録及び貸借対照表を作成して株主総会の承認を得なければなりません。なお、ここでの貸借対照表は時価評価に基づく財産法によるもので、後述する清算中の会社で作成する費用の期間配分を重視する損益法によるものではありません。
5.債権者保護手続き
清算人は、会社の債権者に対して、2ヶ月を下らない一定期間内にその債権を申し出るように官報に公告し、存在を把握している債権者に対しては個別に催告を行います。
6.税務署に解散確定申告書を提出
解散日から2ヶ月以内に、事業年度開始日から解散日までの期間をみなし事業年度として確定申告を行います。これを、解散事業年度の確定申告といいます。
7.残余財産の確定、分配
清算人は、売掛金や貸付金などの会社債権があればこれを取り立てて回収し、買掛金や借入金などの会社債務を支払います。
会社の解散決議により、会社は営業活動を停止して、上記の債権債務の整理のためだけに存続を認められます。これは、残余財産を分配して清算が済むまで続きます。解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をみなし事業年度として確定申告をしなければなりません、これを清算事業年度の確定申告といいます。
8.税務署へ清算確定申告書を提出
残余財産が確定したら、清算人は株主に分配し清算します。このように残余財産が確定したら清算人は決算報告書を作成し、株主総会を開催して承認を得て、1ヶ月以内に税務署に清算確定申告をおこないます。これを残余財産確定日の属する事業年度の確定申告といいます。
9.清算結了登記
清算結了したら、2週間以内に清算結了の登記を申請する必要があります。清算結了登記が完了すれば、会社の登記簿は閉鎖され、会社は完全に消滅することになります。清算結了の登録免許税は2千円です。登記が完了したら、所轄税務署及び地方公共団体へ異動届出書を提出します。
会社の解散・清算中の会社に係る法人税等の税目
法人税等のうち、法人税法上の利益に基づく税目体系
法人税等といわれる税金を体系的にまとめてみます。
| 国税 | 法人税 | 法人税 | |
| 地方法人税 | |||
| 地方税 | 法人都道府県民税 | 事業税 | 法人事業税 |
| 地方法人特別税 | |||
| 法人都道府県民税 | 法人都道府県民税法人税割 | ||
| 法人都道府県民税均等割 | |||
| 法人市町村民税 | 法人市町村民税法人税割 | ||
| 法人市町村民税均等割 | |||
上記体系図から、
国税・地方税という括りを越えて法人税等は次の3つに分類できます。
法人所得から直に導き出される税目
法人税 = 法人所得 × 税率
法人事業税 = 法人所得 × 税率
法人税額等から導き出される税目
地方法人税 = 法人税額 × 税率
地方法人特別税 = 法人事業税 × 税率
法人都道府県民税法人税割 = 法人税額 × 税率
法人市町村民税法人税割 = 法人税額 × 税率
独立的に導き出される税目
法人都道府県民税均等割、法人市町村民税均等割
法人の所得金額の多少にかかわらず、一定額を課せられる税金のことです。そのため、均等割額は住民税の「基本料金」のようなもので、収入が少ないと均等割額も課されません。
上記から、税法上の利益(所得)がゼロまたはマイナスの場合には、法人所得から直に導き出される税目と法人税額等から導き出される税目では納付税額は算出されないことがわかります。独立的に導き出される均等割額だけが課せられます。
法人の解散・清算に係る事業年度の確定申告
・解散事業年度(申告区分は解散確定申告)
解散決議をした事業年度を解散事業年度といいます。これは事業年度開始の日から解散決議をした日までを一事業年度とするものですから、定款記載の事業年度と必ずしも一致しないケースがあります。解散日を決算日として2ヶ月以内に確定申告書を提出します。
解散事業年度は営業活動継続中の事業年度であり、基本的には継続企業と同様の仕組みで所得計算及び税額計算を行います。解散日までは、営業収益(益金)から営業費用(損金)を控除して所得を算出してこれを課税標準として、通常どおりの確定申告を行います。
ただ、解散決議日が期末日と一致しない場合には、解散事業年度は1年に満たない期間となりますから、減価償却限度額、繰延資産の償却限度額等については月割計算(月賦調整)になります。また、地方税に係る法人住民税均等割についても同様です。
・清算事業年度
解散決議のあった日の翌日から、その事業年度の終了の日までの期間を清算事業年度といいます。この事業年度の期間は、解散の日の翌日から1年間となります。また清算事業年度は残余財産を分配して清算が済むまでなので1年で終わるとは限りません。事業年度終了の日から2ヶ月以内に清算事業年度の確定申告書を提出します。
平成22年度の税制改正で清算所得に対する課税制度が廃止されました。これまでは、法人の清算による残余財産の価額から解散時の資本金等の額と利益積立金額等との合計額を控除した金額が課税標準となり、清算所得に対する法人税が課されていましたが、解散の前後で課税方式が異ならないよう清算所得課税が廃止され、会社が解散した後においても解散前と同様に益金から損金を控除して所得を求め、これを課税標準として課税が行われることになりました。
通常は解散決議で営業は停止しますから、営業収益(益金)はゼロで営業収益に直接対応する費用(損金)もゼロとなります。しかし、減価償却限度額、繰延資産の償却限度額等の期間費用と会社清算に係る報酬、退職金、手数料等のみ経費として発生しますから赤字決算となります。
赤字決算では、地方税に係る法人住民税均等割だけが課せられることになります。
・残余財産確定日の属する事業年度
清算事業年度の途中で残余財産が確定した場合には、その事業年度の開始の日から残余財産確定日までの期間を清算最終事業年度とみなして、残余財産確定日の属する事業年度といいます。
これも清算事業年度ですから、通常の損益法により営業収益(益金)から営業費用(損金)を控除して所得を算出する方式をとります。そのため、営業収益(益金)はゼロで営業収益に直接対応する費用(損金)もゼロとなります。しかし、減価償却限度額、繰延資産の償却限度額等の期間費用は発生しますから赤字決算となります。赤字決算では、地方税の法人住民税均等割だけが課せられます。しかし、残余財産確定日と定款記載の決算日とは一致しないケースが一般的ですから、減価償却費等の期間費用については月割計算(月賦調整)となります。
残余財産確定の日は明文化されていませんが、全ての資産の価値を評価して換価し、債務を弁済することによって確定しますから、これら全てが完了した日と考えられます。残余財産確定後1ヶ月以内に清算確定申告を行います。
まとめ
解散・清算に伴い、3種類の確定申告をしなければなりません。通常の会計年度と同様に、益金から損金を控除して課税標準所得を算出して税額を計算します。平成22年度の税制改正で清算所得に対する課税制度が廃止されました。解散の前後で課税方式が異ならないよう清算所得課税が廃止され、会社が解散した後においても、通常の所得計算方式によって算出された所得に対して課税が行われることになりました。
解散によって営業活動は停止するため、一般的には益金も損金も発生しませんが、小規模会社の場合、元代表者から債務免除を受けるケースがあると損益計算書上黒字となります。実質的に数字上は黒字でも残余財産がないケースなので繰越欠損金を利用すると納税が生じませんし、繰越欠損金が存在しない場合でも期限切れの欠損金の利用が認められますので課税とならないケースが多くあります。ただし、清算事業年度に不動産の処分などで、本当の意味で黒字となる場合もあり、そのような場合は普通に法人税等を課せられことになります。