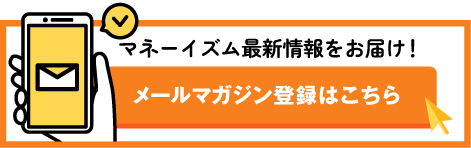インターネット環境が普及している現在では、海外の企業と電子商取引を行っているという会社も多いのではないでしょうか。税負担といえば、国単位で課税されるのが一般的ですが、「国際連帯税」は国境を越えた世界を課税単位とする制度です。今回は「国際連帯税」についての概要について解説していきます。
発展途上国への経済支援と「国際連帯税」
従来の経済支援の考え方
経済援助や技術協力など、以前から先進国が発展途上国に対して行ってきた支援には様々なものがあります。
代表的なものとしては、日本政府が行ってきた発展途上国に対する支援政策の一つであるODA (政府開発援助:Official Development Assistance)があげられるでしょう。
無償の資金提供である「贈与」や、円借款と呼ばれる「有償資金協力」、技術協力など、有償・無償を問わず長年に渡り発展途上国の支援を行っています。
しかし「国が国に対して支援を行う」という仕組みでは、国、ひいては税負担をしている納税者だけが経済支援をしているという形になります。これでは支援をする国としない国の間で不公平感が生まれますし、国単位で支援するにしても財源に限度があります。
食料不足や環境問題などは、自国のみの問題ではなく、地球規模での取り組みが不可欠です。
経済活動に対する課税「国際連帯税」
これに対して「国際連帯税:International Solidarity Levy」の制度趣旨は「国境を越えた地球規模での経済活動を課税客体としよう」という壮大な試みです。
新型コロナウイルス感染症にみられるような世界規模での疫病の蔓延や、地球の温暖化など、現代社会は国家という枠組みを超えた問題を数多く抱えています。
こういった世界規模での問題を解決するためには、国単位での税負担や資金提供だけではなく、問題にかかわる全ての経済活動も資金を負担すべきだ、という考えにより「国際連帯税」の議論が提起されました。
国際連帯税の必要性は以前から提唱されていましたが、税負担の仕組みや国家間の制度運用における協力体制の調整など、超えなければならないハードルが数多くあり導入が遅れていました。しかし、世界規模での問題が深刻化するにつれ参加する国や導入を検討する国が増加しており、一部の「国際連帯税」については既に運用が始まっているものがあるというのが現状です。
「国際連帯税」に対する各国の動き
先進国で導入が進む「国際連帯税」
例えば「国際連帯税」を実際に導入している先進国の動きの一つに「航空券連帯税」というものがあります。
国際線の航空機は国境を越えて各国を往来しているので、地球規模で経済活動を行っているといえます。そこで、搭乗する際の航空券に「国際連帯税」を課税して財源とすることで、世界規模で起こっている問題に資金提供しようというのが「航空券連帯税」導入の趣旨です。
この場合の税負担者は国家ではなく、航空機を利用する乗客になります。我が国のように国民であるというだけで税負担をしていたODAと異なり、利用者が利用した分だけ税負担をすることになりますので公平感は増します。
また、一回の搭乗ごとに課税されるので、世界規模でみれば税負担の回数は国単位の課税と比べて圧倒的に多くなります。
例えば「航空券連帯税」を導入しているフランスであれば「一回の搭乗につき数百円」が課税されており、航空券を購入した日本人の方も既に税負担をしていることになります。
この「航空券連帯税」には現在フランスを中心に十数か国が参加しており、徴収した財源を発展途上国の疫病の治療や予防対策の費用として拠出しています。
わが国における「国際連帯税」の動き
このような国際的な取り組みに対して、我が国の「国際連帯税」導入に対する動きについてみてみましょう。
令和2年度税制改正のなかで、外務省の要望事項として「国際連帯税導入の必要性 」が提起されています。我が国でも「国際連帯税」についての議論は2010年度から継続して行われており、近年中の導入が検討されていました。しかし、新型コロナウイルス感染症による国内経済のダメージ等を考慮し、現在も導入が見送られています。
しかし「航空券連帯税」のように、海外に支社があって航空機の国際線を利用している企業などは既に税負担が発生しています。また、先送りはされましたが「国際連帯税」の議論は今後も国際的に活発化していくであろうことから、将来的には国内においても導入される可能性が高く、経済活動を行う企業にとっては「全く関係ない話」ではなくなることが予想されます。
「国際連帯税」の課税対象
課税対象は「利益」ではなく「経済活動」
「国際連帯税」が国内企業にも影響してくるという理由は、その課税客体が「経済活動」であることが大きく関係してきます。
税負担の一般的なイメージとしては「利益」に対して課税されるのが通常ですが、「国際連帯税」が課税するのは「利益」ではなく企業の「経済活動」だからです。
例えば、法人税や所得税では「利益=課税所得」に税率を乗じて納税額を計算します。仮に赤字であれば税負担はありませんので、法人税や所得税は「利益に対して発生する税負担」です。
これに対して「国際連帯税」が課税対象とするのは「利益」ではなく「経済活動」です。
取引自体の損得とは関係なく、経済活動を一単位として、一つの活動に対して課税しようというのが基本的な考え方です。
どのような業種であっても、利益を生み出すためには必ず経済活動を行わなければなりません。つまり、国内であっても全ての企業に対して「国際連帯税」が課税される可能性があるわけです。
既に導入されている国での取引はもちろん、将来的には、国内においても「経済活動を行ったら課税」ということになり、経営者の方は新たな税負担を考慮する必要があるでしょう。
国際取引を行っている企業は課税される可能性も
では「国際連帯税」が課税対象とする取引について、企業側の観点からいくつか具体例を挙げてみましょう。
例えば、海外との取引があり社員が世界各国を飛び回るような企業があったとします。
社員が航空機を利用して移動したとすれば、先に紹介したとおり航空券に「航空券連帯税」が課税されます。航空券(旅費交通費)の費用を負担しているのが企業であれば、税負担をするのは企業となります。
また、為替取引やデリバティブ取引などの金融取引で利益をあげている投資企業であれば、取引の損得にかかわらず「金融取引税」が課税されることになります。ポイントとしては「一取引ごとに課税される」という点で、膨大な取引を繰り返し行えば行うほど課税されることになります。
「炭素税」は、ガソリンや灯油といった化石燃料に含まれる炭素の量に応じて「国際連帯税」が課税されるというものです。燃料を多く使った企業ほど税負担が増えるという仕組みですので、地球温暖化の原因を生み出した企業が税負担をするという意味では非常に合理的です。
最終的には税負担を少なくするため、化石燃料の消費量を抑えるという方向に進めるのが目的です。
車両は多くの企業にとって必需品であり、ガソリンや軽油といった燃料に課税されるということになれば燃料単価が上がりますので、企業活動に少なからず影響があるといえます。
まとめ
国際取引をしていない企業にとっては「国際連帯税」といわれても、他所の国の話のように思えるかもしれません。しかし、世界というグローバルな観点からみれば国内企業も課税対象の一人であるという考え方を経営者が持つ必要があるでしょう。